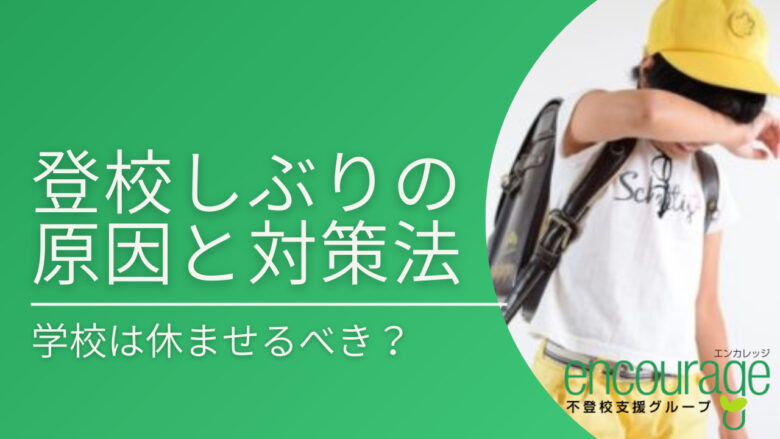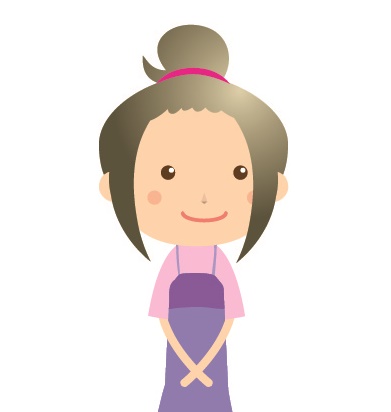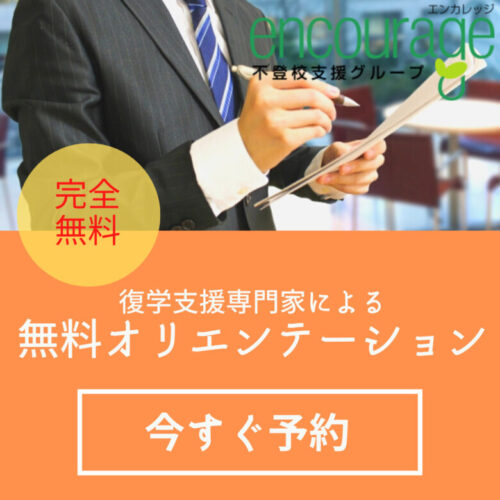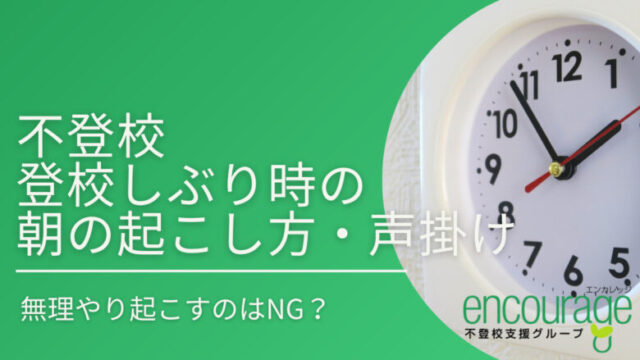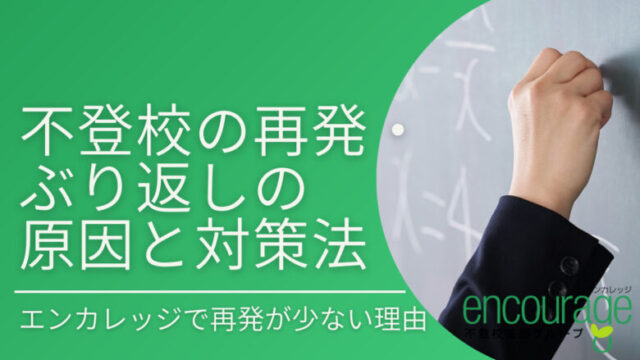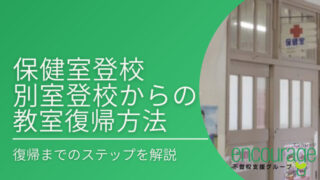最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)
- 兄弟全員が不登校のときは+αの対処法を!親のケアもポイント - 2025年7月3日
- 不登校の子どもに効く!自己肯定感を高める3つの方法 - 2025年6月15日
- 「うちの子が学校に行きたがらない…どうすれば?|不登校の初期対応と親の心構え」 - 2025年5月13日
子どもが急に「学校が嫌だ」とか「学校が怖い」と登校を渋った時は、無理に行かせようとせず休ませた方がいいのでしょうか?
特に朝に突然「行きたくない」と言われると親の方もパニックになって感情的になって怒ってしまう場合も多いです。
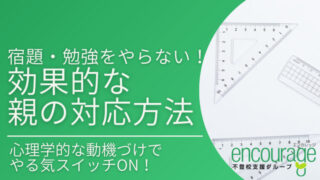
私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1000人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立17年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。
↓不登校の解決に必要な対応をまとめた記事はこちら↓
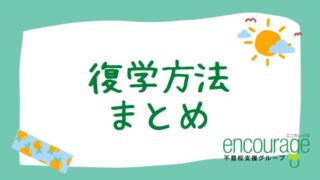
「登校しぶり」の原因

ただ学校に行きたくないだけではなく、しばしば体調不良も一緒に起こる登校しぶり。
登校しぶりはなぜ起きるのでしょうか。代表的な原因を見て行きましょう。
【登校しぶりの原因①】環境の変化

特に新1年生は、幼稚園や保育園という遊びが中心の勉強から、座学中心の勉強へと変化することになります。ルールも増え自己管理もしないといけなくなります。そういった環境の変化に上手く適応できないことで「登校しぶり」につながります。
特に小学1年生の環境ギャップへの戸惑いは大きく「小1プロブレム」とか「小1ギャップ」と呼ばれます。また学年が変わり、クラス替えでメンバーが変わることや担任の先生が代わることなどでも起こります。
特に女の子は女性の担任から男性の担任に代わることで先生を怖いと感じ、登校を渋る子も少なくありません。幼稚園では女性の保育士さんが多いので、男性の先生への免疫の少なさが原因とも言えるでしょう。
最近は優しいお父さんが多いので、男性に叱られるという経験の不足も影響しているかもしれません。
GW明けや夏休みなど長期の休みも環境の変化の1つと位置付けます。そのような様々な環境の変化の戸惑いが「登校しぶり」につながります。
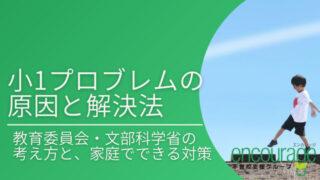
【登校しぶりの原因②】性格傾向

子どもの性格には、不登校になりやすい性格傾向というものがあります。
心配性、神経質、緊張しやすい、わがまま、自己中心的、頑固、感受性が強い、人の目を気にする、プライドが高い、繊細、完璧主義、内弁慶、内向的、怖がり、幼い、依存心が強い、図太い、集団が苦手、甘えん坊などです。
全てがそのまま「登校しぶり」につながるわけではありませんが、そのような性格傾向が影響している可能性はあります。
性格は持って生まれた個性ですが、親の育て方や環境によっても影響されてきます。後者によってそのような性格傾向になってきた場合は、家庭教育を見直していきましょう。
最近は、ひといちばい敏感な子という特性をHSCと呼び、そのようなHSCの傾向がある子は「登校しぶり」になりやすいと言えます。そのような特性に関しても理解して対応していく必要があります。
HSC:生まれつき周りの刺激に敏感で、周りの子よりも傷つきやすかったり不安になりやすかったり、感受性が高かったり思いやりがあったりする特性。
アメリカの心理学者エイレン・アーロン

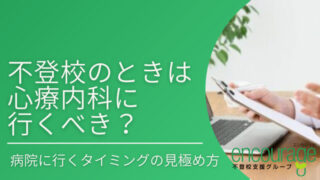
【登校しぶりの原因③】イベントや授業

運動会、水泳、持久走、校外学習、音楽、英語、日直の発表など、苦手なイベントがきっかけで「登校しぶり」につながる場合もあります。
- 日直が苦手で、日直の日をお休みする。
- 翌日は日直の日に休んだので次の日にやらないといけなくなり翌日も休む。
- 2日休んだのでやらなくていいようにしてもらっても行きにくくなったり、休みぐせがついて休みやすい体質になっていく。
先に書いた環境の変化に不登校になりやすい性格傾向が重なると、苦手なイベントをきっかけに「登校しぶり」になるということはよくあります。
「登校しぶり」の対応

登校しぶりは不登校になるかどうかという境目の状況ですので、親側も焦る気持ちが出てくると思います。
子どものことを思えば休ませるべきなのか、それとも励まして何とか行かせるべきなのか、対応方法でも迷われるでしょう。
ここでは親の対応方法についてまとめていきますね。
休ませるべきか?
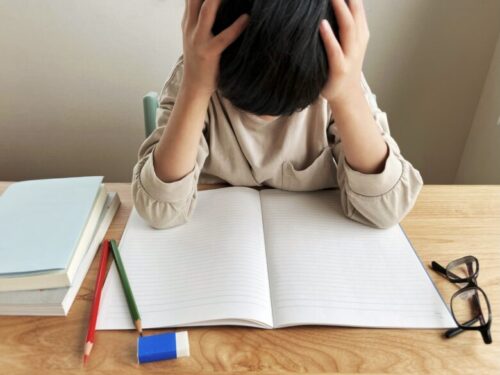
「登校しぶり」になると子どもは精神的に不安定になります。不登校になりだした初期の段階を不登校不安定期と呼びますが、 「登校しぶり」は不登校不安定期の過渡期との位置付けになります。
不登校不安定期は、子どもが荒れて暴力的になったり、ネガティブになり食事をとらなくなったり、小学生はわがままを言うようになったり、甘えて幼くなったりします。
目が吊り上がったり、暗くうつろになったりしますので、無理に行かせると余計に悪化する可能性が高いので無理に行かせないほうがいいのですが、「登校しぶり」の場合は、行きながら改善できる可能性もあるので、逆に安易に休ませるのはよくありません。
スクールカウンセラーや心療内科の先生は、「登校を渋っているのですから無理に行かせないで休ませましょう。エネルギーが回復するまで家で甘えさせてあげましょう。」とおっしゃる方が多いですが、休みが続いてしまうと2次リスクが膨らみ登校がだんだん難しくなっていきます。
教室に入りにくくなり、ちょっと回復しても保健室登校や母子登校で親が教室にいないといけない、別室で待機していないと不安になるといった状況にどんどん後退していきます。
もちろん、過渡期から不安定期になってしまっている場合は休ませないと仕方がないのですが、「登校しぶり」の場合は安易に休ませないということが大切になります。

https://encfutoukou.com/nijirisk/

環境の変化に対する配慮をしてもらう
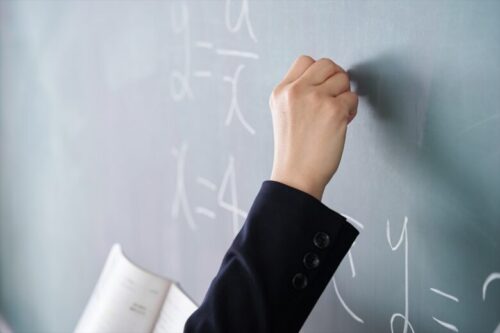
「登校しぶり」はまだそのまま教室復帰できる可能性があるので、ギリギリの状態でも何とか登校を継続し、環境の変化に対する配慮をお願いするといいでしょう。
例えば、担任の先生が男性に代わって怖いと感じる場合は、担任の先生を代えてもらうことはできませんが、みんなの前で叱るなどの行為を控えてもらい、個別に叱ってもらうようにお願いすることはできます。
また、新学期でクラスメイトが変わり不安定になっている場合は、席替えで仲のいい子を隣にしてもらったり、窓際の目立たないところにしてもらったりします。
そうすることで環境の変化の戸惑いを最小限に留められるようにします。
そんなことをしたらモンスターペアレントにならないかと心配される方もいますが、元気に通っているのに仲のいい子を隣にしてくれというのはモンスターペアレントと言われても仕方ないですが、登校を渋っているのでそれは配慮の範疇と考えていいと思います。
不安であれば、保護者会などで担任の先生から保護者の方に「今は○○さんは、学校に来にくい状態なので、クラス替えなど少し優遇させていただくかもしれませんが、ご協力お願いします。」と言っていただければ保護者の方もわかってくれると思います。
このような環境の変化に対する配慮により何とか登校しながら環境に適応していけるよう努力します。しかし、状態が重い場合は、このような対策をしても不登校不安定期になってしまう場合もあります。
※この対応はあくまで対症療法であることを理解しておいてください。
性格傾向の改善に取り組む

環境の変化に対する配慮が対症療法と書きましたが、性格傾向の改善が原因療法となります。つまり登校を渋りやすい性格傾向の改善が「登校しぶり」の根本的な解決方法になります。
不登校もそうですが、「登校しぶり」も様々な原因が重なることで起こります。その要因のベースには、その子の性格的な要素が関わっていることが多いです。
親に頼らず自分で解決できる能力や、親に責任転嫁せず自己責任で解決する能力、ストレスに対しての強さやストレスを受け流す能力、そのようなソーシャルスキルを身に付けさせてあげることが長期的な登校の安定につながります。
できれば、「登校しぶり」が出る前に家庭教育に対して意識的に取り組み、ソーシャルスキルの底上げを家庭内で行ってもらいたいのですが、「登校しぶり」や不登校になって初めて家庭教育の大切さに気づくという方がほとんどなので、子どもが「登校しぶり」で出したSOSサインをしっかり受け止めて、何とか長期の不登校になる前に改善していきましょう。
環境への配慮もしたほうがいいということはわかりました。でもやはりベースは家庭教育なのですね。
「登校しぶり」の段階では、無理にでも登校を続けた方がいいのか休ませた方がいいのか悩んでいる方も多いと思います。インターネットでも休ませた方がいいという意見が多いと思いますし、親としてはその後ずっと行けなくなるのではとそちらの方が心配になりますから。行かせていいとわかっただけでも安心しました。
無理に行かせていい訳ではなく、安易に休ませるのが良くないのですね。わかりました!と言いたいですが、わかりにくいのですが・・・
なので、できれば私のような不登校専門のカウンセラーにアセスメントしてもらうことをおすすめします。無責任なことも言えませんので、blogでは安易に休ませるのはよくないということだけで勘弁して下さい(汗)
先生を困らせてしまいましたね。確かにそうですよね、ブログだけでは個々のケースまで対応はできませんよね。すいません。
個別の相談内容がどういったものかわかるのは嬉しいですね。では今回の内容もまとめますね。
「登校しぶりは休ませるべきか?今すぐ知っておきたい原因と対応を解説」まとめ

登校しぶりはなんとか登校できている状況のため、親御さんも「まだカウンセラーに相談するほどではない」と思われる方が多いです。しかし、登校をしぶっている時点でその子にとってはなにか大きな登校したくない理由があるのです。
その原因がわからないまま無理に登校させていては、いずれ限界が来ます。そのため、登校しぶりの原因をしっかり把握・アセスメント(分析)することが大事なのです。
登校しぶりの原因としては【環境の変化】【性格傾向】【イベントや授業】が考えられますが、休みグセがつく恐れがあるため安易に休ませることはおすすめできません。
一時的に学校に配慮をしてもらう対処法もありますが、あくまで大切なのは、対症療法ではなく根本原因にアプローチすることです。つまり、ソーシャルスキルを身につけるための家庭教育です。
性格や生まれながらの気質の認知変容は素人では難しいため、心理の専門家に相談するのが近道だと思います。エンカレッジでも、日々の家庭内対応を伺い、親の言動を変えることでお子さんの自立を促し自己効力感を高めるサポートをしています。
エンカレッジの支援にご興味ある方は、復学支援内容やクライアントアンケートもご覧いただき、無料オリエンテーションからご連絡ください。


 不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
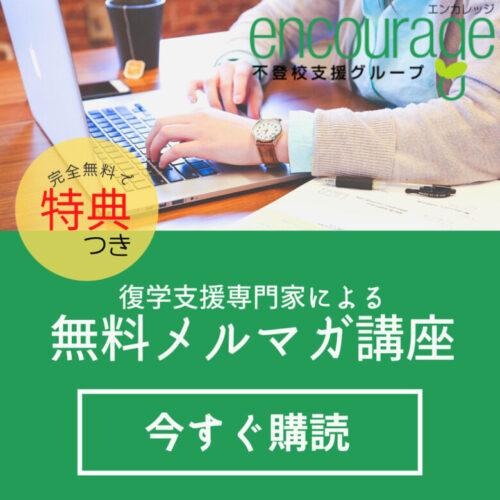 不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!
不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!