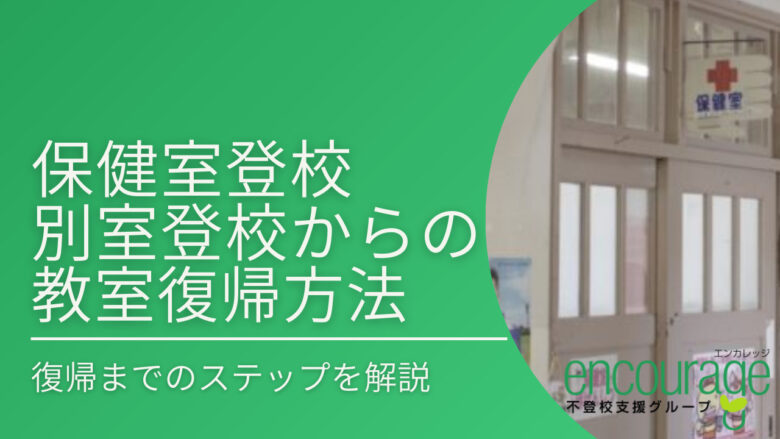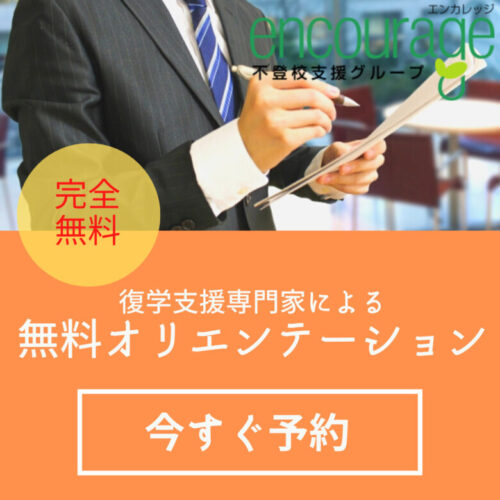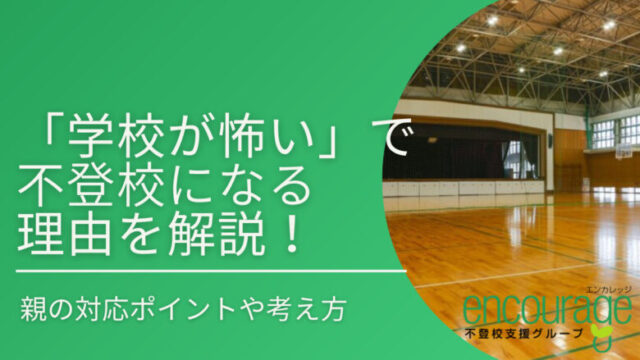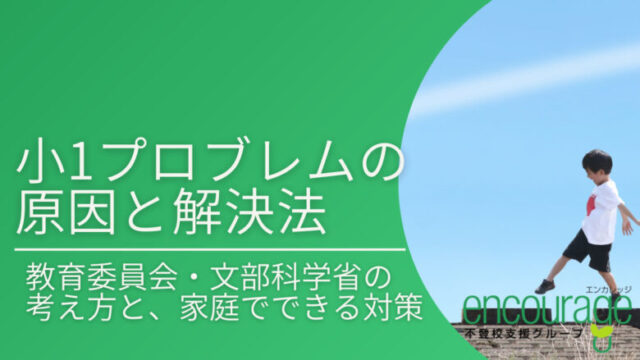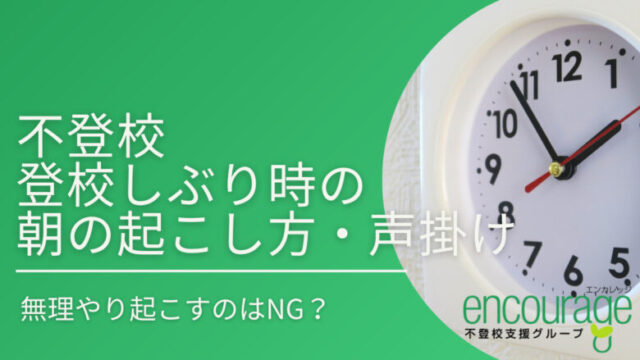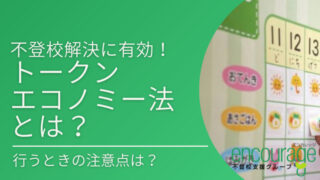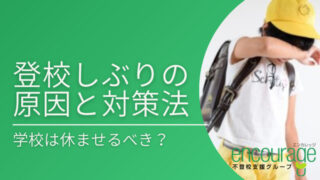最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)
- 兄弟全員が不登校のときは+αの対処法を!親のケアもポイント - 2025年7月3日
- 不登校の子どもに効く!自己肯定感を高める3つの方法 - 2025年6月15日
- 「うちの子が学校に行きたがらない…どうすれば?|不登校の初期対応と親の心構え」 - 2025年5月13日
何とか保健室登校(別室登校)までできるようになったとしても、そこからなかなか進めないというお悩みもよく聞きます。
確かに保健室登校は教室に入るよりハードルが低いので、保健室登校や別室登校をしている方は多いと思います。しかし最初のハードルが低い分、ステップごとに停滞してしまったり、教室復帰に時間がかかったりするというデメリットもあるのです。
今回は保健室登校のメリット・デメリット、教室復帰への具体的な対応を解説していきます。
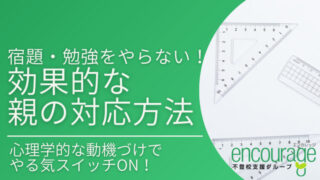
私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1000人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立17年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。
↓不登校の解決に必要な対応をまとめた記事はこちら↓
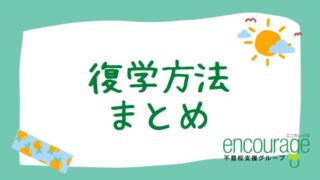
保健室登校(別室登校)のメリット

不登校から復学する場合に、教室復帰はハードルが高いときによく選ばれる保健室登校・別室登校。
復学支援専門家としては、後々のことを考えると一気に教室復帰をおすすめしたいところではありますが、保健室登校・別室登校もメリットがあります。
ここでは保健室登校・別室登校のメリットをまとめていきますね。
学校に登校しやすい

保健室登校・別室登校もメリットは、何といっても登校しやすさです。
同じクラスの子どもたちと合わなくて済むので、友達関係に不安を抱えていたり勉強に不安がある子でもその辺りを気にせずに登校することができます。
最近は「集団が苦手」という子も多いので、不安要素が少ない分、教室ではなく保健室なら登校できるという子は少なくありません。
好きな時間に登校しやすい

不登校や五月雨登校などで休みがちになってしまうと、朝に「やっぱり行きたくない」と登校を渋って朝から登校できないということはよくあります。
特に小学生は前日まで元気でも朝に急に泣きだしたり拗ねたり、やっぱり怖いと尻込みするケースはよくあります。
教室であれば途中からは周りの目も気になるのでその時点でお休みしないといけなくなる場合が多いですが、保健室登校であれば2時間目からとか3時間目からとか午後だけなど、ある程度自由に登校できるので朝渋ってもリカバリーできる場合があります。
罪悪感が少なくなる

不登校でずっと家にいる子は、学校に行っていないことへの罪悪感があります。
そこから精神的に追い込まれるケースもあります。中学生になるとそこから思春期鬱になったり、リストカットなどの自傷行為に発展する場合もあります。
小学生の場合は、「退屈だ」「暇だ」と荒れたり、親に甘えたりする子が多いです。保健室登校をすることで学校に行っているという意識になるので罪悪感は少なくなり、精神的に余裕が出てきます。
母子分離しやすい

不登校でずっと家にいると親に甘えたり、依存するので母子依存につながりやすいです。
母子依存になると自己解決能力も低下しますし、親と共依存になると学校に行ったときにお母さんがいないと過ごせなくなってしまいます。
保健室に行くだけでも親と2人きりで過ごす時間が減りますので家にいるよりも母子分離はしやすいです。


保健室登校(別室登校)のデメリット
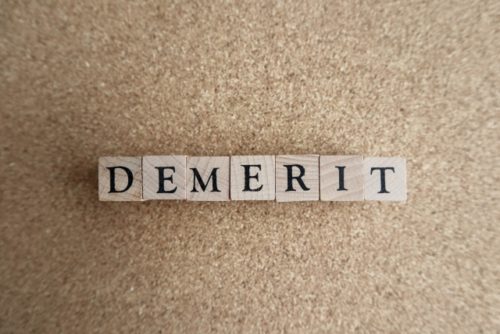
教室復帰よりもハードルが低く登校しやすい保健室登校・別室登校ですが、実はデメリットもあります。
ここからは、デメリットについてご説明していきますね。
教室復帰に時間がかかる
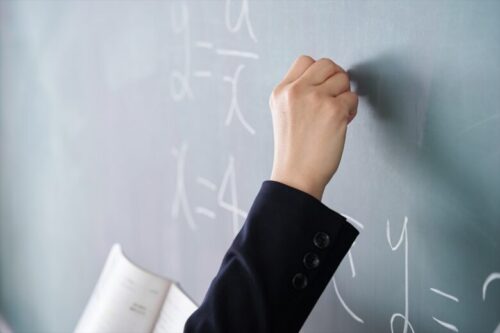
保健室登校の場合は、スモールステップという方法で学校復帰を目指します。スモールステップは、最初から高い目標を設定せず、小さな目標を1つずつ達成し成功体験を積み重ねることで最終目標に近づくやり方です。
少しずつステップを踏んでいくので子どもに負担が少ない反面、教室に戻れるようになるのに時間がかかる場合があります。
【学年】
4年生の女の子
【状況】
スモールステップで半年間かけてようやく毎日保健室に通えるようになったものの、「そこから教室に復帰するのにはどれくらいかかるのだろう」と親御さんが不安になり、エンカレッジの復学支援を開始
【結果】
2か月後には朝から教室に通えるようになった
上の事例でも、結局不登校開始から教室復帰まで8か月近くかかってしまいました。
二次障害(2次リスク)が発生しやすい

先ほど半年間で保健室登校ができるようになったケースをお伝えしましたが、保健室では勉強は基本的にしません。折り紙をしたり、保健室に来た子どものサポートをしたり、図書室の本を読んだりします。
勉強をする子もいますが、保健室の先生は養護教諭なので基本的に自分でドリルをするなどの自習になります。
小学生はそこまで勉強の遅れを気にする必要はないのですが、中学生は勉強の遅れは教室復帰の大きなリスクになります。
保健室登校の期間が長いほどそのリスクは大きくなるので、負担が少ないからと時間をかけすぎると2次リスクが膨らんでしまうことも理解しておきましょう。
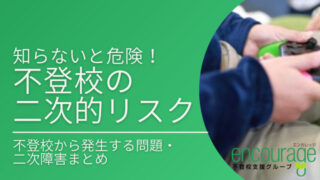
保健室登校で満足してしまう

「保健室登校で満足してしまう」というのは中学生にはあまりいないのですが、小学生には多いです。
「僕は学校に行っているから大丈夫」「私は不登校じゃないし」と保健室登校で学校に行っている気持ちになってそこで満足してしまうのです。
確かに学校には行っているが教室に入っているわけではないのでそこから教室復帰を目指したいところですが、本人が満足してしまうと次のステップになかなか進めないのです。
「僕は教室には行きにくいけど保健室には行っているからそれでいい」と言われてしまうと教室復帰を促しても自分で決めてしまっているのでうまく導けないのです。
特別扱いを許可していることへの弊害
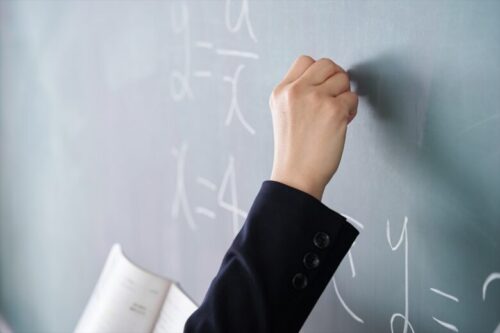
保健室は本来はケガをした子や体調不良の子が一時的にくるところです。それを特別に教室に入れないからと解放していることになるので、原理原則としてはよくはありません。
しかし、親は家にずっといるよりは少しでも学校に行ってほしい、学校も少しでも来てほしいと双方の思いが重なるので特別扱いでも許可した方がいいだろうとの考えになります。
それを子どもたちが勘違いしてしまう可能性があるのです。保健室登校で満足してしまった子は特に次のステップに進みにくくなります。
例え担任の先生が「本来は教室に行かないといけないんだよ」と伝えても「先生が保健室だけでもいいって言ったんじゃないか。嘘つき」と言われてしまうと何も言えなくなってしまいます。
スモールステップの教室復帰は特別扱いを許可することになるのでその弊害がでやすいことも理解しておきましょう。
友達にずるいと言われる

保健室登校(別室登校)だけではなく、母子登校や放課後登校や午後からの登校などもそうなのですが、スモールステップは特別扱いになるので友達から「ずるい」と言われることもあります。
「何であの子はいつも保健室にいるの?」
「何であの子はお母さんと一緒に授業を受けているの?」
「何であの子はほとんど保健室で1時間しか教室に来ないの?」
「いーなー」「ずるいよ」
小学生は、良くも悪くも素直です。特に低学年は悪気はなく単純に思ったことを言ってしまいます。
それが相手を傷つけるつもりはなくても結果として傷つけてしまうことはあります。言われた方は悪気はなかったとしてもやはり言われると辛いです。
しかも、保健室登校・別室登校している時は不安定で傷つきやすい状態なので、そのような言葉で後戻りしてしまうこともあるのです。
ただ、特別扱いであることは事実なのでその友達の発言は一概に否定できません。
スモールステップの教室復帰は、精神的な負担の少ない方法ではあるのですが、その分、他のリスクがたくさんあることも理解しておかなければいけません。
小学生で保健室登校や別室登校から教室復帰する方法
 ここまで読んでいただいた方は、保健室登校・別室登校にはメリットよりもデメリットの方が多いような気がすると思います。
ここまで読んでいただいた方は、保健室登校・別室登校にはメリットよりもデメリットの方が多いような気がすると思います。
保健室登校は教室復帰には良くないのか不安に感じるかと思いますが、保健室登校を使ったスモールステップのやり方の方が教室復帰しやすい子もおり、大切なのは「その子に保健室登校が合っているかどうか」です。
その子に保健室登校・別室登校があっているかどうかは、効果的な手順で進めてみて、それでも好転しない場合は「保健室登校・別室登校が合っていない」と判断したほうがいいでしょう。
その効果的な手順について、以下で解説しますね。
【STEP1】まずは毎日保健室に登校できるようにする

保健室登校はできても、行ったり行かなかったりの五月雨状態では、教室復帰のアプローチができません。まずは毎日保健室に登校できるように家庭内で話し合って進めていきましょう。
小学生低学年や女の子などはエンカレッジでもよく行うトークンエコノミー法などを使ってみるといいでしょう。
【STEP2】1日、保健室で過ごせるようにする

次に、保健室・別室で1日過ごせるようになりましょう。
朝から最後までいないといけない訳ではありませんが、2時間目~5時間目などある程度の時間を過ごせるようにするといいです。
朝から登校するのは他の友達の目線が気になるでしょうし、帰りも気になるでしょうからみんなの登下校の時間は避けてもらってかまいません。
こちらもカレンダーに行けた日は〇をつけるなど視覚的にも努力が結果として見える形をとってあげるとモチベーションがあがります。
時間を延ばすのが先か、日にちを増やすのが先かについては、日にちを伸ばす方を先にしてもらうのが基本ですが子どもによっては時間が先でも構いません。
その子の性格などを考慮して、負担の少ない方から進めていきましょう。
【STEP3】1週間~2週間単位で、成長を感じられるようにする

スモールステップのやり方が成功する場合は、成果が1週間単位、遅くても2週間単位で進んでいくことが大切です。保健室に週に2日行っている子は、次の週は1週間に3日行けるようにしようと目標設定をします。
設定するのは担任の先生がいいのか養護教諭がいいのか母親がいいのか、その子に効果が出やすい人がやります。
1度決めたら同じ人が進めてください。3日が行けたら次は4日と1週間単位で日数を増やしていきます。負担になっていそうなら今週はキープの週を作り、1週間はそのままにする週があってもかまいません。
もしかしたら後退する週があるかもしれませんが、トータルで右肩上がりに進んでいればOKです。
後退→キープ→後退となってしまった場合は、スモールステップのやり方の限界を判断しないといけません。
このやり方を半年から1年かけて少しずつ進めていく学校もありますが、1週間~2週間単位で進んでいない場合は、勉強の遅れや周りの目といった2次障害のリスクの方が大きくなっていきます。
またそこで満足してしまう場合もあります。「今週は3日も行ったんだから頑張ったでしょ。来週は2日でいんじゃない」などハードルを自ら下げたり、「今週は3日も行ったんだよ。凄いでしょ。もっと褒めてよ。遊戯王カード1パック買ってね」などこんなに頑張っているんだというのをアピールしてくるケースもあります。
これは、褒めすぎる場合に起こります。特に養護教諭は優しい方が多いので、「すごいじゃない。3日来れただけも凄いことだよ。お母さんも一杯褒めてあげてくださいね」などと言ってくれますが、そこで満足してしまうと次に進めなくなる可能性があるのです。
【STEP4】友だちに来てもらう

毎日、ある程度の時間保健室で過ごせるようになってきたら、担任の先生と相談して友達に来てもらいます。最初は仲のいい子に2時間目と3時間目の中休みに話に来てもらい、今度はいろいろな子に来てもらうようにします。
ある程度いろいろな子と話せるようになったら、今度は給食を一緒に食べてもらうなど関係を深めていきます。その辺りは学校によって保健室で給食は食べられないとか決まりがあるでしょうから、できる範囲で進めていきます。
友達には会えないとここで止まってしまう子もいます。
保健室登校からの教室復帰の場合は、少しずつハードルを乗り越えていくのですが、各ハードルがその子にとってとてもハードルが高い場合があります。
そこで止まってしまうと結果的にそれ以上は進めず、次のステップに進めなくなるかもしれません。
どこがハードルが高いのかはその子その子によって違うのですが、どこかで止まってしまうと次に進めないのがスモールステップのやり方のデメリットでもあります。
【STEP5】友だちに誘いに来てもらって好きな教科の授業を受ける
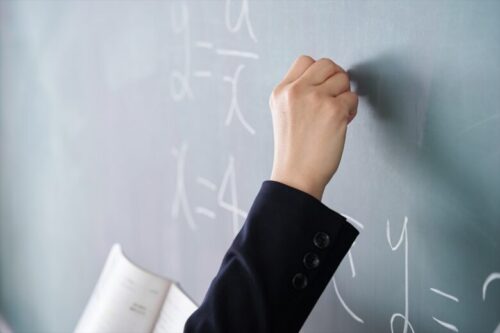
友達との関係が進んだら、仲のいい友達に誘いに来てもらって好きな教科に授業を受けられるようにします。友達に何度も保健室に来てもらったので、友達がいることの安心感で教室に入りやすくなります。
好きな授業からというのも安心できるでしょう。そうしながら、図工だけでれるようになる。算数だけ出られるようになる。と時間を増やしていきます。
ある程度授業に出られるようになってきたら友達に迎えに来てもらわなくても、自分でその時間になったら教室に入り、終わったら保健室に戻るということもできるようになります。
そして、今週は1日2時間出るなどの目標を設定して進めていってもいいです。目標の設定は、担任の先生、養護教諭、母親など設定をしている人が進めてください。
エンカレッジでスモールステップのやり方をする場合は、訪問カウンセラーが設定をして、今週の目標がどうだったのか、来週の目標はどうするのか子どもと一緒に決めていきます。
先生方は不登校の専門家ではないですし、母親が設定を行うと母子依存につながりやすいので、アウトリーチ型の訪問支援を受けている方などは、不登校専門のカウンセラーが進めるといいです。
このように進めていき、全ての授業が受けられるようになったら朝から教室に直接向かうようにして学校復帰できるようにします。
ただ、教室で好きな授業だけ受けるということは周りからずるいと思われる可能性があることも理解したうえで進めていかないといけません。
最近は優しい子が多く、心ない言葉をかけてくる子は少なくなりましたが、イレギュラーなことをしていることは事実なので、周りに感謝の気持ちを持って進めていくようにしましょう。
- 1日、保健室で過ごせるようにする
- 毎日保健室に登校できるようにする
- 1週間~2週間単位で、成長を感じられるようにする
- 友だちに来てもらう
- 友だちに誘いに来てもらって好きな教科の授業を受ける
- 全ての授業が受けられるようになったら朝から教室に直接向かうようにする
このように進めていくことができれば保健室から教室に復帰することはできます。大切なのは、右肩上がりで進んでいるかどうかとそれぞれのハードルで止まってしまわないかです。
保健室にはいけても教室にはどうしても入れないという子は実は多いのです。せっかく保健室に毎日通えてもそこで止まってしまっては結局そこから進まないのです。
そのような場合は、保健室には行けるからと保健室登校を繰り返すのではなく、スモールステップのやり方では限界があると判断して復学支援など別の方法を検討してください。うまく進んでいない方法に固執して時間が過ぎるのはもったいないですし、その子も親御さんも不安になって状況が悪化することがよくあるからです。
「保健室登校や別室登校から教室復帰する方法は?具体的な対応を解説!」まとめ

保健室登校・別室登校にはメリットがある一方、デメリットもあります。
不登校から保健室登校まで行けてもそこで停滞してしまうことがよくありますが、そのような場合は保健室登校からの学校復帰のやり方が合っていないことも視野に入れてください。
一時的な停滞はありますが、3ヵ月以上保健室登校が続いている場合は、別のやり方を検討したほうがいいかもしれません。
保健室登校をされている方は、今回の記事を参考に保健室登校から教室復帰を目指してください。また自分のお子さんが保健室登校からの教室復帰に合っているのかの判断材料としても参考にしていただければと思います。
 不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
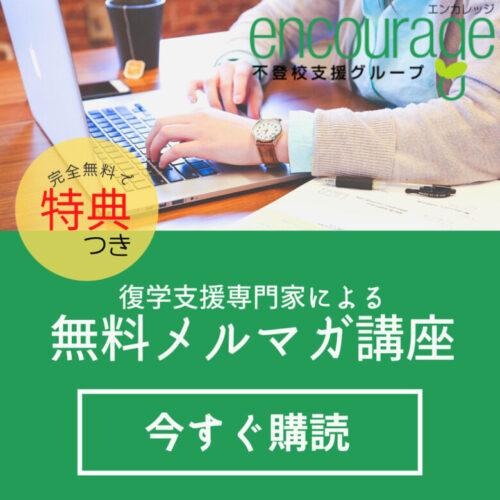 不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!
不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!