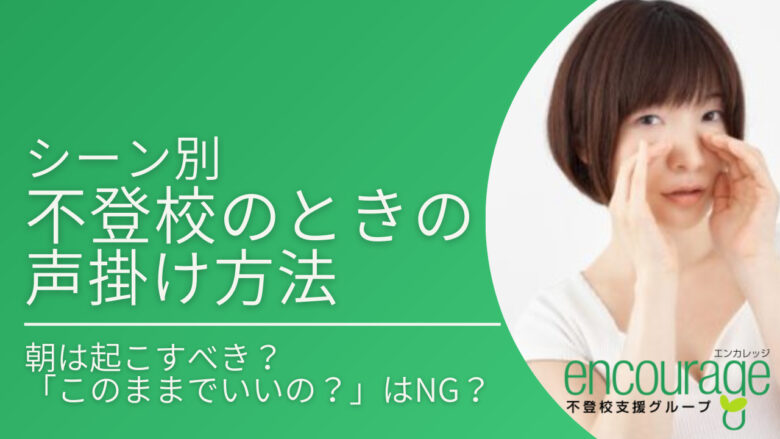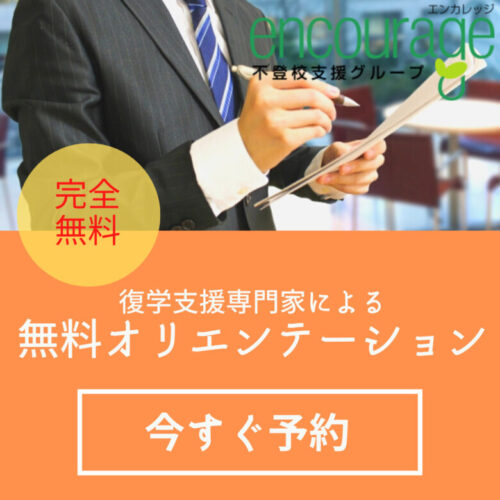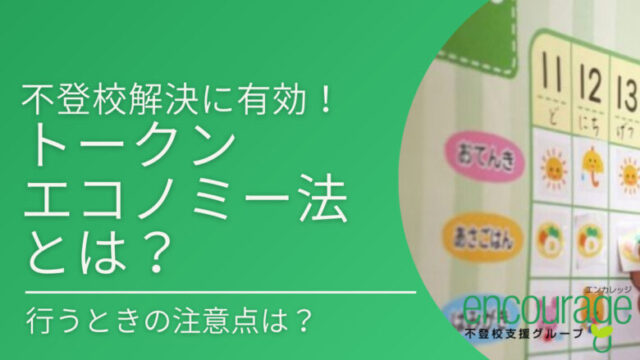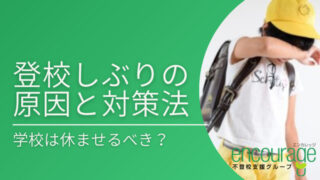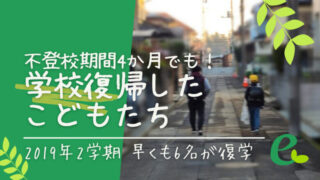最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)
- 兄弟全員が不登校のときは+αの対処法を!親のケアもポイント - 2025年7月3日
- 不登校の子どもに効く!自己肯定感を高める3つの方法 - 2025年6月15日
- 「うちの子が学校に行きたがらない…どうすれば?|不登校の初期対応と親の心構え」 - 2025年5月13日
不登校になると、毎日子どもにどのように声をかけたらいいのかと迷いますよね。
「朝は起こしたらいいのか?」「毎日学校に行くかは聞いていいのか?」「先生からの電話は毎回出るか確認した方がいいのか?」…考え出したら枚挙にいとまがありません。
親にとっても不登校ははじめての経験でわからないことばかりだったり、自分の声かけがいいのかどうかもわからなくなりますね。
しかし子どもへの声かけはポイントがあります。そのポイントをおさえることで、親子関係が改善したり、再び学校や勉強に興味を持ってくれたりします。
そこで今回は自宅での声かけについて解説していきますね。
私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1000人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立17年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。
↓不登校の解決に必要な対応をまとめた記事はこちら↓
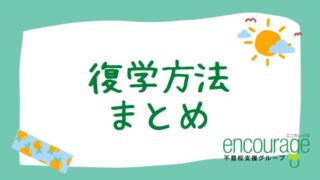
不登校の子への声かけで大切な考え方

毎日の生活の中で、不登校の子にどう声かけすべきか、どう対応すべきかは親御さんがとても悩むところです。
まずは、声かけするときの基本的な考え方についてまとめていきますね。
その子の状況に応じて親が対応を変える
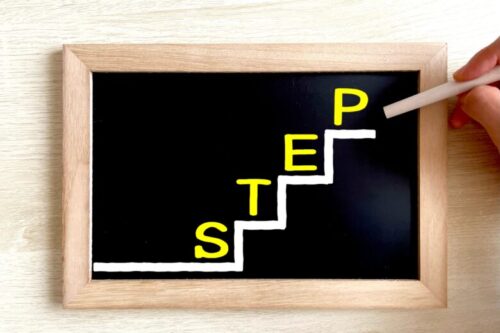
自宅での声かけをする際に大事なのは、その子の状況に応じて声かけ内容を変えるということです。
五月雨登校や別室登校のように、少しでも登校できている子と、全く登校できていない完全不登校や長期不登校の子では当然対応が異なってきます。
さらには、不登校になった原因によっても対応が異なりますし、その子の性格や気質によっても変わるでしょう。
そのため、まず大事なのはお子さんをしっかり観察することです。
声かけしたときの表情、反応、目つきなどを見て、その対応を続けるべきなのか変えるべきなのか、その都度親が考えていく必要があります。
登校刺激はここぞという時に取っておく

子どもが不登校のときは親はついつい心配になって「学校に行かなくていいの?」「明日の理科の実験が楽しそうだよ」と登校を促す登校刺激の言葉を言ってしまいがちです。
しかし、不登校の原因が未解決orわからない場合は「解決してないのに登校しろなんてムリ」と親への信頼が揺らぎますし、何度も登校するよう言われると学校自体に拒否反応を現すようになったり、「登校すらできない自分なんて…」と思考が負のスパイラルにはまってしまったりします。
お子さんだってきっと本心では登校したいのです。でもなんらかの理由があるから行けなくて困っているんです。そんな状況で何度も何度も登校を促されると気持ちが爆発してしまいます。
そのため、登校刺激はここぞというときに取っておき、タイミングを見計らいましょう。
登校刺激のタイミングについては、以下の記事も参考にしてください。
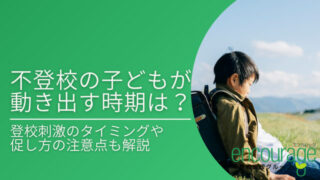
五月雨登校や別室登校の場合の親の声かけ

お子さんの状況に応じて声掛けすべきとお伝えしましたが、では具体的にどのように声かけしていけば良いのか悩みますよね。
ここからは、五月雨登校や保健室登校など、完全不登校ではないけれど登校しぶりなどがあるケースでお伝えしていきますね。
朝に起こすときの声かけ

朝に親が起こすかどうかは、子どもの状況によって変えていきます。
もし五月雨登校や別室登校をしている場合で、まだ昼夜逆転が起こっていない場合は、生活リズムの安定のために起こしてあげましょう。
本来であれば、朝起きることも自分のことなので自分でするべきです。しかし、五月雨登校や別室登校、保健室登校などは今後完全不登校に発展する恐れがあり、そのリスクを減らすために親が朝に起こすことをおすすめします。
朝に起こすときの声かけの仕方ですが、感情を入れずに時間で伝えると効果的です。
- 「早くしなさい」などは言わず、時間だけを伝える。
- 「7時だよ。」「7時10分だよ。」「7時20分だよ。」など。
単純と思うかもしれませんが、この声かけが反発が少なくておすすめです。時間を告知して、その時間だから何をすべきかは子ども自身に考えさせるので自立も促せます。エンカレッジのクライエントさんにも皆さんにお勧めして、効果を実感してもらっています。
ただし、わざと目を開けないなど意図的な場合は無理に起こすのは止めましょう。
登校の確認をする声かけ

五月雨登校や別室登校をしている場合は、登校の確認をしてもかまいません。
- 最初は「今日はどうするの?」などの声かけはせず、行く前提で明るく世間話をしながら進める。
- 動きが重そうなら「今日はどうするの?」と確認する。
- 母子登校などをしている場合は、「玄関で待ってるからね」と一緒にいないことも効果的。
しかし大事なのは、その日その日の確認ではなく計画的にプランニングを立てておくことです。
トークンエコノミー法で登校へのモチベーションを上げておいたり、スモールステップの計画を立てて進めていくのが効果的です。
五月雨登校や別室登校の改善方法については、以下の記事も参考にしてみてくださいね。
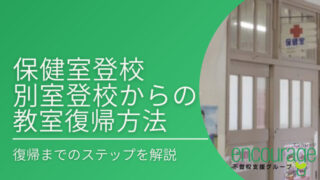
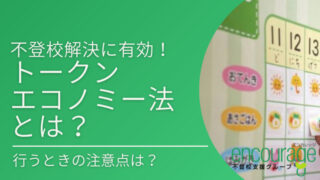
明日の「学校どうするの?」の声かけ

「明日は学校どうするの?明日の給食は大好きな焼きそばだよ」
つい子どもに言ってしまいたくなるセリフですよね。エンカレッジの支援で行っている観察法の1つ「会話ノート添削」でもクライエントさんが子どもに聞いている言葉です。「え?何かまずいの?」と思われた方もいるかもしれません。
しかしこの確認は多くの場合、親が「行くと言ってほしい」「行かせたい」という意図が強く出てしまいます。
親の行かせたいとの思いが強すぎると子どもは行かされると思い心理的リアクタンス(心理的抵抗)が生まれます。
行くか行かないかは翌日になればわかることなので「親が知りたい」「行くと言ってもらって安心したい」という確認であればやめましょう。
お弁当が必要なので「確認しないと困るのです」と言われる方もいますが、「お弁当という理由があるから聞いてもいいはず」という意図的なものがあると子どもにもわかってしまいます。
子どもは敏感なので本当に自分のために聞いてくれているのかどうかはすぐにわかります。
大変ですが、お弁当は確認するのではなく学校に行く前提で作っておきましょう。
完全不登校の場合の親の声かけ

五月雨登校の場合の声かけ方法を見てきましたが、それでは完全不登校や長期不登校の場合はどのように声かけするべきなのでしょうか。
ここからは、完全不登校や長期不登校の場合の声かけ方法についてまとめていきます。
無理して朝に起こす声かけはしない

不登校になると昼夜逆転する子も出てきます。
そうなると親としては「朝はなんとしても起こして昼夜逆転を改善しなければ」と思うことでしょう。
とはいえ、朝に起こすととても不機嫌になってしまったり、イライラしてモノにあたったりされては起こすのも躊躇ってしまいますよね。
生活リズムを安定させることは大切ですが、「朝起きると学校に行きなさいと言われるから嫌」という子もいますし、朝に同級生の声が外から聞こえたりすると辛くなる子もいます。
ただ、生活が乱れているなら起こしても構いませんが、「同級生の声を聞きたくない」といった辛さを抱えている場合は起こさない方がいいです。
起きない理由がある場合は、無理に起こすと親は理解してくれていないと感じますし、関係も悪化するので、無理に起こさないほうが良いです。
登校の確認をする声かけ

完全不登校の場合、登校の声かけはプレッシャーにしかならないのでやめましょう。行く意思がない場合や、行こうと思っても行けない状態になっている場合は声かけはしない方がいいです。
ほぼ行けないと思っていても毎日「今日はどうするの?」と確認される方もいますが、子どもにはかなりの負担になります。
親目線では「行こうと思えば行けるはず」「甘えているだけでは?」と感じるかもしれませんが、子どもからしたら勉強せずに100点を取れと言っているような感覚です。
できないことを毎日やれと言われていることになるので、こちらも「お母さん、お父さんはわかってくれない」と関係も悪化してしまいます。
「それならどうしたらいいの?」と思われた方は、なぜそのような状況になっているのかという理由の方から以下の記事で理解していきましょう。
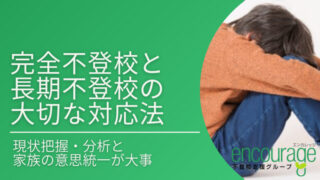
子どもが「甘えているのでは?」と感じる方は、以下の記事も参考にしてみてくださいね。

「このままどうするの?」という確認の声かけ

不登校が長期化すると、「いつ学校に行くの?」「このままでいいの?」「どうするつもり?」と聞きたくなります。そうなるとだんだん説教のようになっていきます。
子どももわかっていてもどうすることもできない状況なので、わからないことを言われても感情だけが爆発してしまいます。お互いの関係性を悪化させるだけなのでやめましょう。
ではどうしたらいいのかと不安になりますが、冷静に今の状況を分析して適切な時期に、適切な関係性の上で、適切な声かけが必要になります。
目の前の不安に対して自分の感情で声かけしてしまうといい方向にはいきません。1人で抱えてしまうとどうしても目の前の事しか見えなくなってしまいます。
その場合は、専門家に相談して冷静に分析してもらうのも1つです。
エンカレッジでは無料オリエンテーションを採用しています。無料オリエンテーションは民間の心理師のアセスメント(分析)を無料で体験いただけるものです。一度受けてみたいと思われる方はこちらをクリックしてください。
学校や友だちとの連絡に関する声かけ
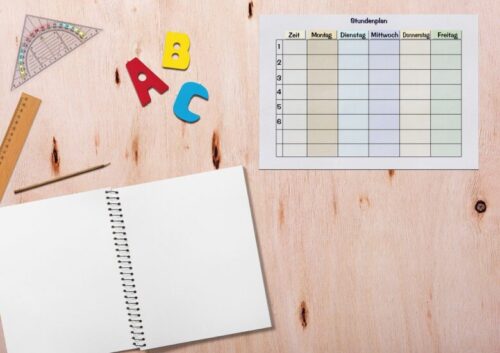
不登校になると、学校や友だちとの連絡でも悩まれる方が多くいます。
本来であれば連絡をもらえるのがありがたいはずなのに、毎日「今日も休みます」と言い続ける親の精神的負担も大きいです。
ここからは学校や先生、お友だちとの連絡のしかたや、ストレスを溜めないための連絡方法などをまとめていきますね。
学校・先生との連絡

担任からの毎日の電話がある場合、子どもが代わる場合は問題ありませんので「先生から電話だよ」と言って代わってください。
しかし、子どもが代わらない場合は担任の先生と親がコソコソ話すことが多くなりがちなのでおすすめしません。子どもも何を言われているのかを聞き耳を立てたり、疑心暗鬼になったりして、先生と親の電話を快く思わない場合があります。
毎日の連絡は子どもにとってもプレッシャーになりますし、先生の負担も増えます。親も辛くなる場合もあるので、先生からの電話は子どもが喜んでいる場合以外は控えてもらいましょう。
学校への連絡は不登校の子の親御さん皆さんが、かなり精神的に辛い思いをされます。学校側から「安否の確認のために毎日連絡してください」と言われる場合もありますが、行かないのがわかっているのに毎日学校に「今日は欠席します」と連絡するのは本当に辛いです。
私が代表を務めるエンカレッジでは、学校と連絡を取るのは毎日ではないようにしてもらっています。その方が親がまだ元気な状態でいられるのでその方がよほど大切です。
兄弟にプリントを頼む先生や、連絡帳を兄弟に頼む親御さんもいらっしゃいますが兄弟も思っている以上に負担がかかります。先生には親が取りに行くと伝えましょう。お子さんに連絡帳を持たせるのもやめましょう。
詳しくは別の記事で書いていますのでそちらも参考にしてください。
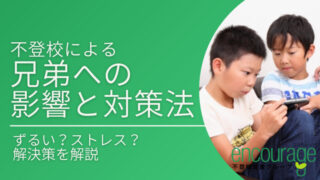
友達からの欠席の手紙

不登校になると、小学生はお友だちが欠席の手紙を毎日持ってきてくれます。
しかし、不登校が長期化している場合、その手紙に書かれている「毎日待っているよ」「早く良くなってね」という言葉がプレッシャーになる場合があります。欠席の手紙を持ってくる子も毎日だと大変になります。
また手紙を書く方も、毎日同じ内容になるので書くことがなくなり「昨日と同じ以上」「書くことがないので早く来てね」など心ない手紙も出てきてしまいます。
なので、喜んで見ている子以外はこの手紙も控えてもらうようにしましょう。1週間に一度プリントを取りに行くときに学習内容などは先生に確認していきましょう。
「不登校解決のために親がすべき声かけとは?専門家が状況ごとに解説」まとめ

毎日のことだからこそ「こんなふうに言っていいのかな?」と声かけ方法が気になるかと思いますが、「明日こそ学校に行かせなきゃ」という親の焦りや誘導尋問などは逆効果になることも多いです。
特に夜寝る前の「明日こそ学校に行くよね?」といった《自分が安心したいための声かけ》になっていないか注意してください。
大事なのは、親子間で信頼関係が築けていること、お子さんが不登校になった原因に対してアプローチ方法を考えているかどうかです。ただただ「学校に行かなくていいの?」と声をかけることは、「不登校の原因が解決していないのに登校しろって言われてつらい」「親は僕(私)の気持ちをわかってくれない」といった親への反発や諦めに繋がってしまう恐れがあります。
エンカレッジのクライアントもそうですが、やはり不登校になると1つ1つの声かけが全て不安になります。「仕事に行くときに行ってきますと言うべきなのか?」「ご飯はどうする?」と聞いてもいいのか「学校の話題は出していいのか?」と不安がどんどん膨らんで親御さん自身が参ってしまいます。
そういった不安が解消できるようにするためにも、親御さんは1人で悩まずに、メンターとして親御さん自身を支えられる存在を見つけることも大事です。
 不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
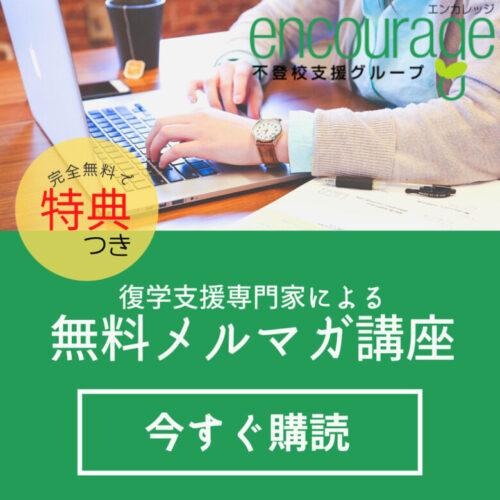 不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!
不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!