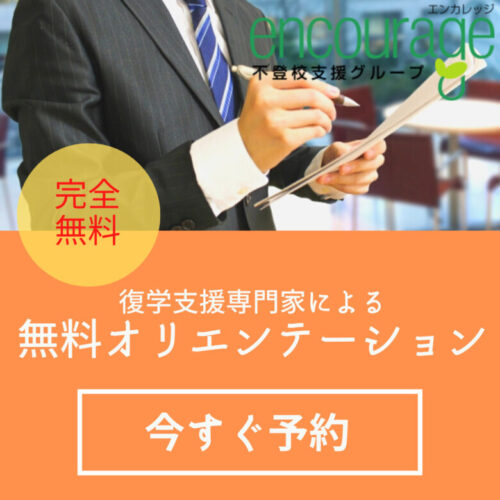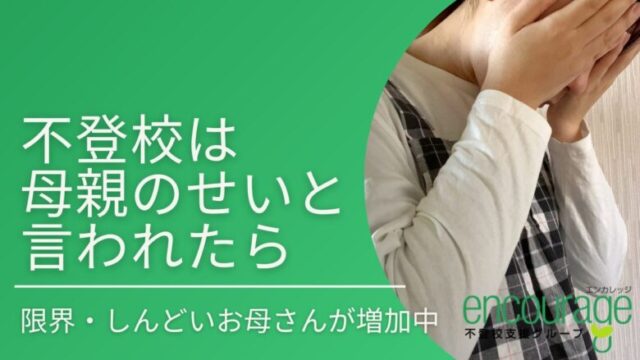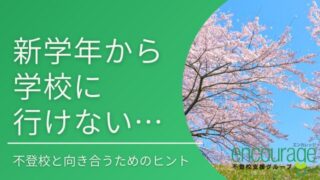最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)
- 不登校の子どもに効く!自己肯定感を高める3つの方法 - 2025年6月15日
- 「うちの子が学校に行きたがらない…どうすれば?|不登校の初期対応と親の心構え」 - 2025年5月13日
- GW明けに「学校行きたくない」子どもが急増?不登校のサインと親の対応法 - 2025年5月7日
夏休み・冬休みなどの長期休暇中は、お子さんが勉強や宿題をやらないと悩む親御さんも多いですよね。
しかし実は、義務である「宿題」と義務ではない「勉強」のやり方には、それぞれ促すのに効果的な方法に違いがあります。
心理学的な理論に基づいた方法なのですが、今回はその考え方についてご紹介していきます。
私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1000人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立17年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。
↓不登校の解決に必要な対応をまとめた記事はこちら↓
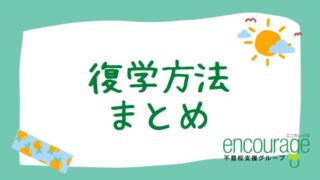
不登校の夏休み中に子どもが勉強・宿題をやらない理由

毎年8月になると、エンカレッジでも宿題が多くて嘆いている子、宿題が少なくて終わったらまったく他の勉強をしない子、まったく勉強しないでゲームばかりしている子…と様々です。
親御さんからも「どうやったら勉強しますか?」「この時期に遅れている勉強を取り戻させたいのですが」「まったくやりません」といった相談を多く頂きます。
ここでは、子どもが宿題や勉強をしない理由をまとめていきますね。
【勉強をしない理由①】何をすべきかわからないから

宿題や勉強をしようとする際、「何をしていいかわからない」という理由で動き出せない子も多いです。
例えば以下のような場合は、何をしていいかわからなくなりやすいです。
- 「復習しておくように」など、宿題の内容・範囲が曖昧
- 自由研究など、自分でテーマを見つけられない など
こういった場合は、何をどうすべきか、どういう順序でいつまでにやるのかなど、以下のような言葉で親が導いてあげられるとよいですね。
- 「1学期でよくわからなかったところはあった?」
- 「分数って難しいよね。足し算・引き算・掛け算・割り算があるけど、夏休み中はどこまで出来るようになれたらいいな~とかある?」
- 「(息子くん)はスイカがすごく好きだよね!スイカの種が簡単にまとめて取れる方法があったらいいのにね~自由研究でスイカを調べてみるのはどう?」
【勉強をしない理由②】諦めているから

「宿題の量が多すぎる」「難しすぎて出来る気がしない」と感じている場合、子どもは宿題をするのを諦めてしまいます。戦意喪失状態とも言えますね。
諦める心理には「《頑張ったのにできなかった》経験をしたくない」というプライドを傷つけられたくない気持ちや、「自分はできないのではなく、やっていないだけ(本気出せば出来る、自分は出来ないわけじゃない)」と言い訳したい気持ちが隠れています。
要するに、宿題や勉強に対して臆病になっているのですね。
このような場合には、今現時点で問題が解けないことは恥ずかしいことではまったくないこと、むしろ「挑戦することが大事であること」を丁寧に伝えてあげましょう。
また、宿題の量や難易度で心が折れてしまう子も多いと思います。「どうせやったって終わらない」「難しいから全然進まないし、やる気がしない」と手を付けなくなってしまいます。これが長期休みの後半になればなるほど残りの日にちが減る分、1日に対してやらなければならない量が増えるわけですから余計に諦めたくなります。
後述の勉強をしない理由⑥でも詳しく書いていますが、まずは何が残っているかをしっかり紙に書いて全体量を把握して、1日の「これだけやる」という目標を紙に書いて終わったら塗りつぶすなど成果を感じやすいようにしていきましょう。
まずは親が手本を見せてこのようにしていくといいと手伝ってあげてもいいでしょう。効果的なやり方が学習できれば色々な学習に応用できますので。
【勉強をしない理由③】必要性を感じていないから

子どもが宿題・勉強をしない1番の理由は、必要性を感じていないからです。
例えば不登校の子は、夏休み明けも不登校でいることを想定していれば、宿題をやる必要性を感じないので宿題をやらないでしょう。
勉強ができないから不登校になるのではなく、不登校だから勉強の必要性を感じられずに勉強できなくなるのです。
このあたりについては、以下の記事でも詳しく説明しているためご覧ください。
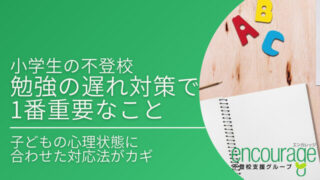
【勉強をしない理由④】勉強の習慣化が出来ていないから

そもそも勉強の習慣が出来ていなければ、勉強するのは難しいです。
心理学の言葉でホメオスタシス(恒常性)がありますが、人間は習慣を変えることがとても難しいのです。毎朝コーヒーを飲む習慣がある人が朝にコーヒーを飲まないと1日の調子が狂うように、人間は脳の性質で、習慣や環境を変えないように無意識で行動していることが多いです。
既に「勉強をしない」という習慣が出来てしまっているなら、勉強したくないのは仕方ありません。無意識に脳が勉強しないようにするのを覆すのですから、工夫や苦労が必要という覚悟をすることも大事です。
習慣化が出来るようにトークンエコノミー法をしてみたり、アラームで毎日同じ時間に取り組むように意識づけしたり、お子さんに合った方法を試行錯誤しましょう。
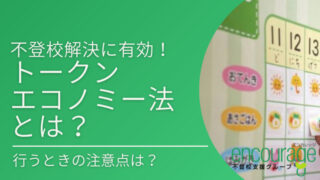
以前、習慣化をテーマに家庭教育推進協会でセミナーが開催されました。セミナー内容にご興味ある方はこちら↓をご覧ください。
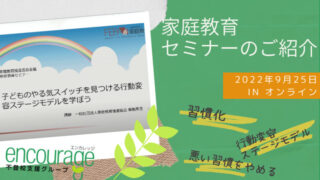
【勉強をしない理由⑤】家はリラックスする場所と思っているから

子どもにとって、家庭で勉強するというのは負荷がかかることです。
不登校の子もそうでない子も「勉強といえば学校でするもの」という感覚があり、家は休んだり遊んだりリラックスする場所という感覚がどうしても出てしまいます。
親も同じで、家で長時間子どもに勉強をさせるのは難しいですよね。机に向かってもらうことも大変ですし、丸付けをしたり、子どもが躓いた箇所をわかるまで説明するのも難しいものです。自宅で勉強するというのは、親にとってもかなりの負荷になります。
元々学校でやっていた勉強を家庭に持ち込むこと自体が、とても難しいことなのです。そのような子には勉強をする環境を別に用意できるといいです。図書館を使う、塾の学習室を使う、マクドナルドやスタバなどのカフェを利用するなどです。中高生は実際にやっている子も多いのではないでしょうか。小学生はさすがにスタバで勉強というのは目立ちますし、難しいかもしれませんが(笑)
【勉強をしない理由⑥】宿題の全体量がわかっていないから

こちらは宿題に関してなのですが、「宿題をしないとゲーム禁止」のように罰でやらせようとしても「提出日までにやるからいいでしょ!」とか「わかっているからうるさい!」などと反抗して、小学生高学年や中学生、ましてや高校生にもなると親の意見を受け入れないことも多くなります。
宿題と違って勉強は親に言われてやるものではないですし、言われてやるより自分で自発的にやる方が効果的なのですが、それを黙って見ていられないのが親というものですよね(笑)
つい「本当に終わるのかな?」「終わらなかったらまた学校に行かなくなるのでは?」と心配になります。
その場合は、全体量を把握させます。これは一時期流行ったレコーディングダイエットをイメージしてもらうとわかりやすいかと思いますが、把握するだけで提出期限とやらなければいけない量が明確化され焦りスイッチが入るというものです。
子どもたちは「わかっている!」と豪語しつつもいざギリギリとなると見積もりの甘さが出て「思ったより量があった。間に合わない。どうしよう?」とパニックになったりしますので、今のうちから全体量は把握させるようにしましょう。
小学生は一緒に全体量を確認してあげるといいですね。そうすることで「このままではまずいぞ」と危機感によるやる気スイッチが入る場合があります。
勉強をすることには抵抗がありますが、宿題や課題の確認であればそれほど抵抗はないので、宿題をほとんどやっていない子に関しては全体像を把握するだけでも今後の動きが変わってくると思います。
宿題を効果的にさせる方法

まず大前提として、宿題と勉強は似て非なるものです。
宿題…やらなければいけないもの。することが義務付けられているもの。
勉強…やることが好ましいが、義務ではないもの。
この「義務」の有無によって、子どもへの対応を変えることが効果的です。
以下ではまず宿題についてまとめていきますね。
そもそも「宿題」とは

そもそも宿題とは、義務的に課せられる勉強のタスクです。
「できたらやる」「好きな人がやる」などではなく、提出という義務がある以上、絶対にしなければいけないことと言えます。
「やったら褒められる」のではなく、「やるのが当たり前」という姿勢が重要です。
「負の強化」の考え方を応用

「やることが当たり前」の宿題には、応用行動分析のオペラント条件付けという考え方が有効です。
オペラント条件付けというのは、簡単に説明すると行動を報酬やペナルティによって変化させるというもので、端的に言うと行動の変化には強化と弱化(罰)があり、正の強化、負の強化、正の弱化(罰)、負の弱化(罰)と分けられます。
正の強化…「勉強することで褒められた」→「褒められたくてまた勉強をする」
負の強化…「勉強をしないことでゲームを制限された」→「ゲームを制限されないように勉強する」
このなかで、宿題に向いているのは「負の強化」です。
宿題はやらなければならない義務なので、やったからと言って報酬を与えることは望ましくありません。報酬とは、以下のようなものです。
- 物理的報酬…ゲームやお菓子などのご褒美
- 心理的報酬…褒めたりする精神的なご褒美
物理的にしろ心理的にしろ報酬が望ましくないのは、「報酬がないと義務をやらない」というのでは困るからです。
「宿題をしたらゲーム(ご褒美)を買ってあげる」ということはつまり「宿題が終わったらそれ以上の勉強はしない」「ゲームを買ってくれなきゃ、今後宿題はしない」ということになりかねません。
そのため、宿題を報酬で釣るのは良くないのです。
具体的な行動目標とペナルティを設定してやる気アップ

では宿題をしてもらうにはどうしたらいいのかというと、負の強化の考え方を使います。
例えば「宿題ができていなかったらゲームはできない」といった罰やペナルティを設定するということですね。やらなければいけないものができていなればペナルティがあるという方が子どもも納得しやすいです。
ただ、提出期限が休み明けとなると「そこまでにやればいい」ということになりかねないので、「毎日1ページずつ。出来なければその日はゲーム禁止」「図工の宿題は〇日までに終わらせる。できなければプールに行かない」といった先行条件を決めます。
ここでのポイントは、子どもも含めて話し合うことです。
親に強制されるとやる気が出なかったり納得感がなくなってやらなくなるので、あくまで「自分で決めたことだから」と子ども自身が感じられることが宿題実行の可能性を高めます。
勉強を効果的にさせる方法
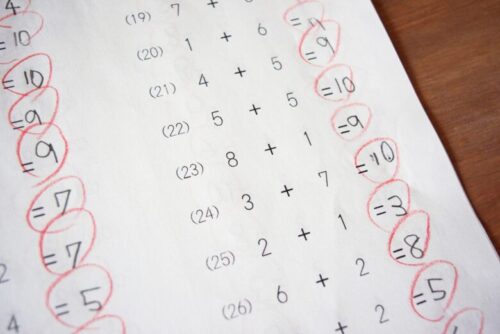
宿題とは異なり、勉強は義務ではないとお伝えしてきました。
しかし勉強は義務でないとはいえ、やった方が良いため、どうすれば勉強してくれるか悩む親御さんも多いです。
ここからは、勉強についてまとめていきますね。
そもそも「勉強」とは

そもそも勉強とは、強制されるものではなく、努力目標です。
宿題はやることが義務でありノルマのようなものですが、勉強は将来のためにやることが好ましいものの義務ではないので、子どもからすると「やらなくてもいいもの」であり、「あとでやればいっか」と思われがちです。
繰り返しになりますが、やる義務があるかどうかが宿題と勉強の違いと言えますね。
「正の強化」の考え方を応用

学校から宿題が出ればしっかり宿題をやる子でも、なかなか勉強までしてくれないことも多いですよね。
子どもが勉強しない理由はズバリ、そもそも勉強は義務ではなく努力目標なので言ってしまえば「やらなくていい」と思ってしまうからです。子ども本人がやる必要がないと思っていることをやらせるのは難しいですよね。
ではそのような場合にはどうするかというと正の強化を使います。
具体的に1日や1週間の目標を決めて、それが達成したらご褒美(物理的報酬)をあげるなどして頑張りやすい環境を作ってあげたり、褒めるなどの心理的報酬も効果的です。
報酬による強化に関してはトークンエコノミー法という視覚にアプローチするやり方も有効なので、以下の記事もご覧ください。
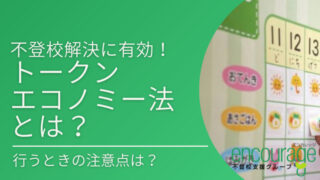
報酬の種類で使い分けてやる気アップ

心理学の言葉で、物理的報酬は外発的動機づけと言われ、心理的報酬は内発的動機づけと言われます。
外発的動機づけはすぐに効果が出やすい一方で継続しにくく、内発的動機づけはすぐに効果は出にくいものの継続しやすいと言われています。
物理的報酬…外発的動機づけ…すぐに効果が出やすいが継続しにくい
心理的報酬…内発的動機づけ…すぐに効果は出にくいが継続しやすい
そのため、最初は外発的動機づけから入って、徐々に内発的動機づけにシフトしていけるとより効果的と言えるかもしません。
- 「20分も集中して取り組めたね」
- 「字がきれいになったね」
- 「苦手な分数にもちゃんと取り組んでいて、お母さんうれしい!」など
内発的動機づけにシフトする場合は、褒められたこと(外発的動機づけ)によって「勉強をすると認めてもらえるし楽しい」と自分で思うようになること(内発的動機づけ)が大切です。
ただただ親が「すごいね」「えらいね」と言っているだけでは、何がどのように良かったのか子どもに伝わらず、内発的動機づけに繋がりにくくなるかもしれません。
「夏休み中に宿題・勉強をやらないと悩む親続出!やる気を高める方法」まとめ
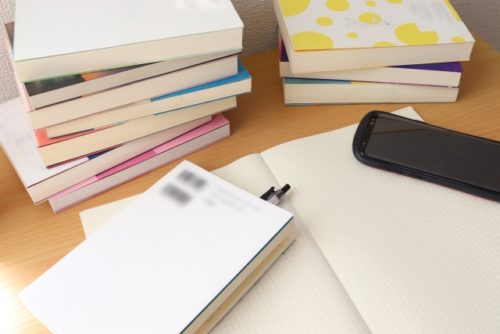
宿題などのやらなければいけないものには「負の強化」の考え方を用いて、やらなかったときにペナルティを設定するのが効果的です。
一方、努力目標である勉強に関しては「正の強化」の考え方を用いて、やったときに物理的報酬(ご褒美)・心理的報酬(褒める)を与えるのが効果的です。
報酬を与える際は、心理的報酬の方が継続的な効果が見込めるのでうまく活用して行きましょう。
 不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
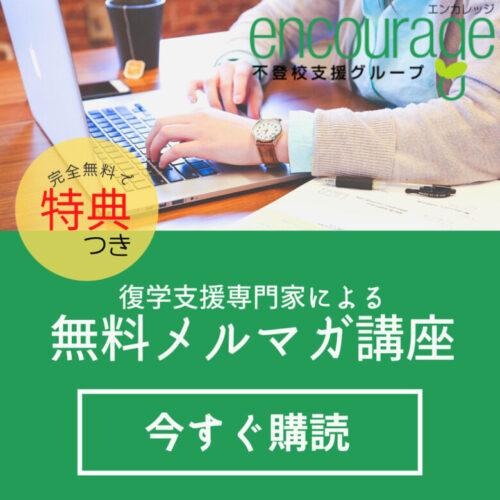 不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!
不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!