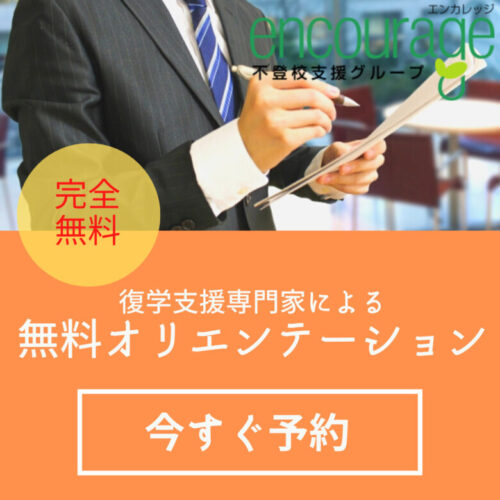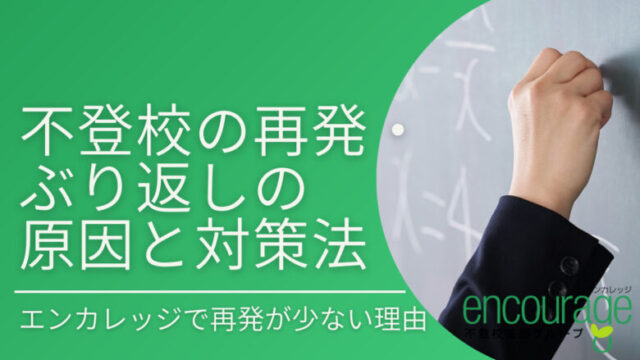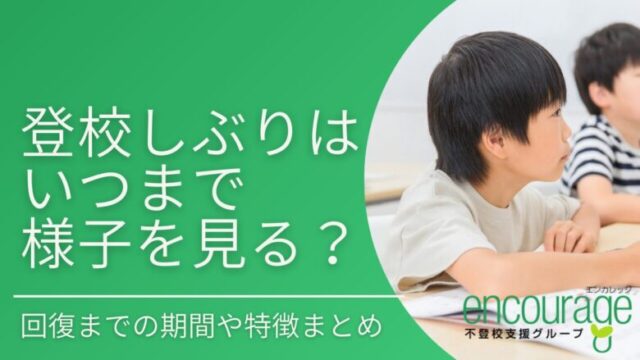最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)
- 兄弟全員が不登校のときは+αの対処法を!親のケアもポイント - 2025年7月3日
- 不登校の子どもに効く!自己肯定感を高める3つの方法 - 2025年6月15日
- 「うちの子が学校に行きたがらない…どうすれば?|不登校の初期対応と親の心構え」 - 2025年5月13日
近年、母子分離不安による不登校が多くなってきています。
ひと時代前は「不登校」と言えば素行不良型で、学校の裏でたばこを吸ったり夜の繁華街に出かけたりといったタイプが多かったのですが、平成・令和になるにつれて母子分離不安による不登校が多くなりました。
この母子分離不安・母子依存による不登校は、子どもの生まれながらの性格だけでなく、環境や親の対応の仕方が原因となっていることも多いのです。
今回は、母子分離不安・母子依存による不登校の原因や解決方法についてまとめていきます。
私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1000人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立17年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。
母子分離不安・母子依存とは

母子分離不安とは、母と子が離れることで精神的に不安定な状態になることを言います。
赤ちゃんは近くに母親がいないと不安になり泣いたり後追いしたりしますが、これは人間の自己防衛本能なので問題ありません。3歳以下などの小さいときに寂しがるときはしっかり向き合い、抱っこをせがまれたら対応してあげるなど、甘えさせてあげることが子どもの安心感に繋がります。
しかし幼稚園・保育園に行く年齢になっても近くに母親がいないと落ち着かなかったり、登園で離れようとすると大泣きしてしまうといった場合は母子分離不安が疑われます。
- 母親と離れることを極端に嫌がる
- 学校など、母親がいない場所に行くのを怖がる など
心身ともに健やかに育つために、3歳くらいまでは親に甘えることも大切です。
しかし、人間として自立していくために、少しずつ親から離れて行くことも必要です。
母子分離不安は、本来徐々に自立していく・距離が生まれるはずの親子関係が成長せず、親と子で依存関係が起こってしまっている状態と言えます。
母子分離不安の不登校は、小学校1年生・2年生などの低学年に特に多い傾向があります。
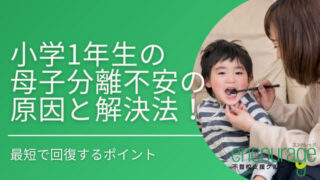
母子分離不安になる原因・理由

母子分離不安には、大きく分けて3つの原因があります。
- 子どもの生まれながらの性格・気質
- 親の育て方
- 環境
これらについて、以下で詳しくまとめていきますね。
子どもの性格・気質

子どもが生まれながらに持っている気質や性格で、不登校になりやすい気質・性格というのはやはりあります。
例えば物事を敏感・繊細にとらえるHSCの子は不登校になりやすいです。しかし、こういった個性はパーソナリティとなる部分のため、その子なりの対処法を周りの大人がサポートしてあげて欲しいと思います。
不登校になりやすい性格・気質というものはありますが、生まれながらの気質は変えられないので、親の対応の仕方や環境によって改善して行きましょう。

親の過干渉

親の過干渉が原因で子どもが不登校になるケースはよくあります。
親が普段から子どもに細かく指示を出しすぎていたり、先回りして色々と行ってしまうことで子ども自身が考えることを止めてしまい、自己解決能力が育たなくなってしまうのです。
- 自己解決能力の不足
- 心配性
- コミュニケーション能力の不足
- 退行
例えば以下のような会話をしている方は要注意です。子ども自身が考えて発言や行動をする前に、親が先に動いたり、答えを言ったり、アドバイスをしてしまっています。
母「朝食は、パンでよかったよね。バターは濃い目に塗ってあるから」
母「飲み物は牛乳でいいよね、はいどーぞ」
母「今日はお母さん遅いからお昼は置いてあるから、夕食までにお腹すいたら戸棚にお菓子があるから食べすぎない程度に食べてね。そうそう、歯磨きは忘れずにね。忘れないように歯磨き粉つけてここに置いておくから」
母「今日は午前中はゲームしないで勉強するって話してたよね。憶えてる?国語の漢字を5ページね。ご飯終わったら早く用意しないとね。」
母「じゃー仕事行ってくるね」子「はーい」
引用:エンカレッジ公式HP
お母さんが何から何までしてくれて、指示も出してくれるので、子どもは何も考えず「はーい」と言っているだけで済んでしまいます。始終受け身で、何も考えてなくても、滞りなく生活が進んでいくのです。
この受け身の姿勢が当たり前化してしまうと、学校に行くのが怖くなるのは当然です。なんせ、身の回りの世話をしてくれて指示も出してくれる人がいないですし、今まで自分で決定して行動した経験が圧倒的に不足しているのですから。
しかも、周りのお友だちは自分で自分のことを考えて言動できているので、自分だけ能力が劣っているような気分になり、自信を失くしたり、自分自身で決断して行動することが怖くなったりしてしまいます。その結果、不登校となってしまうのです。
こういった過干渉の親御さんは、時間に追われる共働きの方や、秘書や教師や看護師など周囲のサポートをする職業の方に多いのが特徴です。親御さん自身が「過干渉をしたい」というよりは、仕事の都合などで時間がなく、生活を効率よく回すために過干渉にせざる得ない方も多いです。
しかし、お子さんの自立を考えると、この対応も変えていく必要があります。
さらに言うと、お子さんが自立して親に言われなくても自分で身の回りのことも出来るようになれば、親御さんが指示・手伝う手間も省けます。お子さんの自立は一石二鳥になるため、ぜひ自立を促していきたいですね。

親の過保護

母子分離不安の原因の1つに親の過保護もあります。
親の過保護も、子どもが考えるより先に答えを出してしまったり、行動してしまうのは過干渉と同じですが、子どもが可愛すぎて愛情をかけたくて仕方がなくてついやってしまうというという特徴があります。
大まかに言うと、過干渉タイプと過保護タイプは以下のような違いがあります。
- 過干渉タイプ → 仕事のため指示せざるを得ない
- 過保護タイプ → 子どもがかわいくて仕方なく、失敗させたくない。つい口出ししてしまう
過干渉の方が自分の時間に追われたり、自分が子どもの行動が遅いことにイライラして待てないことにより先読み行動してしまうのとは異なり、過保護の方は子どもが可愛すぎて愛情をかけたくて仕方がなくてついやってしまうのですね。
この過保護タイプに多い仕事としては、専業主婦やパートなどで時間が比較的ある方で、子どもは1人っ子などその子に時間がかけられるケースが多いのも特徴です。孫がかわいくて仕方ないおじいちゃんおばあちゃんにも多いです。
逆に1人親家庭でも「私が何とかしてあげないとかわいそう」「私しかいないから愛情不足を思われないようにしないといけない」という義務感から、過保護になってしまう方もおられます。
過保護も過干渉と同様に、子どもが自己解決能力が不足したり、心配性になる影響があります。そして甘やかしが多い場合は、プライドが高く自己中心的になる傾向も見られます。
- 自己解決能力の不足
- 心配性
- プライドが高い
- 退行
子どもの母子依存

上で述べた「過保護」「過干渉」は親側の問題です。
それとは別に、子どもが親に依存することで母子依存の状態になり、子どもに依存されてしまうから親が過保護・過干渉にならざるを得ないというパターンもあります。
元々の子どもの気質もあるでしょうし、親の育て方により自信を失ってしまったり、甘やかされて失敗を過度に恐れて依存する性格になってしまったのかもしれません。
いずれにせよ、子ども自身に母子依存の考え方が染みついてしまった場合は、自立を促すのにはそれなりの時間と手間が必要になってきます。根気が必要ですが、母子依存や不登校が続くと様々なリスクが発生しますので、お子さんが小さい内が頑張りどころです。
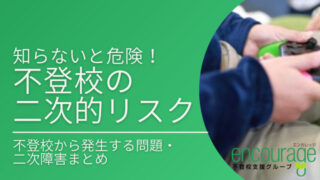
不登校になることでの母子分離不安
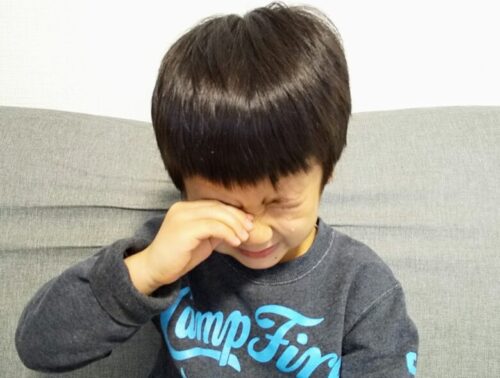
何かをきっかけに登校を渋ったり、不登校になったりすると子どもたちの心は不安定になります。そして、今までできていたことができなくなったり、1人で寝ることができていたのに一緒に寝ないといけなくなったり、留守番ができなくなったりします。不登校による退行の影響です。
そして、一緒に居る時間が長くなり退行がすすむことにより赤ちゃん返りのような状態になり母子依存が強くなり、母子分離不安になってしまいます。
不登校という環境の変化によっておこる母子分離不安の場合は、一過性であることも多いため、学校復帰できるようになれば母子分離不安は解消されやすいです。ただ、不登校、登校渋りの状態が長くなってしまうと、一過性で一時的な母子依存が定着してしまうことで母子依存がベースになってしまい、本来一過性だったものが長期化してしまうこともあります。
もともとの性格的な影響の場合は家庭教育で家庭内の対応を変化させていく必要がありますが、行き渋りや不登校による一過性の母子依存、母子分離不安の場合は、環境の改善を早くしてあげる方が家庭教育で家庭内の環境を変えるよりも母子分離不安から抜け出しやすいです。
不登校や渋りが改善できるなら早くそうしたいけど、それができないから困っているというのはわかりますが、自分の子どもがどのような母子分離不安なのかという母子分離不安のメカニズムとしては理解しておくといいと思います。
愛着障害や愛情不足?

不登校関連書籍などで、よく「不登校の原因は親の愛情不足です」と書かれていることがあります。
しかし、20年以上不登校の子たちをサポートしてきた私の経験上、愛着障害が原因で不登校になるケースはほとんどないです。むしろその逆で、愛情のかけすぎやかけちがいで不登校になるケースが近年では増えていると感じています。
そのあたりについてはこちらの記事で詳しく解説したので、ご興味ある方はご覧ください。

母子分離不安症による不登校の解決方法

一度なってしまうと、解決まで時間がかかる母子分離不安症。
お子さんに「甘えるんじゃない」「1人で学校に行けるでしょう」などと自立を促すつもりで声を掛けても、逆効果になることもしばしばです。
ここでは、母子分離不安症を解決するために大事な考え方をまとめていきます。
そもそも「甘え」ではないことを認識する

母子分離不安による不登校は「甘えなのでは」と思われる方も多いでしょう。
いじめなどをきっかけとした深刻な不登校ならすんなり「仕方ない」と認める方でも、「学校が怖い」「先生が怖い」といった一見余裕がありそうな理由で学校を休もうとするのは甘えに見えてしまうかもしれません。
しかし、子ども自身にとっては深刻な問題なのです。「甘えてないで登校しなさい」という言葉は、甘えているつもりがない子どもからしたら突き放されたように感じ、親子関係をこじらせることに繋がりかねません。
不登校が甘えなのかについては、以下の記事でも詳しくまとめていますのでご覧ください。

過保護・過干渉を改善する

母子分離不安を解決するには、まずは親の対応方法を変えることが重要です。
子どもの行動は大人から見ると遅いので、ついイライラして口出しや指示をしてしまったり、仕事に行くため時間的に焦って先回りして指示を出してしまうこともあるでしょう。
また、我が子がかわいくて失敗させたくないあまりに、良かれと思って手伝ってしまうこともあるでしょう。
しかし、親が先回り指示をしなくても、手伝わなくても、お子さんは自分で自分のことを決めて行動していく力があるのです。今は少し言動が遅かったりするかもしれませんが、少しずつ練習していく必要があります。
本当に過保護・過干渉の方は、ご自身が「過保護・過干渉かも」と気づけません。ご自身で「過保護・過干渉かも」と気づけたのなら、もう最初の一歩は踏み出せています。あとは具体的なやり方を学んで実践するだけです。
過保護・過干渉を卒業して親子ともに自立した生活を実現したい方は、エンカレッジでもご相談をお受けしています。


母親は仕事をやめる必要はない

母子分離不安が強かったり、母子登校が多くなったりするとお母さんは「仕事を辞めた方が良いのかも」と悩まれる方が多くいらっしゃいます。
しかし、その子の状況にもよりますが、子どもを自立に導くという観点では仕事を辞めないほうが良いと考えています。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
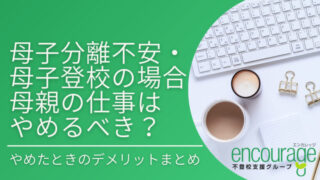
親が自分の気持ちを整理する

親がなぜ過保護・過干渉になってしまうのかという根本理由ですが、過度に子どもに世話を焼いてしまう親御さんは、その背景にはご自分の不安が隠れていることもあります。
- 「早く食べないと遅刻するよ」→「自分が遅刻してしまう」という焦り
- 「勉強しなさい」→「良い大学になんとしても入れなくては」
- 「その服じゃなくてこの服にしたら?」→「センス悪いと周囲に思われたくない」という心配
まずは親御さん自身が、自分がなぜ過保護・過干渉になってしまうのかを整理してみましょう。なぜ早くしないとイライラしてしまうのか、何に駆り立てられているのか、義務感を感じてしまうのかなどを整理してみましょう。
責任感が強い方ほど、お子さん思いの方ほど「子どもに失敗させてはいけない」「私がやらなければ」と思ってしまうことが多いですが、子どもが宿題をやらないのも、夜更かしするのも、本来は子ども自身の問題(問題所有の原則)なので、親が口出ししなくていいはずです。
宿題や習字道具を忘れるなど、本来は「あえて失敗させる」くらいドンと構えていて良いのですが、それが出来ないときは親御さん自身が今まで学業や仕事に完璧主義で頑張って来たことで、つい子どもへも妥協しにくくなっているのかもしれません。
まずは親御さん自身も、日々の自分の頑張りを認めて、肩の力を抜いてみましょう。
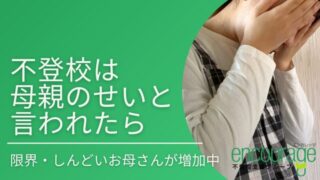
「母子分離不安症による不登校の解決方法!根本的原因と克服方法を解説」まとめ

いかがでしたか?
母子分離不安にも原因が色々ありますが、一番重要なのは普段からの親の対応方法です。親が子どもを信じて見守ることができれば、子どもも自分のことを自分で考えて行動するように意識づけられていきますし、何より「自分で決定し行動している」という満足感が自信となって大人になってもその子を支えていきます。
自分自身が過保護・過干渉の行動を取っているとはなかなか気づきにくいものです。もし不安がある方は、エンカレッジのメルマガやLINEに登録して親の対応方法の参考にしてくださいね。

 不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
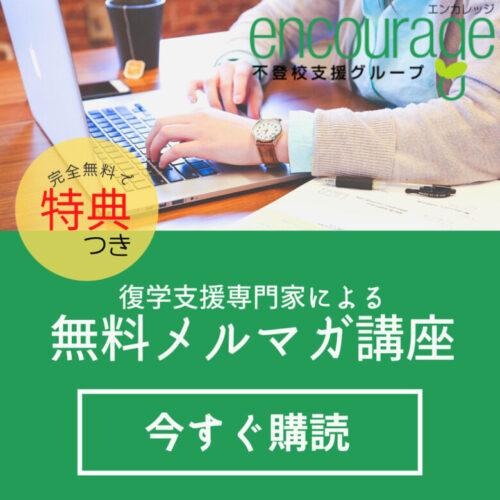 不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!
不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!