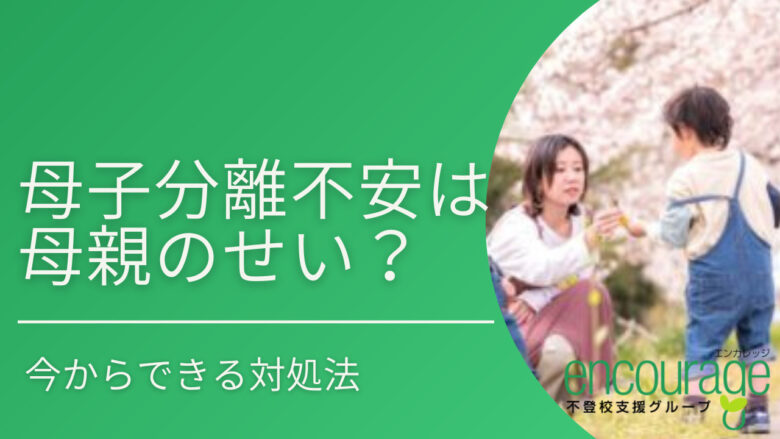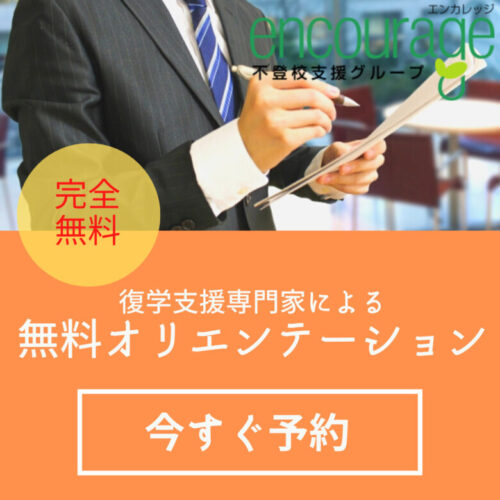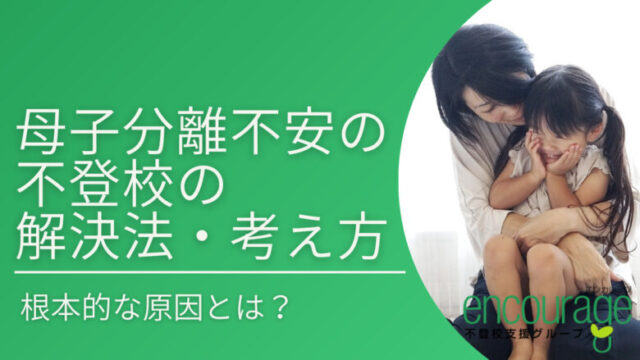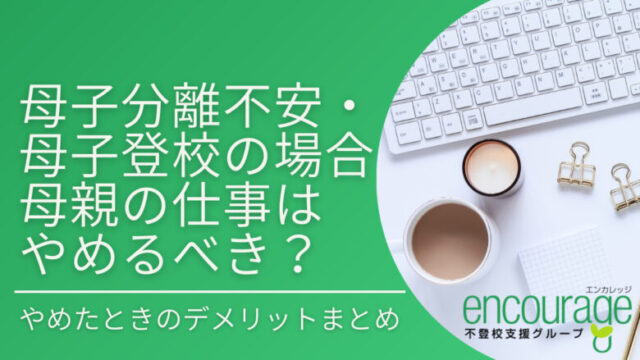最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)
- 兄弟全員が不登校のときは+αの対処法を!親のケアもポイント - 2025年7月3日
- 不登校の子どもに効く!自己肯定感を高める3つの方法 - 2025年6月15日
- 「うちの子が学校に行きたがらない…どうすれば?|不登校の初期対応と親の心構え」 - 2025年5月13日
復学支援専門家として長年不登校のご家庭のサポートをしてきましたが、ここ数年では特に母子分離不安症での不登校が多くなったと実感しています。最近も、母子分離不安の相談や母子登校の相談が多くなってきましたので母子分離不安について改めて書いていきたいと思います。
母子分離不安になるとお母さんの負担が一層増える一方、周囲からは「ただ甘えているだけなのでは」といった言葉をかけられて、「母親である自分が悪いの?」「育て方が悪かったのだろうか」とお母さん自身も苦しむ方が多くおられます。
母子登校などもあれば尚更時間の調整も大変で、1人で抱え込んでしまうお母さんも多いです。
お母さんが1人で抱え込んでいると、いつか爆発してしまう日が来ます。出来るだけ早く母子分離不安を解決することが重要ですし、今時点で「解決は無理」と感じられても母子分離不安はきっと解決できます。今まで1000人以上の不登校の親子を見てきたからわかります。
今回は母子分離不安は母親のせいなのかどうかや、解決方法についてまとめていきます。

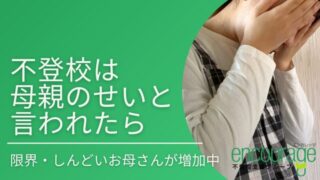
私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1000人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立17年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。
母子分離不安症は母親のせい?

結論から申しますと、母子分離不安症は母親の対応の影響があるケースもありますし、そうでないケースもあります。ただ、1つ言わせていただきたいのは決して母親のせいではないということです。一生懸命に子どものためを思って対応してきたことがたまたまボタンの掛け違いで悪循環になってしまっただけです。自分が悪いと思う必要もないですし、愛情をもって育てていることは子どもに伝わっているので決して自分を否定しないようにしてください。
そして、ボタンの掛け違いがあったのであれば正しいボタンの場所にしてあげればいいのです。そう考えましょう。なぜなら、母親が原因の母子分離不安は比較的解決しやすいからです。
お母さんが日頃の対応方法を変えれば、お子さんも連動して変わることが多いです。お子さんの性格・気質を変えたりするよりは、お母さんの行動を変えるほうが簡単ですよね。
そのため、まずはお母さんの日頃の対応方法が母子分離不安を招いていないかを確認していきましょう。以下のような場合は母親が母子分離不安症の一因と考えられますので、思い当たることがないか見てみてください。
母親による過干渉

お母さんが日頃お子さんに過干渉に接していると、干渉されて受け身に慣れてしまったお子さんは自力の判断力や思考力が身に付きにくく、自己肯定感が下がったり母子分離不安症になることがあります。
- 「早くしなさい!登校する時間だよ」→子ども自身で時間の管理をさせていない
- 「プール道具の準備はもうしといたから」→子ども自身に準備・確認させていない
- 「パンにはいちごジャムだったよね。塗っておいたから」→子ども自身に決断させていない など
できれば学校の準備なども子ども自身でできるまで見守って手を出すべきではないのですが、つい過干渉になってしまっていないでしょうか。
お母さんが過干渉になってしまうのは、現代特有の忙しさもあります。共働きでとにかく時間がなくて、毎日をスムーズに進めるために過干渉にならざるを得ないことも多いでしょう。そういった頑張っているお母さんに「過干渉」とお伝えするのはこちらとしても心苦しくもあります。
しかし、お子さんの自立心を育むことは、お子さんが生涯にわたって強く自分らしく生きていく力になるものです。
少しずつでいいので自立心を育てていくことが、長い目で見たら親御さんの手を早く離れることにもなるのでおすすめします。
とはいえ、行き渋りで朝に行く行かないの状態の時に自立を優先して干渉しないと渋りが強くなってしまう可能性があります。朝は状況によっては登校を優先するために少し過干渉をしても登校を優先させる方がいい場合もあります。
朝の渋りに対してはこちらの記事も参考にして下さい。

朝の起こし方はこちら
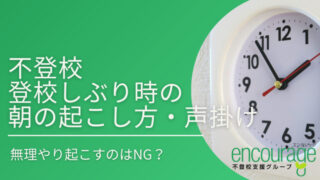
お子さんへの声掛けや対応の仕方については、こちらの記事も参考にしてくださいね。

母親による過保護

母親による過保護も母子分離不安の一因になります。
- なんでもかんでも「すごい!」とおだてる
- 子どもが失敗しないように先回りする など
子どもが可愛すぎて、失敗しないように、怪我をしないように先回りしすぎてしまうのが過保護タイプの親御さんです。お子さんができるのにも関わらず、ついやってあげたくなるのですね。
日頃から過保護の親の元で育った子どもは、自分で行う経験が不足しているために色々と臆病だったり、自信をなくしていたり、はたまた自分で失敗した経験がないためにプライドが高く完璧主義になっていることもあります。
そのため、保護してくれる・指示してくれる親がいない学校などで不安を感じるようになり、親離れ出来なくなるのです。

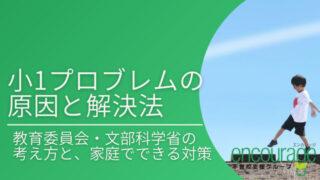
母子分離不安症の母親以外の原因

前述の通り、母子分離不安はお母さんのせいとも限りません。
環境やお子さんの気質が原因となることも大いにありますし、そもそも母子分離不安や不登校は複数の原因が複雑に絡まっていることの方が多いです。お母さんの対応が原因の母子分離不安よりも、お母さん以外の原因の場合の方が解決までには時間がかかります。
ここからは、お母さん以外の母子分離不安の原因を挙げていきますね。
子どもの不安定な気持ち

子どもの気持ちが不安定だと、母子分離不安になりやすいです。具体的には、以下のような場合に子どもは気持ちが不安定になりやすいです。
- 入園・入学・クラス替え
- ペット・親族の死や病気
- 両親のケンカ・離婚・別居・再婚
- 引越しなどで環境が変わった など
変化への適応力は人によって違うので、環境の変化に弱い子や繊細な子はどうしても不安感に駆られやすいのです。
しかし、これは誰が悪いということではありません。環境を変えてしまった親が悪いわけでもありませんし、変化に弱いお子さんが悪いわけでもありません。
生きていれば環境が変化する方が当たり前なので、大事なのは少しずつ環境の変化に慣れていく練習をすること、「きっと自分は大丈夫!」と思えること(自己効力感)です。
子どものHSC

長年不登校の子のサポートをしてきて、HSCの子は不登校になりやすいことがわかってきました。
HSCとは「敏感な子」のことで、他人の言葉に敏感・繊細に反応して精神が疲弊しやすかったりします。現在では約5人に1人がHSCと言われているので、決して珍しいことではないのです。
お子さんがHSCの場合はお子さんの生まれながらの気質が母子分離不安を招いているとも考えられますので、HSCの特性を理解して、その子にとっての解決策を模索していくことが重要です。
HSCの特性や不登校との関連については別記事でまとめていますので参考にしてください。

母子分離不安症を解決する方法

母子分離不安症は、上記にも記載したような環境の変化による影響や、お子さんの性格、気質、特性などお子さん自身の特徴にも影響があります。そして、やはり母親の対応の影響が大きく関わってくるのは事実です。そのような様々な要素が絡み合って母子分離不安症になりますし、様々な要素が絡み合った結果、行き渋りや不登校にもつながっていきます。
なので、どれか1つをもって母子分離不安や行き渋りや不登校の問題は解決はできません。大切なのは、それをしっかりとアセスメント(分析)して外在化(整理)して1つ1つにアプローチをして悪循環を好転させていくことなのです。
この原因分析や問題の切り分け、解決までの道筋の組み立てや実際のアプローチなどは、やはり専門家の方が確実で、原因がはっきりするほど母子分離不安の解決も早くなります。
母子分離不安になってしまった原因がよくわからなかったり、原因に心当たりがあっても行き渋りや不登校の問題も絡み合って何をどのようにどこから対応したらいいのかわからなくなったり、そして迷いだすと、そもそも学校復帰することがいいことなのかとどんどんわからなくなってしまいます。
そのような混乱した状態でお子さんに対応してもイライラしてしまったり感情的になってしまいますので、まずは状況をしっかり整理しましょう。
正しい整理ができるだけでも少し気持ちも整理できます。整理の方法がわからない場合は、ぜひアセスメントの得意な専門家に相談してください。
まだ相談する気力もない場合は、少しでもblogなどを参考に頭を整理してみましょう。母子分離不安症の解決方法はこちらの記事で詳しく書いていますのでそちらも参考にしてみてください。

「母子分離不安は母親のせいではない!今からできる対処・解決方法」まとめ

お子さんが母子分離不安症になったとき、お母さんの影響は確かにありますが、お子さん自身が不安になりやすい性格・気質なこともあるため、詳しくご状況を伺って分析してみないと一概には言えません。ですから周りから「母親のせい」と言われても自分を責めないでくださいね。
逆に考えれば、母子分離不安症の原因がお母さんの過保護・過干渉だった場合はチャンスでもあります。ボタンの掛け違いは正しい位置に直してあげればいいのですから。お母さんがお子さんへの対応方法を学び実践すること(家庭教育)だけで母子分離不安症が改善することも多いので前向きに取り組めるようにしていきましょう。
もし現在お子さんの母子分離不安症で悩んでいて、原因分析も難しい場合は、専門家に相談するなどして解決の手掛かりを早く見つけましょう。
エンカレッジも今までに多くの母子分離不安の親子をサポートしてきました。その経験上、アセスメント(分析)に関しては定評があります。その経験をLINEで母子分離不安関連の情報として発信したり、無料オリエンテーションでご相談も承っておりますのでぜひご活用くださいね。

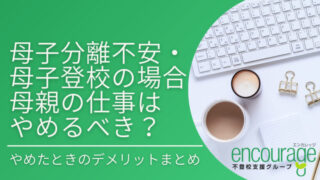
 不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
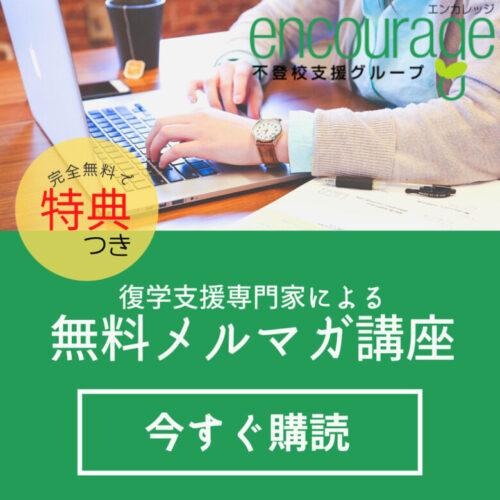 不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!
不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!