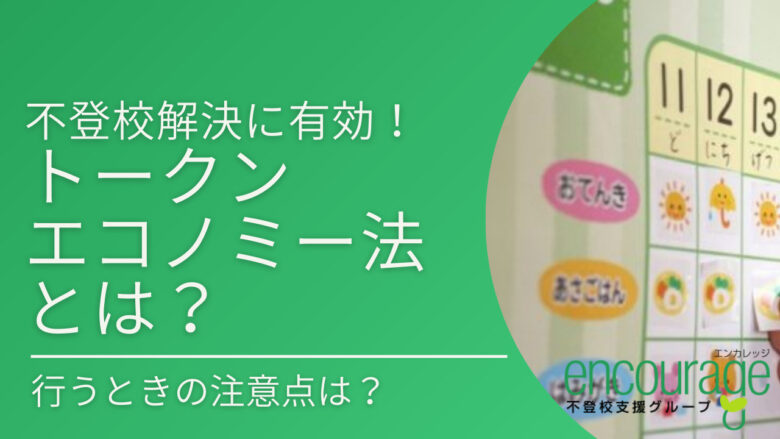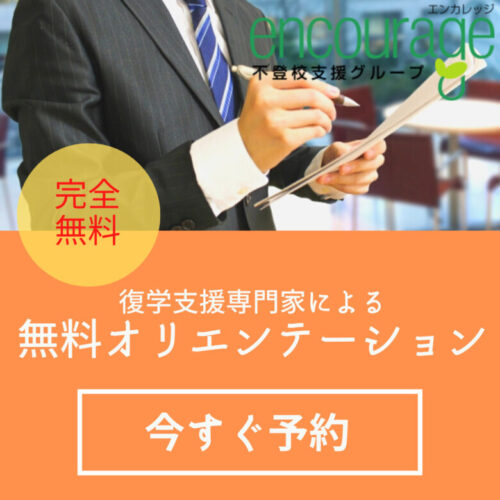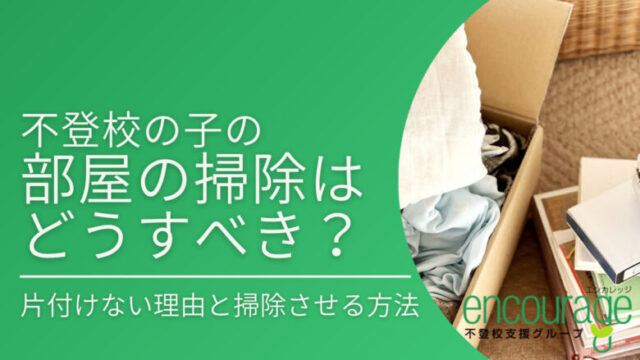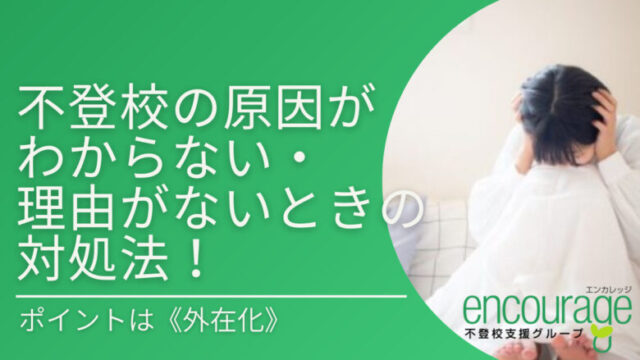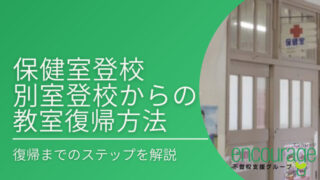最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)
- 兄弟全員が不登校のときは+αの対処法を!親のケアもポイント - 2025年7月3日
- 不登校の子どもに効く!自己肯定感を高める3つの方法 - 2025年6月15日
- 「うちの子が学校に行きたがらない…どうすれば?|不登校の初期対応と親の心構え」 - 2025年5月13日
五月雨登校・保健室登校などは、なかなか登校が安定しないのが悩みですよね。
そんなときは、トークンエコノミー法を使うのもおすすめです!
今回は五月雨登校・保健室登校などで効果を発揮する、トークンエコノミー法の進め方についてご紹介させて頂きます。
私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1000人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立17年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。
↓不登校の解決に必要な対応をまとめた記事はこちら↓
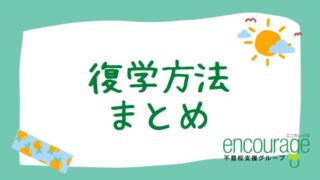
トークンエコノミー法とは

トークン・エコノミー法とは、望ましい行動をしたときに代用貨幣(トークン)を渡し、それがたまったらご褒美がもらえるといった新しい行動に対しての学習意欲を高めるための行動療法の1つです。
復学支援の場合は、子どもが登校などの望ましい行動をしたときにスタンプやシールを渡して、それがたまったらお菓子と交換したりプールや遊園地へ出かけるなどして登校を習慣化させたりします。
夏休みのラジオ体操のカードもまさにトークンエコノミー法で、カードにスタンプを押してもらって最後まで溜まったらお菓子をもらったり、賞状をもらったりしましたよね。「早起きして体操」という大変なことを続けるために効果的だったと思います。
このようにトークンエコノミー法は不登校の子どもたちのスモールステップの教室復帰に使ったり、ADHDの子ども達の行動強化や歯医者さんでも歯科衛生の促進に使われていたりします。
保健室登校・五月雨登校の解決策としてのトークンエコノミー法の進め方

ご褒美を設定することで、続けにくいことを習慣化させたり、少し楽しい気分で進められるようになるトークンエコノミー法。
五月雨登校・保健室登校の解決のために、具体的にどのようにトークンエコノミー法を活用するのかをご紹介していきますね。
【ステップ1】告知・提案

トークンエコノミー法を始めるにあたっては告知が必要になります。告知は、お母さんからでもお父さんからでも構いませんが、シールを渡したり認めてあげたりするのはお母さんの方がいいかなと思っています。
告知は「学校に行きたいけどドキドキしてなかなかいけないよね。でも行きたい気持ちがあるのはわかるからお母さん(お父さん)としてもなんとか行けるように協力したいと思ってるんだ。それで、目標を決めてできたらシールを貼っていくというようにしようと思うんだけどどうかな。それだとわかりやすいし、がんばってシールがいっぱいたまったら、お菓子を買うとか、ポケモンのカードを買うとか目標を決めようと思うんだ。その方がやる気がでると思うから。どうかな?」と伝えます。
そこで「やってみる」ということになれば次のステップに進みます。
【ステップ2】シールと台紙を準備
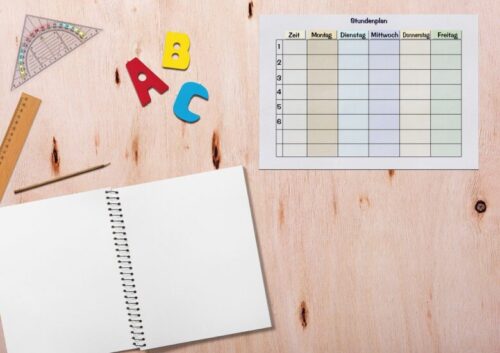
トークンエコノミー法に挑戦するという合意がお子さんから取れたら、シールと台紙を準備しましょう。
エンカレッジでは冷蔵庫などにカレンダーを貼っていただき、そのカレンダーにシールを貼るようにしています。カレンダーは100円ショップなどの卓上カレンダーのようなものでも構いませんし、手作りでマスにシールを貼るかたちでも構いません。
絵を描くのが好きなお子さんだったら、自分で自由に枠やイラストを描いてもらっても良いですし、親子で貼り絵などで一緒に製作するのも楽しめそうです。
シールの代わりにマジックや色鉛筆でマスを塗りつぶしてもいいですよ!
【ステップ3】目標を決める

次にお子さんと一緒に目標を決めましょう。
- 教室で1時間でも授業に出ることができたら金色
- 教室で給食を食べることができたら銀色
- 保健室に登校できた場合は銅色
- 休んでしまった場合は青色
達成できなかったときに赤色や黒色などのシールを貼ると、落ち込みが強くなるなるのでなるべく達成できなくてもマイナスのイメージが強くならないようなシールにします。
逆に達成できた時は金色や大好きなキャラクターのシールなどテンションのあがるものにするといいでしょう。
そして、毎日のシールが積み重なったときの1週間ごと、1か月ごとなどの中長期的な目標とご褒美も設定します。
目標はお子さんの状況によって変わってきます。簡単すぎても成長がないですし、難しすぎてもやる気が失せてしまいます。そのときどきのお子さんの登校への温度感やハードルの高さを考えながら「ちょっとだけ頑張る」ようなスモールステップの目標を繰り返し続けていけるのが理想です。
- 1回給食を教室で食べられたら、お菓子を買う
- 1週間で5回授業に参加出来たら、ポケモンカードを買う
- 1週間で3回給食を教室で食べられたら、週末にマクドナルドのハッピーセットを頼める など
ご褒美はお子さんのワクワク感も演出できるポイントです。
予算もあるかと思いますが、無理のない範囲で楽しめることを親子で会話しながら決められたらベストですね。
【ステップ4】できたら毎日シール&褒める

設定した目標通りの行動ができたかどうかをお子さんと一緒に毎日振り返って、シールを貼ります。
「いい調子だね!」「キラキラシールがたまってきてキレイだね」などの声掛けも行い、シールがたまっていく達成感を感じてもらえるようにしましょう。
【ステップ5】目標達成でご褒美

設定した目標に応じて、ご褒美も随時あげていきましょう。
また「今週は銀色がたくさんあったね」「今週は青色がひとつもなかったね」などと言葉でも評価してあげます。「自分で決めたことを自分で実行できて、お母さん嬉しい」といった親御さんの気持ちや、「頑張りをちゃんと見ているよ」と伝わるとお子さんもやる気が出ます。
「自分は頑張ればできるんだ」「頑張ったら良いことがあるんだ」という気持ちをお子さんに持ってもらうことが重要です。
【ステップ6】シールがたまったら終了

徐々にシールを積み上げていき、金色のシールがすべてになったら終了します。
そのころになると子どももシールに興味がなくなってくるので、「もう大丈夫だな」と思ったら「これでシールは終了しよう。行けるようになってよかったね、よくがんばったね。」といって最後に遊園地に行く、好きなアイドルのコンサートに行くなど最終のご褒美でトークンエコノミー法を終了します。
トークンエコノミー法での注意点

楽しい気分で続けられるトークンエコノミー法。
具体的な目標があるので、子どもも頑張りやすいです。
より効果を高めるための注意点もご紹介しますね。
ペナルティはなし

トークンエコノミー法を使う際、できなかったときにマイナス評価やペナルティーを与えないようにしましょう。
「青色(登校できず)が多かったから今週はご褒美はなし」「来週はできてもご褒美なし」などのペナルティーを与えたり、「来週はもっとがんばりなさいよ」とマイナス評価をしないことが大切です。
なぜなら、ペナルティーを与えると子どもは一時的に親の言うことを聞きますが、そのうちに「もうシールいらない!」などとイライラしてトークンエコノミー法も使えなくなってしまったり、登校が余計にイヤに感じてしまったりして、長期的に見てマイナスだからです。
青色(登校できず)が多かった場合は「青色が多かったね」と事実を認識させるにとどめ、「来週は青色を減らせるようにがんばろうね」と肯定的にアドバイスするのが効果的です。
テンションを維持

せっかくトークンエコノミー法に挑戦するので、楽しい気持ちが継続するような声掛けができたらいいですね。
例えばいい色のシールが貼れた時には、「今日は金色だったね。いい色がいっぱいになるといいね」とか「ピカピカが続くときれいだよね!がんばろうね」などとお子さんの気持ちを盛り上げていきます。
もしそのようなことを言ってもテンションが上がらない場合は、お母さん・お父さんの気持ちで伝えましょう。
「ちゃんと約束を守っていて、お母さんはうれしいな」といった感じです。
親がシールを忘れない

お子さんがシールのために頑張っているのに、親がすっかりシールの存在を忘れてしまっては「その程度のものなんだ」と子どもに感じさせかねません。
ついつい家事などに意識が向いてしまうかと思いますが、シールを貼る時間は一瞬立ち止まってお子さんを「頑張ったね」「たまってきたね~」と労ってあげましょう。
シールを貼るのを忘れない&しっかり習慣化するために、「学校から帰宅したらまずシール」のようなルーティン化するのもおすすめです。
「五月雨登校・保健室登校の解決に有効なトークンエコノミー法をご紹介」まとめ
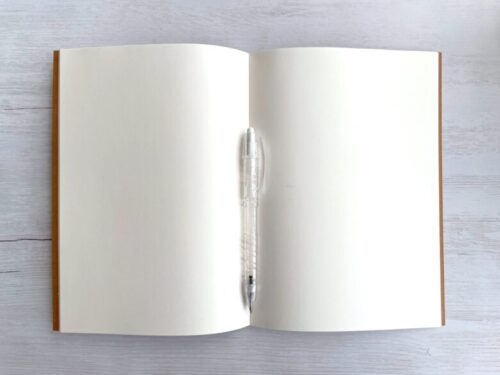
いかがでしたか?
トークンエコノミー法は五月雨登校や保健室登校などの登校が安定しないシーンでも使えるので、お悩みの方は一度試してみてくださいね。
目標やご褒美を一緒に設定したり、一緒に日々取り組んでいくことは親子の一体感にも繋がります。
ぜひ楽しんで挑戦してみてください。
 不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
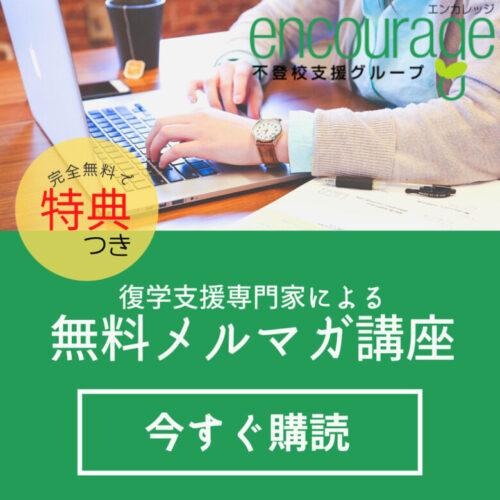 不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!
不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!