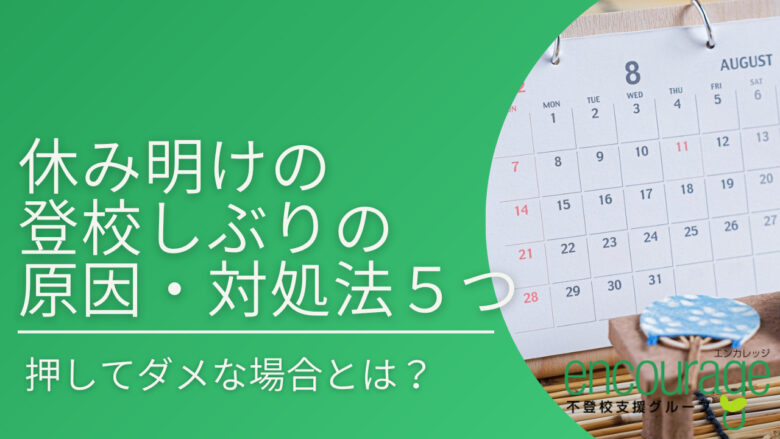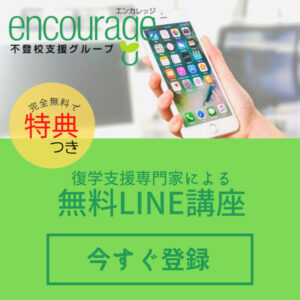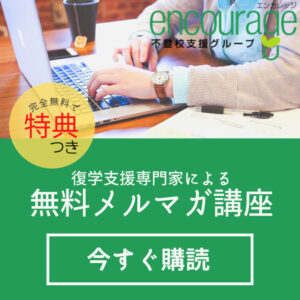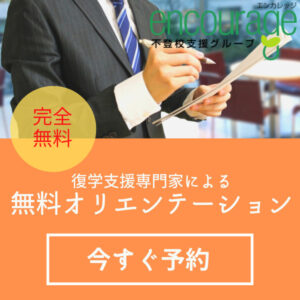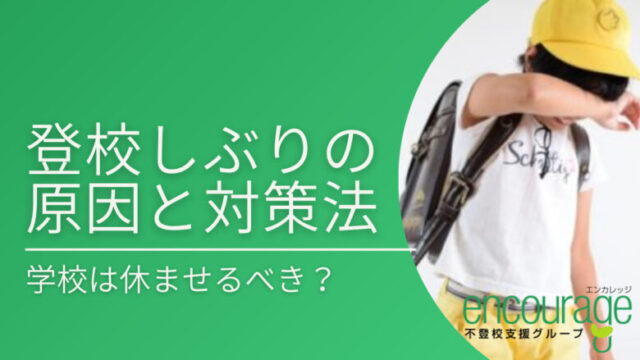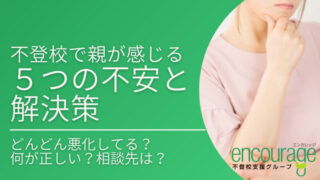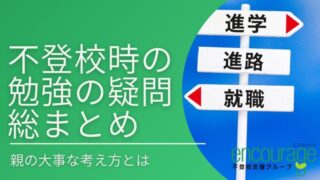最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)
- 不登校の兄弟がずるいと言われたときの対応法5つ!不登校連鎖にならないために - 2024年7月16日
- クライアントさんからの感謝の手紙 - 2024年7月8日
- 不登校の子にイライラするときの対処法5つ!親の気持ちを整理しよう - 2024年7月1日
今の子どもたちは新しい環境に適応するのに時間がかかり、慣れない環境に振り回されてストレスを抱えている子がたくさんいると感じています。
そして休み明けには「学校に行きたくない」と言う子が続出します。
登校しぶり自体は一年を通して色々なタイミングで起こることがありますが、休み明けの登校しぶりは通常の登校しぶりとはまた違った傾向があるのです。
今回は休み明けに登校しぶりが起こる原因と、その対策方法をまとめました。
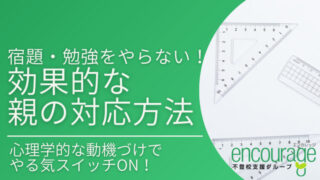
私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1000人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立17年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。
↓不登校の解決に必要な対応をまとめた記事はこちら↓
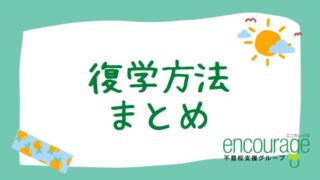
登校しぶりになったときの親の考え方

登校しぶりは「なんとか学校に行けている状態」のため、親からしたら大したことに感じずに「いいから学校に行きなさい」と子どもを言いくるめてしまいがちです。
しかし「自分の話を聞いてもらえない」と感じた子どもは親への信頼感を失って親子関係がこじれます。登校しぶりの原因がわかっていないと、対処することも出来ずにそのまま不登校になってしまうことも多いのです。
今回は、登校しぶりになった場合の大事な親の考え方をまとめます。
まずは「困りごと」の原因を確認

お子さんが登校しぶりになったら、まずは登校したくない理由をお子さんに直接聞いてみましょう。
このときのポイントは、問い詰めるように聞かないことです。
親としては「学校は行くべきなのに」「ただの甘えでは?」「登校してもらわないと困る」といった焦りの気持ちがつい先行して、お子さんが登校しない理由を責めるように聞いてしまったり、登校するように誘導尋問のようになってしまうことも多いです。
しかし、そういった親の焦りや「学校に行くべき」といった気持ちは、子どもに見透かされているものです。仕事の都合などで大変かとは思いますが、「~べき」で語ったり他の子と比較したりせずに、まずはシンプルに「登校したくない理由」のみを聞いてみるようにしましょう。
詳しい聞き方や考え方については、こちらの記事で詳しく説明しているので参考にしてみてください。

休み明けの登校しぶりの原因ごとの解決法

普段の登校しぶりと、休み明けの登校しぶりは少し傾向が異なり、休み明けの登校しぶりには「自己保存の本能」が強めに働いていることも多いです。
自己保存の本能…「自分を守りたい」と思う人間の本能。危険を回避したいために変化を恐れたりする
人間は、環境の変化で得られる利益よりも、環境の変化で失う損失やリスクの方を過剰に怖がって変化を好まないことが心理学的に発見されています。つまり、現状維持でそれほど困ることが無ければ現状維持でいいと思うのは人間の本能でもあるのです。現状維持バイアスとも言われます。
休み明けの子どもたちも、こういった変化を避ける人間の本能もあって不登校になりやすくなりますが、これは本能なので当然と言えば当然なのです。なので親御さんも「自分の育て方がいけなかったのだろうか」「愛情が足りなかったのでは」と考えずに、変化を回避するのは人間の本能なのでお子さんも親御さんも悪くないと思ってください。
危険を回避する本能とはいえ不登校になると色々なリスクも発生するので、子の将来を思えば早いうちに手を打つべきなので、ここからは休み明けによくある登校しぶりの原因・理由と対処法をまとめていきます。
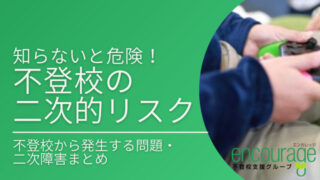
【登校しぶりの原因①】ネット・ゲーム依存で生活リズムが乱れた

自粛生活、YouTube生活の影響で完全に生活リズムが乱れてしまったことで登校しぶりするというケースが最近多いです。
外出自粛でやることがなくYouTubeやゲームばかりといった家庭も少なくないと思います。ネット依存になっていますといった相談もとても多くなりました。
現在は新型コロナウイルスの影響なのでネット依存もある程度は仕方がなかったと思いますが、そのまま不登校になっては困るので対応していきましょう。
ネット依存・ゲーム依存の場合、対処は小学生と中学生で分けて考えます。
小学生…まず生活リズムを整える。それでもダメな場合「負の強化」を用いる
中学生…「負の強化」を用いる
小学生の場合は、「もうすぐ学校が始まるから」とまずは生活リズムを直すように促しましょう。「登校しなければゲームを制限」などの負の強化を使うのもいいかと思います。
中学生の場合は、親に「明日から生活リズムを整えるために7時に起きなさい」などと言われて聞くような年齢ではありませんので、「登校日に寝不足で登校できなければゲームを制限するから」といった負の強化の使い方がいいでしょう。
「負の強化」というのは心理学の用語で、やる気を出してもらうために有効な考え方・働きかけの1つです。詳しくは以下の記事でもご説明していますので、参考にしてみてください。
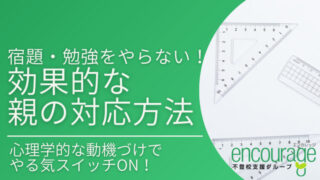

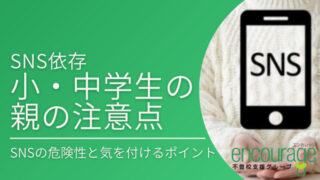
【登校しぶりの原因②】長く休みすぎて登校が面倒くさい

気持ちはよくわかります。これだけ休みが続いてしまうと学校に行くのも面倒だと感じるでしょう。大人でも会社に行くのが面倒と感じると思います。
でもそこは割り切るしかないので「長い冬休みでよかったね。でもその長い冬休みも終わり!切り替えるよ!」と学校に押し出してしまいましょう(笑)
面倒くさい子は学校に行けないわけではないので、行きだしたら慣れてきます。中途半端に休ませるとまた休みたくなりますので多少強引でも学校生活に体がなじむまで頑張らせましょう。
【登校しぶりの原因③】学校の宿題
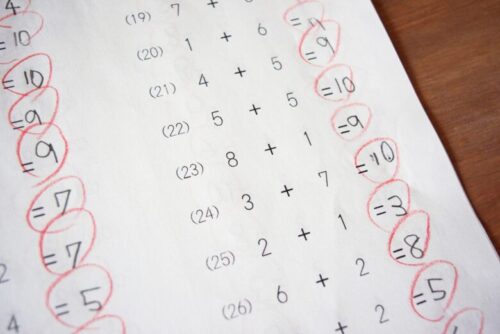
長期休暇中の勉強はただでさえ孤独で難しいにも関わらず、そこに大量の宿題がのしかかり「何でこんなに多いんだよ~」「絶対無理」「人生終った」といった会話がよく見られます。
宿題ができていなくてもなんだかんだで学校を休まないと思う方は、基本的には本人に任せた方がいいです。以前の記事でも書いた通り全体量を把握するということはやっていただくといいと思います。
宿題ができていないと登校を休みそうと思われる方は、過干渉でもいいので宿題を終わらせてください。なぜなら、登校しぶりの原因が宿題ならば、宿題さえ終われば不安がなくなり登校しぶりしなくなるからです。
このブログでも家庭教育の考え方でも子どもの自立のために過保護、過干渉、指示、提案などはよくないと伝えていますが、登校しぶりがあるならそんなことを言っている場合ではありませんので、まずは学校に行きやすいような状況を作ることが優先です。
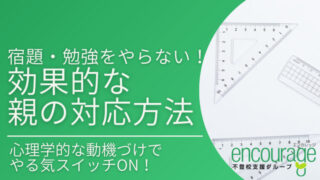
【登校しぶりの原因④】新型コロナウイルスへの恐怖

現在は減ってきてはいますが、2019・2020年に新型コロナウイルスの感染が広がってからは、ウイルスの影響を身近なものと感じて留守番ができなくなったり、お母さんから離れられなくなったりした子もいました。
オミクロン株になってから少しはよくなりましたが、まだコロナウイルスにかかりたくないから外出したくないという子もいます。
今は敏感な子ども達が多いので、そのような影響で「学校が怖い」と感じている子もいると思います。「学校に行くとコロナウイルスにかかってしまうのではないか」と不安になっている子には、少しずつ安全と思ってもらうことが必要です。

【登校しぶりの原因⑤】理由はよくわからないけど不安

実はこのパターンが一番難しいです。困りごとが把握しにくいというのもありますが、環境の変化に適応するのに時間がかかってしまう子に多いです。
今の子ども達は、環境の変化に適応するのにとても時間がかかります。ですから小1プロブレム、中1ギャップという言葉もよく聞くようになりました。長いお休み生活で体が完全にお休み生活に慣れてしまいましたので、そこから急に学校と言われてもどうしても気持ちの面がついていかないのです。
さらにコロナウイルスの影響で社会全体がギスギスして不安定です。そんな空気を今の子ども達は敏感に察知してます。何だか不安な空気の中、お休み生活から学校生活に急に気持ちの切り替われない状況というのはとても辛いです。
夏休み明けに自殺者が多いのも、長期休みの生活から学校という生活に急に切り替わる環境の変化に気持ちの面がついていかず鬱のような状態になるからというのも一因にあるようです。
学校もそうならないように今は夏休み明け後半にラジオ体操で早起きの習慣化をさせたり、プレ登校なる準備登校をしたり工夫しています。以前にはなかったことですが、それだけ子ども達が環境の変化に適応するのに時間がかかるということの表れです。
対応としては、環境の変化に時間がかかることを親が把握して、ある程度は休みながらも徐々に適応できるようにしてあげるといいです。このようなタイプの子には、登校が面倒くさい子のときのように押してはいけません。無理をさせると壊れてしまいますので。
「休み明けの登校しぶりの原因5つと解決策!押してダメな場合とは?」まとめ

今回は休み明けの登校しぶりの理由に焦点を当てました。
しかし完全不登校の場合などは宿題が引っかかっていても、宿題がができたから行けるという訳ではなく、そもそも学校に行く意思があるのかというところも問題になってくるので状況によっても対応方法は変わってきます。
不登校や登校しぶりは出来るだけ長引かせずに解決できるに越したことはないので、登校しぶりの原因分析が難しいと感じられる場合は、専門家に相談するのも一手です。