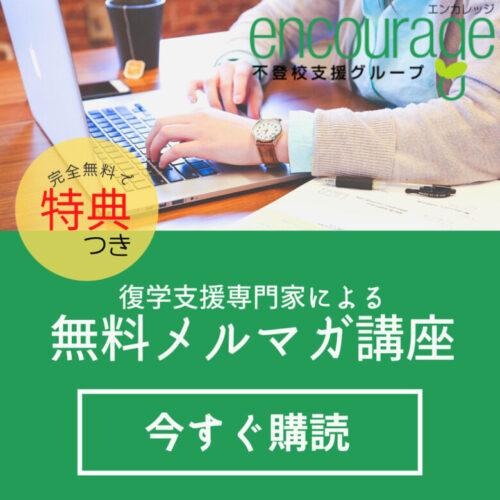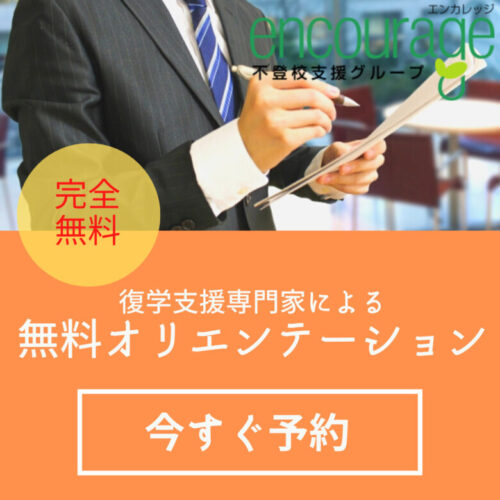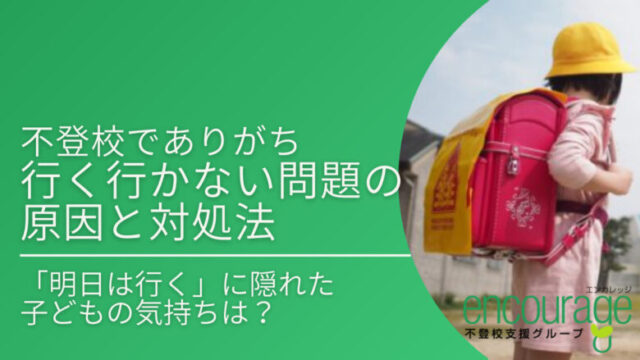最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)
- 兄弟全員が不登校のときは+αの対処法を!親のケアもポイント - 2025年7月3日
- 不登校の子どもに効く!自己肯定感を高める3つの方法 - 2025年6月15日
- 「うちの子が学校に行きたがらない…どうすれば?|不登校の初期対応と親の心構え」 - 2025年5月13日
子どもが学校を休んで家で何時間もゲームばかりしていると不安になるしイライラするというご相談をよく受けます。こういった状況では、「ゲームを制限したり取り上げたりしなくていいの?」と疑問に感じる親御さんも多いでしょう。
確かにゲーム取り上げたくなる気持ちもわかります。ゲーム依存のせいで登校できないと思ってしまいますよね。しかし多くの子どもたちはゲームに依存して不登校になっているわけではないのです。
今回は、不登校の子がゲーム依存症になってしまう理由や心理状況、ゲーム依存症から抜け出すための対処法や考え方をご紹介します。
私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1000人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立17年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。
↓不登校の解決に必要な対応をまとめた記事はこちら↓
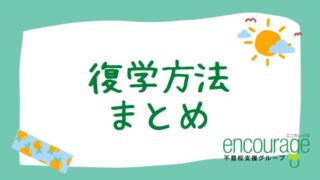
不登校のときゲームに依存してしまう理由

子どもが不登校になって毎日ゲームばかりしていると、親としては「ただ甘えているだけなのでは?」「こんなんじゃ将来どうなっちゃうの?」と登校を強く促したくなりますよね。
しかし、不登校の子がゲームをしているのはただ遊びたいだけではなく、不登校ならではの子どもの焦りや不安があることも多いです。
ここからは、不登校時に子どもがゲームしがちになってしまう心理的理由や背景についてまとめていきますね。
ゲーム依存の理由①「現実逃避」

学校を休んで家にいると「みんなに何て思われているだろう」「いつまで家にいるのだろう」「勉強がどんどん遅れていってしまう」など、子ども自身もいろいろな不安や恐怖を感じています。
すると、休んでいることへの罪悪感で子どもは不安になります。一見元気に見えたとしても、心の奥では不安や恐怖、焦りを感じているのです。
しかし、ゲームをしていれば不登校のことも考えなくて済みますよね。このように、現実逃避をするための手段としてゲームをしている子も多いのです。
ゲーム依存の理由②「退屈しのぎ」

学校を休んでいると日中は時間がどうしても余ります。
「それなら勉強したらいいのに」と思うかもしれませんが、勉強が学校のことをイメージさせてしまうので、勉強すると学校のことを思い出してしまい手につかなくなるのです。
学校のことを思い出して辛いからできない子以外にも、単純に勉強が嫌いだから1人で勉強する気になれない子もいます。
そのため結果的に勉強以外でやることと言えば、テレビ・ゲーム・YouTubeなどの動画といった選択になってきますが、学校の時間帯に面白いテレビ番組はないので、結果的にいつでもやれるゲームや動画に没頭してしまうことになるのです。
ゲーム依存の理由③「単純に楽しい」

今は、自宅にWi-Fiがある家庭がほとんどなので、インターネットにつながった環境でゲームをすることができます。
昔のゲームであれば一度クリアーしたら飽きますし、コンピューターとの対戦もマンネリ化して飽きてきます。
しかし、今はインターネット通信で新しいコンテンツが次々と追加され子どもが飽きないような工夫が各所に散りばめられています。また無料のゲームアプリなども多く、お金もかけずに楽しむことができるので、際限なく次々とゲームを楽しむことができてしまいます。
「もっと楽しく」「飽きないように」「つい続けたくなるように」というゲームメーカーの研究が、子どものゲーム依存に繋がっているのです。

ゲーム依存症から抜け出せなくなる理由

子どもがゲームをはじめるのは、ゲームが楽しいというのはもちろんですが、退屈しのぎや現実逃避が背景にあることを前述しました。
そして本来退屈しのぎや現実逃避だったゲームが、どんどん長時間プレイするようになり、ゲームをしたくてたまらなくなります。そして、そこから抜け出せなくなってしまうのです。
一度ゲームをはじめると、なぜ止められなくなってしまうのでしょうか。
ここからは、ゲームが止められなくなる理由や、ゲーム依存症から抜け出せなくなる原因についてまとめました。
ゲーム依存症から抜け出せない理由①「社会からの孤立」

不登校期間が長くなり、現実逃避、退屈しのぎ、楽しいと言った理由でゲームに依存するようになると社会との接触が少なくなります。
外に出られる子であっても後ろめたさがあるので積極的に社会とつながりを持ちたいと思う子はほとんどいません。
また、罪悪感や後ろめたさから家からまったく出られなくなる子も出てきます。そうすると家族としかコミュニケーションを取らなくなります。
しかし、ネットの世界でのコミュニティに参加することで家の中にいてもつながりを持つことができます。
ネットの世界でのコミュニティの充実が現実の世界を必要と感じなくさせてしまうのです。
ゲーム依存症から抜け出せない理由②「依存性の強さ」

「ゲーム依存症」というとギャンブル依存症やアルコール依存症ほど深刻ではないと思われがちですが、ギャンブル依存症などと同じく治療が必要な疾患としてWHOにも位置づけられました。
「ゲーム障害」は新たなICDではギャンブル依存症などと同じく治療が必要な疾患として位置づけられました。
診断基準として詳細はまだ未定であるものの
「ゲームの時間や頻度をコントロールできない」
「日常生活の中で他の活動を差し置いてゲームを最優先する」
「生活に支障が出ているのにゲームを続ける」という3つの基準を提示されており、当てはまる状態が12カ月以上続いた場合、依存症の疑いがあるとされそうです。
注意点としてはお子さんの年齢が低い場合は、12か月継続よりも早く診断が下りる可能性があります。
このようにアルコール依存症やギャンブル依存症といった治療が必要な依存症としてゲーム障害(ゲーム依存症)も加わったとことからもゲーム自体が「抜け出せない依存性のあるもの」と社会の認識が変わってきています。
ゲームメーカー各社は、どうしたらユーザーに飽きられないか、ゲームを続けてもらえるかを日々研究しています。大人が「ついゲームがしたくなるように」「たくさんプレイしたくなるように」と心理学等を研究し尽くして作りあげたゲームなので、子どもが抜け出せなくなるのは当たり前です。
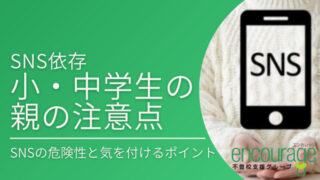
ゲーム依存症から抜け出すために必要なこと

もともとゲーム依存症(ゲーム障害)ではなかった子も、不登校をきっかけにゲーム依存症になることも多いことをお伝えしてきました。
それでは、ゲーム依存症やゲーム依存の傾向がある子に対して、どのような対応をすれば良いのでしょうか。
ゲーム依存症を改善する方法について以下でまとめていきます。
ゲーム依存症の対処法①「深刻なゲーム依存になる前に対応」

最初は「余計なことを考えなくて済むから」とゲームをしていたとしても、そのうちにゲーム依存症という精神疾患になってしまっては治療が必要になってきます。
まずはそこまで深刻にならないように早めの対応をしていきましょう。
お子さんがゲームをしているとき、親は以下のチェックポイントを確認して、ゲーム依存傾向をいち早くつかんでください。
- ゲームしている以外に笑顔がない
- 「ゲームは〇分ね」といった約束が破られる
- ゲームをしていないと、イライラしたり落ち着かない
- 生活の中心がゲームになったり、興味関心がゲームばかりになる
- 「今日はまだゲームしてない」等、ゲームをするための嘘を言うようになる など
これらの傾向が見られたら、お子さんはゲーム依存症になりかけているか、もうなっています。
「いち早くゲーム依存症に対処しなければいけない」という認識合わせを家庭内で行いましょう。
ゲーム依存症の対処法②「ゲームの制限や禁止では解決しない」

不登校になって最初の段階では「学校のことを考えたくない」という理由や「退屈だけど学校には行けない」という理由などからゲームを仕方なくやっている場合が多いです。しかしゲームの強い依存性から、次第にゲーム依存症に移行していきます。
「もともとはゲーム依存ではなかったのだから」と、親はゲームを制限したり禁止したりしたくなりますが、ゲームを制限したり、禁止したりすることは直接の解決には繋がりません。
なぜなら、不登校の子にとってゲーム依存の根本的原因は不登校だからです。ゲームを禁止したり取り上げたりしても学校に行けるわけではないため、ゲーム依存も解決しません。
本当の問題・原因である不登校が解決されていないので、お子さんの中に不登校への罪悪感があったり「現実逃避したい」「退屈すぎてつらい」といった気持ちが残っており、また気持ちがゲームに戻ってきてしまいます。
そのため、無理にゲームを取り上げることでその怒りが親に向いて暴力として表れたり、自分自身を追い込んで自分を傷つけてしまうことになるかもしれません。
- 「ゲームさせろよ!」と家具や家電を壊したり、親に暴力をふるう
- 「ゲーム機を返してくれないなら、車のカギも返さない」と親を脅すようになる
- やりがい・生きがいを突然奪われた気がして、自暴自棄になる
- 「自分の楽しみを奪う人=親」というイメージが強くなり、親子関係が悪化する など
ゲーム依存を解決したいと思ったとき、ゲームを止めさせることに焦点を当てるのではなく、そうせざるを得ない理由を取り除いてあげることが大切です。
ゲーム依存症の対処法③「学校に行けることが重要」

不登校からゲームに依存する場合、多くが学校に行けない辛さからくるのです。
その辛さを受け止め、学校復帰に向けての解決策を一緒に考え不登校の状態から学校復帰に導いてあげることがゲームの依存を解決する近道になるのではないでしょうか。
実際に、学校に復帰することでゲームに依存する理由がなくなるので、多くの子どもたちがゲームと上手に向き合えるように変化していきます。
エンカレッジで復学した子どもたちの中にも昼夜逆転していた子はいましたが、学校に行くようになると自分の睡眠時間との兼ね合いでゲームの時間を調整するようになりました。
ネットの友達から現実の友達との時間が増えて徐々にネットの友達が全てということはなくなりました。学校生活が安定すると習い事なども再開するようになり物理的にゲームの時間も減っていきます。
先ほど紹介した不登校自立支援センターのブログにもゲーム障害が疑われる子が復学した時のことをこのように書かれています。
パターン1ゲームを辞めだす。
これは復学によって同級生たちと学校でともに適応します。そして、学校のお友達感化されるようになり、ゲームから年齢相応の遊びやツールに 変化しました。カラオケ、ショッピング、遊園地、外食などに。これは交際費が高くなりました。パターン2 ゲームが趣味として残る
ゲームは好きでそれを楽しみにしながら部活から急いで帰ってきたり、就職して働いていたりしています。学生の間は学校の友人と待ち合わせをネット上でして一緒にゲームをしたりしています。学校のお友達とのゲームでの交流は正直学校での適応の助けになっています。
学校に行くことでまったくゲームをしなくなるということはありませんが、学校に行けない辛さからゲームに依存せざるを得ないケースでは、禁止をしたり取り上げたりするのではなく、その根本的な理由である学校の問題が解決してあげることが近道なのです。
「不登校はゲーム依存症の影響ではない!制限で解決しない理由と対処法」まとめ

ゲームが楽しすぎて昼夜逆転傾向になり起きられなくなって学校を休んでしまいそこから不登校になるというケースも少数ながらあります。このケースは深刻なので、医療機関等のサポートを得ながら、すぐにゲーム依存症(ゲーム障害)を解決することが重要です。
しかし不登校の子の多くは、不登校をきっかけに罪悪感からの現実逃避や退屈しのぎからゲームをはじめて次第にゲーム依存に繋がっていきます。ゲームのせいで不登校になっているのではなく、ゲームをせざるを得ない状況となっているのです。
ゲーム依存から抜け出すためには、ゲーム依存が深刻化してゲーム依存症になる前に根本的な問題である不登校の状態を解決することが大切なのです。
お子さんがゲーム依存症傾向になると親御さんの心配はさらに尽きないかと思いますが、言い換えれば「不登校が解決さえすれば、ゲーム依存などの問題が一挙に解決する」とも言えます。
ここが頑張りどころですので、なんとか不登校を解決してほしいです。もし親御さんだけでの対応が難しいと思ったら、エンカレッジをはじめとしたサポート機関に相談することも視野に入れて、色々な角度から不登校解決に挑戦してください。