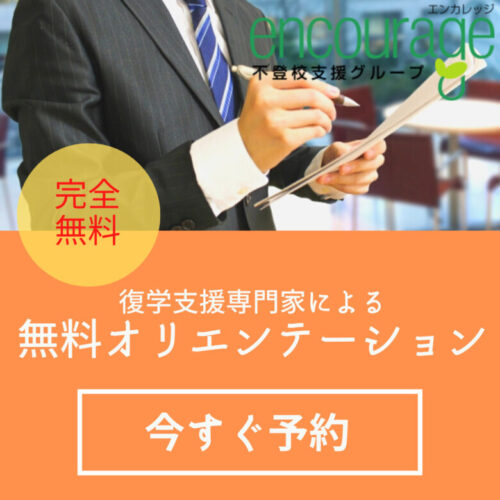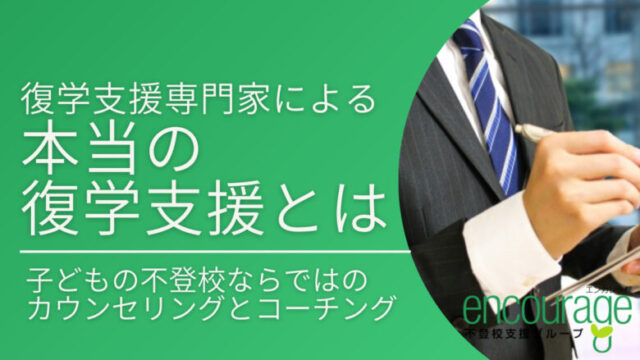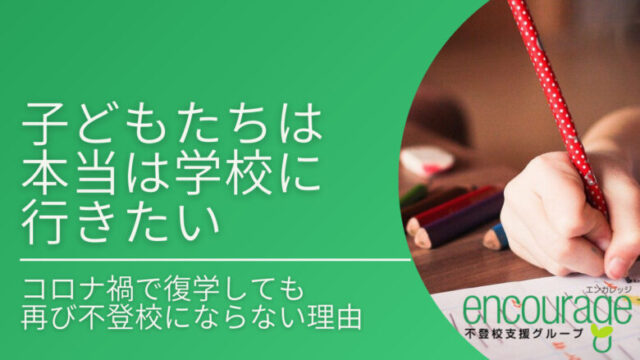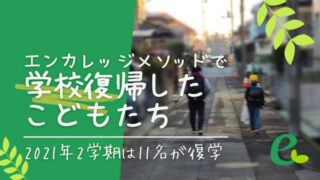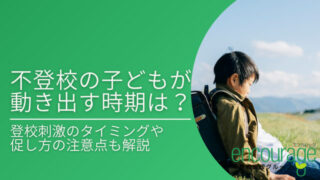監修者:若松
最新記事 by 監修者:若松 (全て見る)
- メンタルフレンドが不登校解決に効果的な理由!親の体験談も - 2022年3月10日
復学支援のプロセスにおいて重要な役割を担う存在、メンタルフレンド。
不登校やひきこもりといった問題を抱える青少年のもとに訪問するお兄さん・お姉さんのような存在ですが、具体的にはいったいどんなものなのでしょうか。
実はエンカレッジの復学支援でもメンタルフレンドはとても重要です。
今回はメンタルフレンドとはどんなものなのか、不登校の子にとってメンタルフレンドがいるとなぜいいのかについて、現役でメンタルフレンドを務める私の視点からお伝えさせていただきます。
私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1000人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立17年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。
↓不登校の解決に必要な対応をまとめた記事はこちら↓
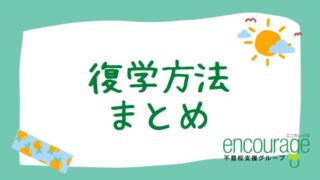
メンタルフレンドとは

メンタルフレンドとは不登校の子どものもとに定期的に訪問する人物のことで、神奈川県のホームページでは「子どもとのふれあいを通じて子どもの健全な育成を援助するもの」とされています。
メンタルフレンドは、児童相談所がかかわっているひきこもり、不登校などの子どもに対して、その兄、姉に相当する世代で児童福祉に理解と情熱を有する大学生などを子どもの心の友(メンタルフレンド)としてその家族等に派遣し、その子どもとのふれあいを通じて子どもの健全な育成を援助するものです。
子どもとの会話はもちろんのこと、ゲームなどを用いた遊戯療法などによる子どもとのふれあいによって子どもに寄り添い、子どもの健全な育成を援助します。
児童相談所や学校とも連携を取り、必要であれば復学に向けてのサポートも行います。
自治体で募集されていることも

メンタルフレンドは自治体で募集されていることもあります。
例えば神奈川県はメンタルフレンドの制度が充実しているので、活動内容や要件、相談先や募集情報にご興味のある方は神奈川県のHPをご覧ください。
自治体でも一目置かれているメンタルフレンドですが、ここで重要なのが、なぜメンタルフレンドが必要であるのかということです。
親でも学校の先生でも友達でもカウンセラーでもないメンタルフレンドですが、なぜこのような存在が必要なのでしょうか?
メンタルフレンドの役割

メンタルフレンドの役割は主に4つです。
1)「子どもを支える役割」
2)「子どもの興味や関心を広げていく役割」
3)「子どもの生き方のモデルとなる役割」
4)「子どもと社会との接点としての役割」
不登校などで、つい自分の部屋に閉じこもってしまいがちな子どもと社会との接点を作り、社会に興味を持ってもらうきっかけになるのです。
以下で詳しくポイントをご説明していきますね。
親でも先生でもない存在

メンタルフレンドは、親でも先生でもない存在です。
これは「つかず離れず」の絶妙な距離感を保ちながら子どもをケアし、子どもにとって心地の良い関係を築くことができるという理由からです。
親であれば、ついつい過干渉になってしまったり、お互いに感情の制御ができなくなかったりで甘えが起きてしまうことが多いでしょう。まさにそれこそが家庭教育の難しさといったところです。学校の先生やカウンセラーではどうでしょうか。
これだと、上下関係が明確な上に、学校制度の中に存在しているものですので、子どもが緊張やストレスを感じやすく、リラックスできる関係になることは難しいでしょう。同年代である友人たちも、復学にあたって大切な存在ではありますが、子どもが不登校である段階で適切なケアを行うことは難しいというのが現実です。
そこで必要なのが、メンタルフレンドです。最初はなんの面識もない全くの他人であるメンタルフレンドは、子どもに寄り添いながら訪問を重ねることで、まったく新しいからこそ、適度な関係を築くことができます。
これこそ、メンタルフレンドという関係を復学の過程で利用する大きな理由と言えるでしょう。
復学支援でのメンタルフレンドの役割

メンタルフレンドとの関係というものは、子どもにとっていったいどんな意味があるのでしょうか。
復学後の社会生活に向けた練習や学校との連携など、実践的なものもさまざまありますが、一番大きな役割は「子どもに自信をつけさせる」ということです。
というのも、メンタルフレンドは、すでにうまく社会生活を送っている大人として、子どもに寄り添い、そして子どもを肯定することができるからです。不登校の状態にある子どもは総じて、学校に行かなければならないのに行っていないという負い目を少なからず感じています。
それでも登校できないでいることで、自分に対する自信や復学への自信を失ってしまい、不登校が続いてしまいます。ここで、メンタルフレンドが大きな役割を果たすのです。
外の世界から来た大人に、自分を肯定され寄り添ってもらうことで、自分もまた外の世界に戻って学校生活を送れるのではないかという自信につながるのでしょう。
エンカレッジの復学支援においては、メンタルフレンドは訪問カウンセラーとして不登校のお子さんのご自宅に通って一緒に遊んだりしながら信頼関係を構築したり、学校との連携をとって再登校しやすい環境作りを行ったりします。
詳しくは復学支援内容のページをご覧ください。

メンタルフレンド訪問に対する親御さんの感想

エンカレッジでは訪問カウンセラーがメンタルフレンドとして子どもとコミュニケーションを取っていきます。
そのため、メンタルフレンドの訪問を受けた親御さんからは以下のような感想をいただいています。
とてもうまく息子との関係を築き、復学まで伴走してくれてありがたかったです。息子も私も訪問をとても楽しみにしていました。
上野先生との役割(厳しく言う人)との役割を分けていて、(メンタルフレンドは)優しく楽しく、そしておかしい所は指導してくれるのでとても良かったです。
息子の興味のあるゲームを聞いて一緒に遊んでくださったり、そのゲームについても調べたり、進めておいてくださったり、本当に息子に寄り添っていただきました。
一緒に弟も混じえて遊んでくださるので「次はいつ来るの?」と息子2人がいつも楽しみに待っていました。
子どものいないところでは息子の様子などを伝えてくださり、母の私にも親身になって寄り添ってくださいました。
大変優しく子どもたちに対応していただき、すぐに仲良くなっていた。
当時未就学児だった娘もなついて、先生の膝の上に座って遊んでもらった。
信頼できる先生に直接子どもと関わっていただき、アドバイスしてもらえて、心強かった。
子どもと同じ目線でいてくださるのか本当にすぐなついていました。なついているんだと子どもが自分で言っていました。
上野先生と違う目線でアドバイスをくださり、違う目があることの安心感がありました。
厳しめで父性を感じさせる上野先生と、子どもに寄り添い母性の立場で一番近くでサポートしていくメンタルフレンドの訪問カウンセラー。
この2つの役割があるからこそ、不登校の様々なケースでバランスが取れていくのです。
その他詳しいクライアントアンケートが気になる方は、以下からご確認くださいね!

現役メンタルフレンドの体験談

以下、わたしがメンタルフレンドとして経験した実際の話です。
最初から活発にしゃべる子どもというのはそう多くありませんが、特に口数が少なかった小学4年生Aくんについてお話します。
Aくんのもとに初めて訪問したとき、わたしとの直接の会話というものはほぼ皆無でした。もともと他人の気持ちを考えられる子だったので、気を遣おうと不安になったり緊張したりしていたのかもしれません。
自分で受け答えをすることはできず、横にいるお母さんに小声で話しかけたり表情で訴えたりすることで、意思疎通を代わってもらっていました。
そこで、Aくんが好きな鉄道のゲームなどを中心に、遊戯療法を行い訪問を重ね、機会があるたびにAくんの良いところを褒め、またいろいろ質問をして会話を増やしていきました。
最初はもちろん同席しているお母さん経由での受け答えでしたが、訪問のたびに、隣に座るわたしに直接話してくれることが増え、お母さんがいなくても楽しく会話できるようになっていきました。
私が帰ったあと、お父さん・お母さんに、話した内容や私と仲良くなれたということを嬉しそうに話していたそうです。はじめに肯定や共感を重ねることで、不安も私に話せるようになり、自然な会話ができる心地の良い関係へとつながっていったのでしょう。
初回の訪問と最後の訪問とではみちがえっており、元のおもいやりはそのままで明るく話してくれる子になっていました。Aくんは今も元気に登校できているようで、非常に嬉しく、また本当に素晴らしいな、頑張っているなと思います。
このように、メンタルフレンドによって受け入れられ肯定されるということは、非常に大きな自信につながるのです。この重要さについて確認していただけると幸いです。
\メンタルフレンドや訪問カウンセラーをご希望の方へ/
\復学支援について詳しく知りたい方へ/
※エンカレッジのHPに飛びます
 不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
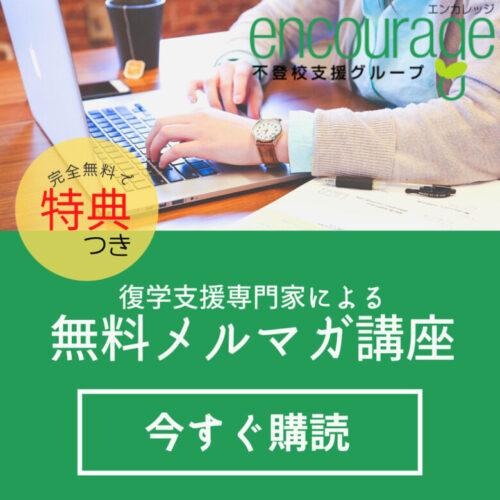 不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!
不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!