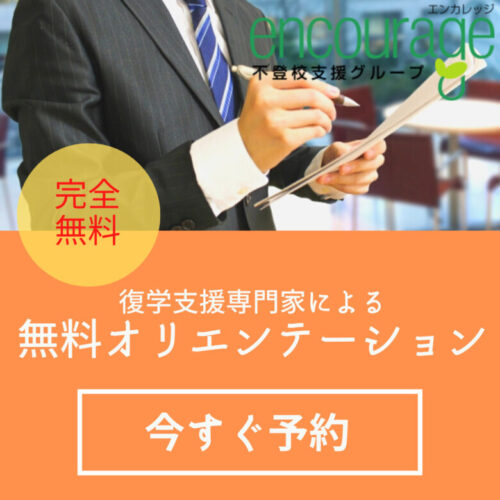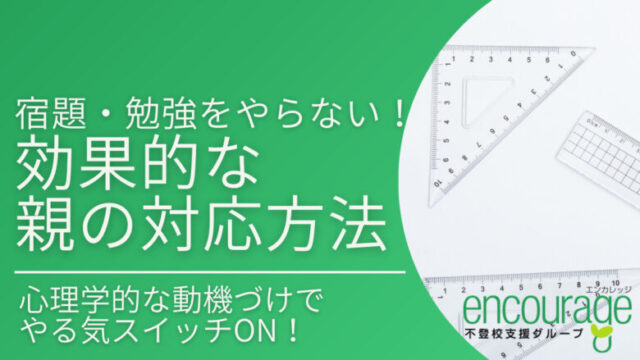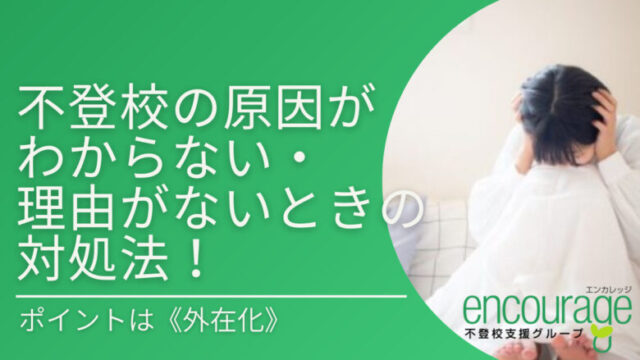父親不在で不登校になる理由と対処法!ポイントは家庭内の「父性」

最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)
- 過剰適応起因の不登校の特徴10選|頑張りすぎる子に多いサイン - 2026年1月19日
- 2025年の2学期は6名の子ども達が学校復帰しました! - 2026年1月7日
- 岸和田市 学び舎ゼミでの講演のご報告 - 2025年12月15日
近年は共働きが増え、男性も家事や育児を担うことが増えてきました。街中の保育園の送迎も、一時代前はお母さんばかりだったのが、ここ数年は一気にお父さんの送迎も増えていると感じます。
これは非常に良い傾向で、実は父親が育児に関わることは非常に重要なのです。父性不在が原因で不登校になったケースもいくつも見てきました。
今回は、父親不在の家庭で不登校が起こる理由や、不登校を防いだり解決する方法について私の意見をまとめたいと思います。

私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1000人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立17年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。
父親不在と不登校は関係する

エンカレッジでは、家族療法の考え方をしています。つまり、不登校の原因はその子だけにあるのではなく、家族システムが機能していないことが不登校と言う現象になって表出するという考え方です。
つまり不登校の原因は、家族システムの機能不全なのです。
家族システムは、父性/母性のバランスが保たれて機能します。
母性:子どもを健やかに育む、辛いときに癒す、ありのままを受け入れる
父性:子どもに社会のルールや厳しさを教える、社会に適応し成長するよう促す
この母性/父性というのはあくまで役割であって、母性をお母さんが必ず担わなければいけないわけではありません。しかし、家庭内においては母性と父性の両輪があって家族システムが機能しやすいのです。
もし子どもが母性のみに触れていると父性が不足して、以下のような性格・気質になってしまう恐れがあります。
- 不安やストレスに弱い
- 母子依存が起こりやすい
- 甘えてばかりで自立できない
- 社会のルールやマナーを守れない
- 万能感が強く自らを過大評価する
- 苦しいことがあるとすぐに諦めてしまう など
父性不在が続くと子どもは上記のような特徴が出てくるので、不登校をはじめとした何らかのトラブルが家庭内で起こりやすくなってきます。
特に、父親不在が母子依存を招き、その結果不登校になってしまうというケースも多いのです。

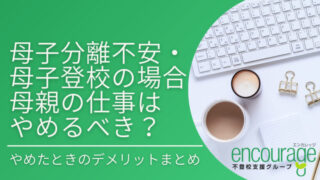
家庭内で父親不在のケース

父性不在の家庭でしばしば不登校が起こると前述しましたが、「父性不在」というのは単に「お父さんがいない」ということだけではありません。
お父さんが家にいるのに、まるでいないかのような状態も「父性不在」と言えます。
父性不在のケース例を挙げていきますね。
父親がいない

「父性不在」でまず挙げられるのは、父親の存在がいないというケースです。死別や離婚だけでなく、単身赴任や長時間労働でほとんど会えないケースもこれに当てはまります。
このような場合は父性不在でも仕方ないため、例えばお母さんが母性と父性の役割で対応していくことになります。
昔は地域で子育てをしていたため、学校の先生やクラブのコーチ、地域を見守るおじいさんなどが父性を発揮してくれていました。しかし近年は地域の大人が子どもを叱ることも激減しており、父性の担い手はほとんど家庭内となってしまいました。
そのため、現代日本では家庭内で父性を担えることがますます重要になってきたと言えるでしょう。
家庭内で父性が必要なため、もし父性を担うお父さんが家庭内にいない場合は、お母さんが父性も担えるのが理想です。父性的な考え方や対応方法について学び、実践していくことが不登校の改善や防止に繋がります。
父親が育児に無関心

父親が育児に無関心であることも、父性不在と言えます。
父親が育児家事に無関心で手伝わない場合、母親は父親に期待せずに1人で家事育児を回そうとし、その結果、父親が家にいるのにまるでいないかのような状態になってしまいます。
その結果、母子依存が進み不登校になってしまうケースがあります。
このケースで不登校になった場合は、母子依存を改善するとともに、父親に育児に関わってもらうことが重要です。
父親が育児をしない理由は、育児の面白さがわからない、育児の仕方がわからない、育児よりも趣味を優先したい…など色々考えられますので、まずは原因を分析するところから始めましょう。
父親が家庭内で地位が低い

父親自体は家にいるものの、軽視・蔑視されてまるで不在かのように扱われているケースもあります。
例えば父親と母親が不仲で子どもが母親側について父親がのけ者扱いされていたり、亭主関白や自己中心的な言動から家族から腫れ物に触るような扱いを受けていたり、お金や異性にだらしがなくて呆れられていたりなどです。
父親が家庭内で地位が低い場合も、まずは父親が育児参加することが可能かどうかを考え、家庭内でどのように父性を発揮できそうかを検討していきましょう。

父親不在で不登校になった場合の解決方法

父性不在の家庭で育った子は打たれ弱く、社会のルールや厳しさも知らずに大きくなってしまう傾向があることをお伝えしましたが、それでは父性不在の家庭はどのように対処すれば良いのでしょうか。
父性不在の家庭で行うべき対処法をまとめていきます。
父親に父性を学んでもらう

家庭内で父性が不在の場合、まずはお父さんに父性の役割を担ってもらうのがベストです。
お父さんに「父性とは何か」を学んでもらい、お父さんのどのような言動が子どもを自立させ成長させるのかを知ったうえで、日々お子さんに対応してもらいます。
子どもは家庭内で父性に触れることが出来てくると、徐々に不登校が改善されていきます。

母親に父性の役割も担ってもらう
 A mother studying in her room and a child playing next to her
A mother studying in her room and a child playing next to her父親がいない場合や、どうしても頼れなさそうな場合は、お母さん1人で母性と父性の両方の役割を意識して頂くことが多いです。
母性と父性の両方を担うのは気が重いかもしれませんが、どのように対応すべきかはお子さんを観察することで見えてくるので、慣れてくると悩むことなく良い対応が取れるようになってきます。
エンカレッジでは会話ノートを使って心理学でいう観察法を行っているのですが、会話ノートで日々のお子さんとの会話や状況を伺うと「今は母性/父性のどちらを強くすべきか」「どのように対応すると子どもの自立を促せるか」がわかるので、それを都度フィードバックしていきます。
するとお母さん自身がその時々のお子さんの様子からどのように父性を発揮すべきかを考えられるようになるので、お子さんもどんどん不登校になりにくい思考回路や行動パターンが身に着いていくのです。
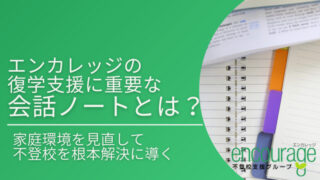
家庭外で子どもが父性に触れる機会を作る

家庭内に父性不在の場合、家庭外でお子さんが父性に触れる機会を作るのも有効です。
例えばスポーツのクラブチーム等に加入して、スポーツの中でめげない気持ちや根気強く練習する力、上下関係などの社会のルールを学ぶきっかけにするのも良いでしょう。
ただ、週に数時間父性に触れただけではなかなか身につくまでに時間がかかるので、やはり家庭内に父性の役割を持つ人がいることがおすすめです。
第三者に家庭内に介入してもらう

父親を頼れない、父性を学んでもなかなかうまくいかないというときは、父性の役割を担える第三者に一度家庭内に介入してもらうことがおすすめです。
これはエンカレッジでも良く使う手法で、まずカウンセラーがご家庭を訪問し、お子さんをカウンセリングしたり認知行動療法のコーチングをしながら、必要に応じて父性を発揮し気持ちを奮い立たせる励ましなどを行っていきます。
そうして父性の立場でお子さんとの信頼関係が築けてから、その父性を家庭内に移譲するのです。
例えばゲーム依存症の子に厳しく言えない親(父性不在)に代わって「ゲームは宿題が終わってからにしよう」というルール付けを行い、定着してきたらその主導権をお父さんに戻すような感じです。
このように第三者が入ると父性の復権は比較的スムーズに行えるので、始めのハードルが低くなると同時に家族システムの正常化や不登校解決までの時間を短縮することができるのです。
「父親不在で不登校になる理由と対処法!ポイントは家庭内の父性」まとめ

日本は長らく「父親は仕事、母親は育児家事」という性別役割分担が社会的に行われてきました。母親が育児家事を1人で担い過ぎて母子依存傾向になる家庭も多く、それが結果的に不登校に繋がっていることも少なくありません。
だからこそ、家庭内で父性の役割を担える人が重要なのです。家庭外で父性に触れられると良いのですが、近年はその機会も失われつつあるので、家庭内での父性の重要性はますます高くなっていくでしょう。
もし家庭内で行うべき父性対応の仕方がわからなかったり、父性対応が苦手と言う場合はエンカレッジにご相談ください。ご家庭のご状況やお子さんの性格に合わせた対応方法をお教えし、家庭内で実践できるようになるまでフォローします。
 不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
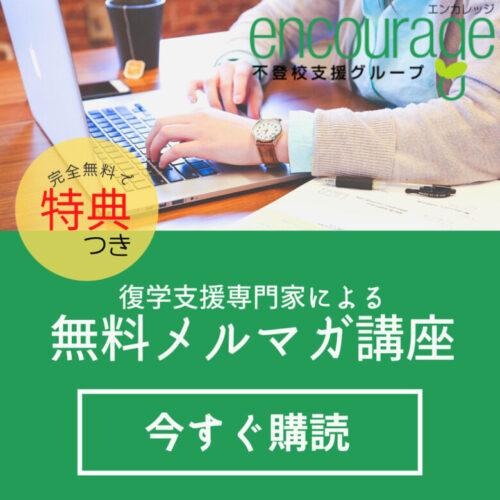 不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!
不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!