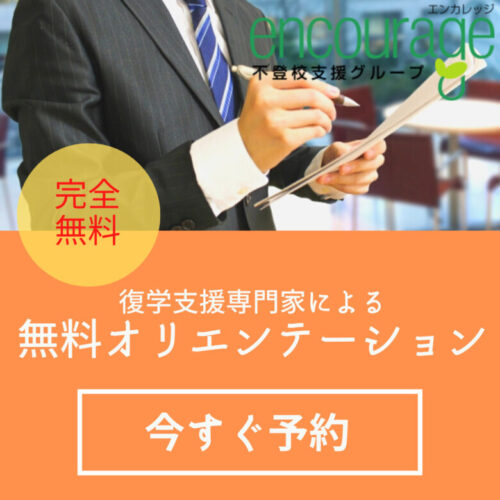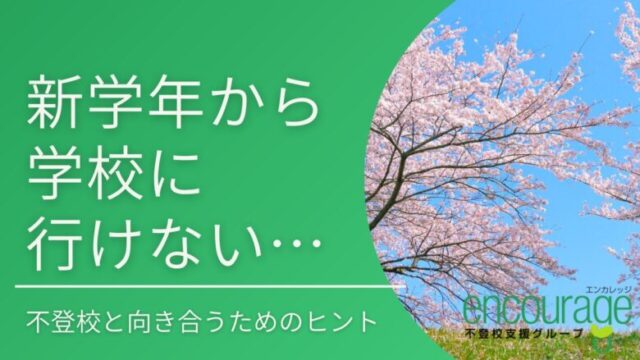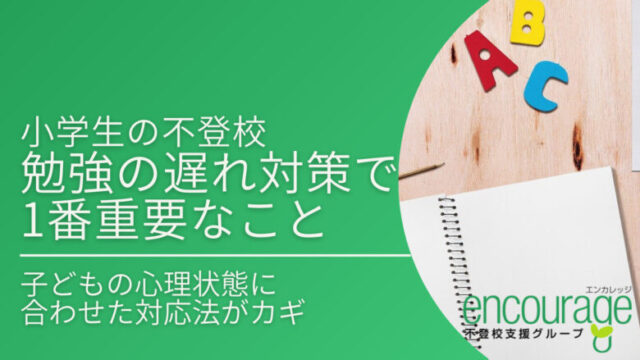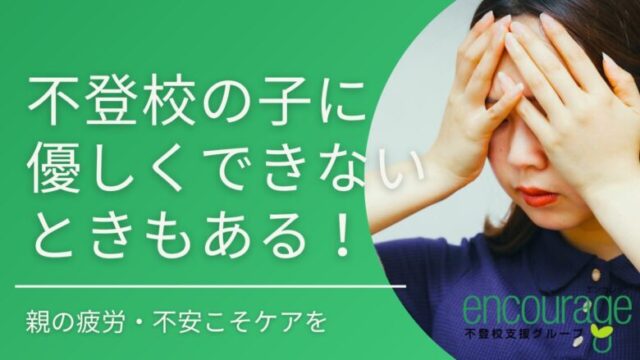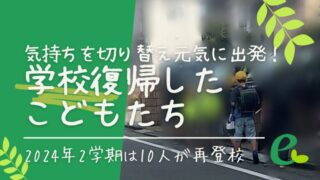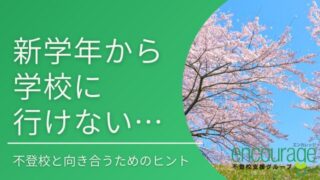新しい環境は不登校になりやすい!環境変化(先生・クラス)が苦手な子の対応3つ

最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)
- 過剰適応起因の不登校の特徴10選|頑張りすぎる子に多いサイン - 2026年1月19日
- 2025年の2学期は6名の子ども達が学校復帰しました! - 2026年1月7日
- 岸和田市 学び舎ゼミでの講演のご報告 - 2025年12月15日
新学期やクラス替えのシーズンは、新しい人間関係やルールに慣れない子どもにとって大きなストレスがかかります。
特に、もともと環境の変化が苦手だったり、慎重な性格のお子さんは、自分では思っている以上に大きなプレッシャーを感じているかもしれません。
こうしたストレスが強まると、「学校に行きたくない」「クラスになじめない」といった不安を抱えるようになり、そのまま不登校につながってしまう場合もあります。
今回は、新しい環境(先生・クラス)に苦手意識を持つ子どもへの対策と、保護者や学校側がどのようなサポートをしていけば良いのかについて解説しました。
お子さんが新しい環境が苦手だと感じる方はぜひ参考にしてください。
私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1000人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立17年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。
新しい環境が苦手な子どもに見られる特徴
【特徴①】慎重で繊細な性格

初めて会う大人や同級生に対してすぐに心を開けない子は、警戒心が強い反面、物事を深く考えるという長所も持っています。感受性が強い子も多いのが特徴です。
一方で、適応には時間を要することが多く、相手の出方を観察しながらゆっくり距離を縮めようとします。
そのために慣れるまでにストレスがかかるので、最初の段階で行き渋りになるケースも多いです。
【特徴②】変化への抵抗感

クラス替えや先生の交代など、学校生活のなかでは毎年ある程度の変化がつきものです。
しかし、変化に対して強い不安を抱えがちな子は、“慣れたやり方”や“安心できる人”がそばにいない状況が苦痛になります。
新しい環境が合えばいいですが、以前のクラスの方がよかったと感じると「前の方が安心できた」「新しいクラスは行きたくない」と登校すること自体を回避し、学校を休むという選択を取りやすくなってしまいます。
【特徴③】完璧主義な性格

- 新しい環境でも上手くやりたい
- 皆に認められたい
- 恥ずかしいところを見られたくない
完璧主義の性格の子は、少しのミスや失敗を極度に怖がってしまいます。
そのため、やり直しがきかないと感じてしまうとそれを乗り越えようとするよりも、行かなければ失敗しないと登校自体を回避するようになり、不登校につながる場合もあります。
新しい環境起因で不登校になったときの親の考え方
不安の原因を一緒に整理する

「先生が怖いの?」「クラスメイトとの関係が不安なの?」「集団行動が苦手なの?」といった具合に、具体的に何を不安に思っているのかを確認し、整理してあげると良いでしょう。
本人も“何が嫌なのか”をはっきり言えずに悩んでいることが多いので、質問を投げかけながら気持ちを言語化できるようサポートしてあげると安心感が生まれます。
小さな変化や成長を認める

少しだけでも教室に入れた、休み時間に友達と話せた、などの小さな進歩を見逃さず、「よくがんばったね」と認めてあげることはとても大切です。
親からの肯定的な言葉掛けがあると、子どもは“自分は成長できている”“少しずつ慣れてきている”と感じやすくなり、新しい環境への苦手意識がやわらぎます。
周囲が前向きに待つ姿勢を示す

子どもが不安を抱えている状態で「早く学校に行きなさい」「友達を作りなさい」と強く促すと、逆にプレッシャーが増してしまいます。
親として焦る気持ちは理解できますが、「あなたのペースでいいんだよ」「今は少しずつ慣れていこうね」と伝えることで、子どもが安心して自分の気持ちを整理できる雰囲気をつくることが大事です。
だからと言って「無理せず疲れたら学校を休んでもいいよ」と休む選択肢を親として提示してしまうと休むことを子どもも選択しやすくなります。
休むことで次につながる子もいるので、そのような子にはプラスですが、休むことでの2次リスク(勉強の遅れ・周りの目)などが膨らむ場合もあります。
また、ストレス耐性が不足し「少し嫌だけどがんばろう」というような乗り越える力が不足してしまう可能性もあるので、プレッシャーはかけず子どものペースに合わせてあげる必要はありますが、休むという選択肢に関しては慎重に考える必要があります。
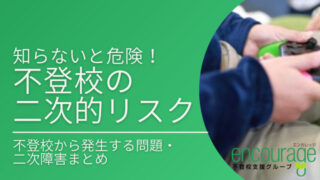
環境変化が苦手な子への具体的な対策とサポート方法
【環境変化への不登校対策①】学校や担任の先生との連携を図る

不登校が続きそうなときは、まず学校や担任の先生とこまめに連絡を取ってみましょう。
家庭ではどのような様子か、新しいクラスでどんなフォローをしてもらえると安心できるかなど、具体的に相談しながら進めるのがおすすめです。
学校に「家での不安を分かち合ってもらえる協力者がいる」という安心感があるだけでも、子どもの気持ちは安定しやすくなります。
また新しい環境が苦手な子は、なるべく安心して通えるように「仲のいい友達と一緒に登校してもらう」「苦手な子を別のクラスにしてもらう」「次も担任の先生が一緒がいいなら、同じ担任になるようにお願いしてみる」など学校に配慮をお願いしてみましょう。
不登校の子や休みがちな子の場合は特に新しい環境は大切ですし、それはモンスターペアレントではなく合理的配慮と考えて、学校側に迷惑なのではと考えず積極的に伝えるようにしましょう。
【環境変化への不登校対策②】焦らずスモールステップで進める

すでに不登校になっていたり、五月雨登校など登校自体が不安定で、さらに新しい環境が苦手な場合は、できる範囲で進めていくことも大切です。
「朝だけ行って早退する」「週に何回かは保健室登校や別室登校を利用する」など、子どもの状況に合わせた段階的な登校プランを作っていく方法があります。
学校側と相談のうえ、授業をフルに受けるのではなく“少し顔を出すだけ”からスタートするのも一つの手段です。最終的に通常登校が目標だとしても、まずは小さく区切った成功体験を積むことが長続きのコツになります。
ただ、休むという選択肢に関しては先ほども書いたリスクがありますので、こちらもお子さんの状況に合わせた判断が必要になってきます。
【環境変化への不登校対策③】カウンセリングや専門機関の利用

不登校の原因や本人の不安が複雑化している場合は、家庭だけで対処しようとせず、エンカレッジのような不登校の専門機関を活用するのも有効です。
親御さんが色々なところに相談に行き客観的な視点からアドバイスをもらって、その中で自分の家庭に合ったサポートを受けることでより前向きに解決策を見つけられることが多々あります。
今回の記事で何度も記載した「休むという選択肢」に関しては様々な要素を加味した上でお子さんに合った対応が必要になってきます。
特に新しい環境、スタートでつまずいてしまうとそこからどんどん悪循環になり一気に不登校の状態になるということも多い時期です。客観的に判断してもらうためにも専門機関にサポートしてもらうのも大切かと思います。
「新しい環境は不登校になりやすい!環境変化(先生・クラス)が苦手な子の対策3つ」まとめ

新しい先生やクラスの変化がきっかけで不登校になりやすい子どもは、決して“わがまま”や“甘えている”わけではありません。
親の目には何気ない環境の変化でも、子どもにとってはとても大きなストレスと感じられるのです。その不安を否定するのではなく、理解し受け止めたうえで、少しずつ“新しい環境に慣れるためのステップ”を組み立ててあげることが大切です。
保護者や学校の協力を得ながら、今回の環境を無事に乗り越えることができれば、また不登校の子に関しては今回の新しい環境をきっかけに復学できれば次にまた変化が訪れたときにも今回の成功体験が自信につながってきます。
ぜひこの新しい環境をプラスに捉えられるよう親としてできることをやっていきましょう。
 不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
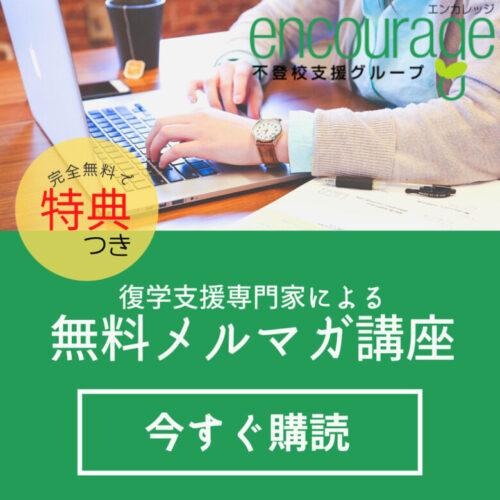 不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!
不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!