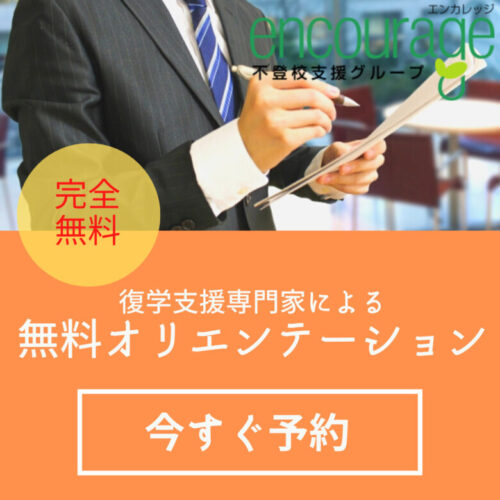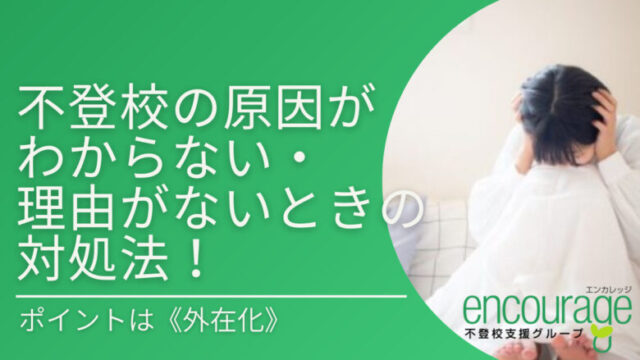新学年から学校に行けない…不登校と向き合うためのヒント
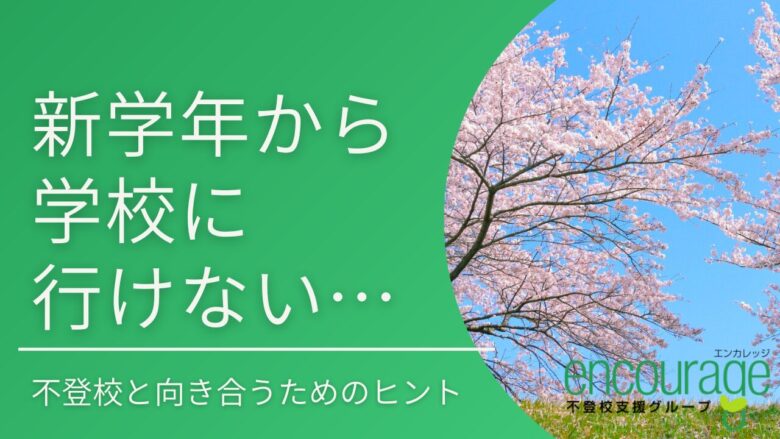
最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)
- 過剰適応起因の不登校の特徴10選|頑張りすぎる子に多いサイン - 2026年1月19日
- 2025年の2学期は6名の子ども達が学校復帰しました! - 2026年1月7日
- 岸和田市 学び舎ゼミでの講演のご報告 - 2025年12月15日
4月、新しい学年のスタート。元気に登校する子どもの姿を見て、「うちの子は学校に行けなかった…」と、胸がギュッと締めつけられるような思いをしている方もいるかもしれません。
「このままずっと行けなかったらどうしよう」「どう向き合えばいいの?」と、不安や焦りが大きくなるこの季節。
そんな親御さんに向けて、この記事では不登校の小学生、中学生と向き合うためのヒントをお伝えします。
不登校は特別なことじゃない
小学生、中学生の不登校は年々増加中

まず知っておいてほしいのは、不登校は誰にでも起こるということ。
文部科学省の統計でも、小学生、中学生の不登校児童は年々増えており、特に小学生は低学年から学校に行けなくなるケースも珍しくありません。もちろん、中学生は中一ギャップの影響も受けやすいです。
新学期が始まったばかりですが、昨日からスタートで2日目から行けなかった子や、初日のギリギリまで行く気で行けなかった子などすでに多くの相談がきています。
つまり、「うちの子だけ…」と感じる必要はないんです。
「甘え」や「親のせい」じゃない

「ただの甘え?」「親の育て方が悪いのかな…?」と自分を責めたり、逆に「どうして行かないの!」と子どもを責めてしまうこともあるかもしれません。
でも、不登校は子どもが出しているSOSサイン。子どもなりに頑張ろうとしたけど、「僕だけ私だけでは限界」という家族全体の問題というサインを出してくれていると受け止めましょう。
そして、不登校が解決しにくいのは、親の子育てが悪いとか、子どもが甘えているとかではなく、不登校になると復帰が難しく悪循環になりやすい不登校のシステムの問題なので、そこを理解しないといけません。
なので自分の子育てが悪いとご自身を責めないでくださいね。
新学年は見直しのチャンス
担任やクラス替えは環境リセットのタイミング

新学年が始まる春は、環境がリセットされるタイミングでもあります。
担任の先生が変わり、クラスメイトも変わり、学ぶ内容もスタートがみんなと一緒です。それをプラスにして、今まで不登校が長引いてしまっている子はこのタイミングを活かしていきましょう。
逆に新しい環境になじむのに時間がかかる子は大変な時期です。不登校が長引かないように大崩れしないことを意識して、自分のペースで焦らず進めていきましょう。
「今」の気持ちを丁寧に受け止める

「新しいスタートだからこそ行ってほしい」という気持ちが強すぎて親が焦って感情的になってしまうと子どもの気持ちも不安定になります。
行ってほしいという気持ちは親もそうですが、お子さんも行きたいのです。まずは子どもの今の気持ちを大切にしましょう。
無理に登校を促すのではなく、心の状態に寄り添って、ゆっくり整えていくことが大切です。
家庭でできる3つのサポート
①無理に登校させようとしない

小学生は、気持ちを言葉でうまく表現するのがまだ難しい時期。
「行きたくない」と言われたときに「なんで行きたくないの?何が理由なの?」と聞いてもその裏には不安・怖さ・緊張など、たくさんの感情が隠れています。
「何があったの?」と問い詰めるより、「一緒に考えよう」と安心して話し合える環境が何よりのサポートです。
逆に中学生は、行く気で制服に着替えて時間になると突然固まります。話し合う時間すらないことが多いので対応はとても難しいです。そして、その理由も答えない、答えられない子が多いので、一緒にというよりは子どもに寄り添い子どもを信じて少しでも動きやすい環境を親として整えてあげましょう。
②朝の時間を“楽”にする工夫

不登校の子にとって、朝は一番つらい時間かもしれません。
焦って「早く起きて」「もう学校始まるよ」と言うよりも、好きな音楽をかける・好きな朝ごはんを作る・推し活の話など明るい話題をふる・帰ってきたときにアイス買っておくよなど、心がほっとする時間や帰ってから楽しみがあるような朝の過ごし方を工夫してみましょう。
「朝の雰囲気が変わる」ことも、不登校から回復する小さな一歩になります。
③学校との連携をしっかりとる

子どもは登校の直前に急に学校の不安が頭に浮かびます。普段から担任との連携をとっていると柔軟に対応してもらえます。
特に小学生は連絡帳に書く、タブレットの連絡アプリに入れるなど子どもが安心しやすいようにしてあげましょう。
中学生は、スクールカウンセラーとの連携も大切です。不安感が強い子は話を聞いてもらうことで安心します。
親はどうしても焦って登校を促してしまいますが、スクールカウンセラーに「無理をせず自分のペースでいいんだよ」と言ってもらえると子どもたちは「自分のペースでいいんだ」と安心して通えるようになります。
特に新学年は新しい環境ということで緊張も不安もある時期です。そこを無理して完全不登校にならないようにペースを落として継続的に通えるようにすることも大切です。
また完全不登校の子にとっても新しい担任の先生との連携は復帰に向けてとても大切になります。今からしっかり関係を築いて学校復帰した時に安心できる環境になるようにしていきましょう。
新学年から学校に行けない…不登校と向き合うためのヒント まとめ

新学年から行けないと親としては焦ると思いますが、そこで感情的になってしまうと親子の関係性にも影響が出てしまします。
行けるまで登校を促した方がいいのか、いったん休ませた方がいいかなど、判断に迷ったら1人で抱えずまずは専門家に相談してくださいね。
 不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
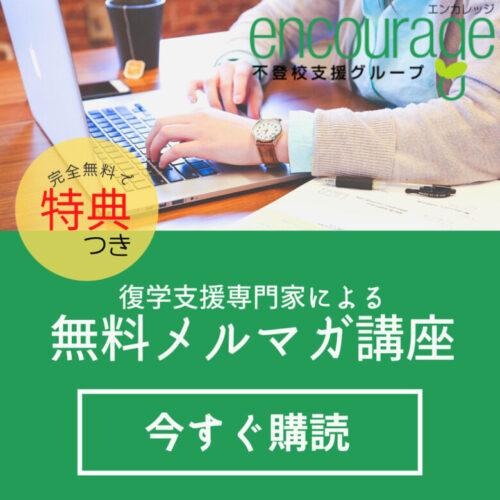 不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!
不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!