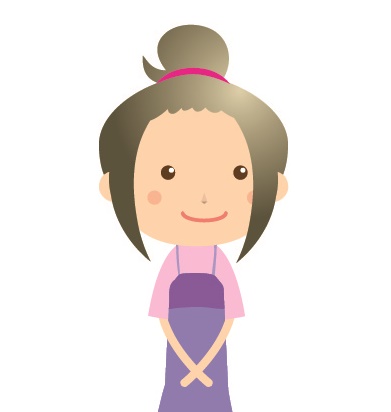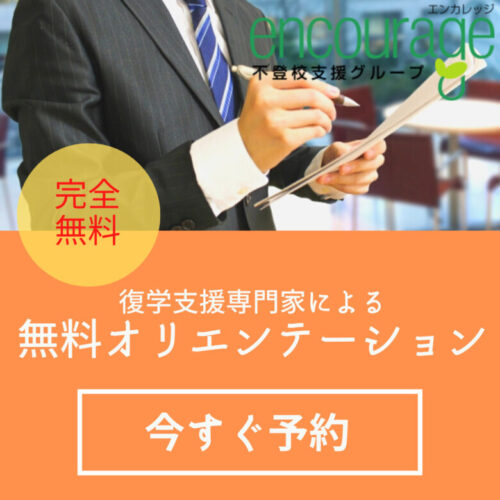子どもが偉そうな態度を取るのは父性の不足!家庭内対応の見直し方

最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)
- 過剰適応起因の不登校の特徴10選|頑張りすぎる子に多いサイン - 2026年1月19日
- 2025年の2学期は6名の子ども達が学校復帰しました! - 2026年1月7日
- 岸和田市 学び舎ゼミでの講演のご報告 - 2025年12月15日
不登校の子育てに奮闘されるお母さんから、こんな悩みをよくお聞きします。
お仕事や家事、そしてお子さんのケアまで、毎日たくさんの役割を抱えながら必死に頑張っていらっしゃるのに、子どもから偉そうな態度や暴言を浴びる…。本当につらいですよね。
「子どもがこんなに偉そうな態度を取るのは普通のことですか?」と時々聞かれるのですが、あまりにも偉そうな態度を取るのは良くないですし普通でもないです。
そして、ここ数年で偉そうな態度を取る子が非常に増えていると私も感じています。偉そうな子どもの数も増えているし、偉そうな態度がどんどんエスカレートしているのも現場を見ていて感じます。
私は公認心理師として1500人以上の不登校支援を行ってきました。二児の父として同じように子育てに悩む経験もしています。
今回は、心理学の知見と支援現場のリアルを交えながら、「なぜ子どもが偉そうになるのか」「どう対応すればいいのか」をお伝えします。
私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1500人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立22年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。
子どもが偉そうな態度を取るのはなぜ?心理学から見る4つの理由

子どもが偉そうな態度を取るのは、人間の本能的なものや、日々の家庭内対応により誤学習してしまっていることが考えられます。
具体的に、子どもが偉そうな態度を取る理由についてまとめていきますね。
自己主張の発達段階とパワーストラグル

心理学では、子どもが偉そうに振る舞うのは、パワーストラグル(権力闘争)と呼ばれる心理状態の表れという考え方もあります。親に「支配されるだけの存在」ではなく、「自分も対等に扱われたい」「コントロールしたい」という気持ちが強くなるのです。
特に不登校の子は、学校に行かないことで親が学校に行かせられない状態を作ってしまうことになり、結果「家庭の中では自分が上位」という状況を作りやすく、親の弱い部分を見抜いて言動をコントロールするようになります。
現場でも「そんなこと言うなら学校行かないから」と登校を交渉材料にしてしまうお子さんは少なくありません。
認知的不協和が生む親の迷い

お母さん自身が「厳しくしないとダメ」という気持ちと「でも登校に影響するのは怖い」という気持ちで揺れると、無意識のうちに矛盾した対応になることがあります。
例えば、「ゲームは夜9時まで」という家庭内ルールを決めたのに、「あと1時間やらせてくれたら明日学校に行くから」と言われてしまうと、迷った結果、「学校に行かないのは困るから仕方ない」とゲームを許してしまうことなどがあります。
こういった、矛盾した認知を同時に抱えた状態を心理学では認知的不協和と言い、子どもはその揺れを鋭く感じ取って、さらに上位に立とうとするのです。「〇〇してくれたら学校に行くから」と言えば思い通りになると誤学習することにもなります。
ダブルバインドによる子どもの混乱
また、矛盾という意味ではダブルバインド(二重拘束)にも注意が必要です。ダブルバインドとは単純に言えば「言っていることとやっていることが違う」ということです。例えばスクールカウンセラーの話を聞いて子どもに「無理しなくて学校を休んでいいよ」と伝えたが、色々な書籍を読むと学校は休ませない方がいいと書いてあり、「学校は休んではいけない」と言う。
このように違うことを言われると子どもはどう思うでしょう。「どっちなんだよ」と混乱して気持ちが揺れ、そこから暴言など偉そうな態度につながる場合もあります。
もちろん、ダブルバインドは親の方にも迷いがあり、自分自身でもわからなくなり混乱してしまうので、親のストレスにもつながっていきます。
エンカレッジでは担当カウンセラーがそれをマンツーマンで丁寧にサポートし解きほぐしていくので安心です。どんな感じか体験されたい方は、現在無料オリエンテーションを行っていますので気軽にお申し込みください。
父性の不在による誤学習

見落とされがちなのが父性の不足です。
心理学でいう父性とは、「ルールや境界線を示し、毅然とした態度で接する役割」のことを言います。子どもに対し「ダメなことはダメ!」とはっきり言うことですね。
私は常々、家庭内は「母性」と「父性」のバランスが大事であると日々のカウンセリングでも、書籍でも、お伝えしてきました。現代は母性が強く、父性が弱いご家庭がとても多いのです。
※「父性」=「父親」ではありません。「母性」=「母親」でもありません。「父性」の対応を「母親」が担う場合もありますし、「母性」の対応を「父親」が担う場合もあります。こちらは状況や家族のパワーバランスによって変わります。
家庭内で父性が発揮されないと、子どもは「親に対して強く出れば自分の思い通りになる」と誤学習し、より偉そうな態度が強化されてしまいます。
父性については、今までもブログで書いてきたので参考にしてくださいね。

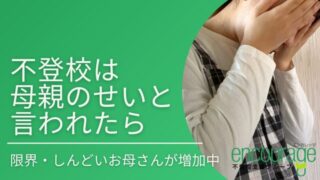
子どもの偉そうな態度に悩む親がやりがちなNG対応

子どもが偉そうな態度をしていると、親御さんは「この関係がずっと続くのだろうか?」と不安になるかと思います。しかし、親が家庭内対応を変えないと、家庭内で子ども上位の関係が続くことが多いです。
そのため、家庭内対応を見直す必要があると思います。
ここからは、私が現場で何度も見てきた、ついやってしまいがちなNG対応を3つ紹介します。
【偉そうな子どもにNGな対応①】不適切な「お願い」と「感謝」

子どもに感謝を伝えることは良いことですが、時と場合によっては良くないことがあります。
例えば、親が通せんぼうを子どもにされて困っていて、何度もお願いして通してもらったら「通してくれてありがとう」といってしまう。
「ありがとう」というのは一見良い対応に見えますが、逆効果です。
本来は「通せんぼうをする」という行動が良くないのに、そこで感謝してしまったら、「良くないことをしても感謝される」という誤学習がうまれます。
このような小さな積み重ねが子どもを偉そうにしていきます。
【偉そうな子どもにNGな対応②】恐怖からの妥協

子どもが大きくなってくると、暴力に訴えるケースもあります。
例えば、「寿司を買ってこい」と親に買いに行かせて、それが気に入らないと寿司をぶちまけて、「内容が気に入らないからもう一度行ってこい」と言う。
親としては怒って父性を発揮すべきところですが、怖いので受け入れてしまうんですよね。そうすると子どもは、「激しいことをすればよりいい効果が得られる」という誤学習をします。
このようなケースでは「昔は素直で優しくそんなことをする子じゃなかった」と親御さんは言いますが、カウンセリングしていくと父性の対応が不足していることが多いです。
【偉そうな子どもにNGな対応③】父性を止める

お父さんが父性対応をしようとすると子どもがかわいそうで止めさせるというお母さんもいます。
父性対応が機能していないケースは、主に以下の2つのパターンがあります。
- お父さん自体が優しくて父性対応をしていないケース
- お父さんが父性対応をしたくてもお母さんが止めてしまった結果、父性対応ができないケース
どちらにせよ、家庭内で父性が機能せず、ますます子どもが上位になって偉そうになるケースも多いです。
子どもの偉そうな態度が父性で落ち着く理由

家庭内は、母性と父性のバランスが大事です。
まだ自分では何もできない赤ちゃんは、母性100%でお世話しないといけません。しかし、徐々に子どもが大きくなるにつれて父性の割合をふやし、周囲の迷惑にならないようなマナーや規範意識、苦しくても頑張る気持ちなどを育てて行くことが大切です。
その子の年齢相応の父性対応ができると、家庭内は安定します。その理由を以下でご説明しますね。
父性により規範意識と安心感が家庭に戻る

父性は、子どもにとって「安心してぶつかれる壁」です。
家庭の中でルールや境界線を明確に示すと、子どもは「〇〇すると怒られるけど、▲▲すると褒めてもらえる」とわかっていきます。生活の中で先の見通しが立つと、子どもは不安が減り落ち着きを取り戻すことも多いです。
会社でもスポーツでも、チームプレーには必ず司令塔となる人がいるはずです。メンバーをまとめる人がいなければ、個人プレーばかりで統率が取れず、力を発揮することはできませんよね。
現場でも、父性対応を導入した家庭は、半年以内に子どもの態度が改善し、再登校につながるケースが多く見られます。
父性は身近で尊敬できる人だから

共働きが増えたとはいえ、まだまだ子どもと過ごす時間はお父さんよりもお母さんが多いという家庭は多いでしょう。
なので、子どもにとって父親は「会話する機会が相対的に少ない人」かもしれませんが、だからこそ一言に重みがあることも多いです。
そして、なんだかんだ子どもは口にしなくても社会で働いているお父さんを尊敬していることが多いので、そんなお父さんの言葉は結構効くものです。特に男の子は父親の言葉が効くことが多いです。
「もうゲーム3時間やったでしょう(そろそろ止めたら)」という言葉も、母親から言うのと父親から言うのとでは響き方が違ったりしますので、父親の存在感も使って家庭内のバランスを取って行きましょう。

父性対応が難しいときは第三者を頼る

家庭内に父性を取り戻すと安定するご家庭は多いです。
ただ、一度誤学習が進んでしまった場合、家庭内だけで父性対応を取り戻すのは難しいことも多いです。お子さんがすっかり偉そうな態度で親の言葉に耳を貸さなかったり、ちょっと厳しいことを言おうとすると部屋に閉じこもったりするからです。
そんなときは、復学支援の専門家が第三者として介入し、子どもに「新しい環境での学習」を促すのが有効です。
エンカレッジはこれまで訪問カウンセリングやコーチングで多くのご家庭をサポートし、100%の復帰率と高い継続登校率を実現してきましたが、このような子ども上位のご家庭に対しては、カウンセラーとして訪問カウンセリングでご家庭に介入し、父性の土台を作ったうえで、父性を親御さんに返すという方法を取っています。
つまり、親子の間に入って家庭内ルールを決めたり、「親に向かってそんなことを言ってはダメだよ」「それはわがままだよ」という社会のルールを教えて父性対応の土台を作り、家庭内が安定してきたら徐々に介入ペースを減らして親子で自走できるようにするのです。
子どもは親に対しては反発しても、第三者から言われるとすんなり言うことを聞くことも多いです。親だからこそ対応が難しい場合もあるので、そのような場合は第三者に入ってもらうことをおすすめします。
※訪問カウンセリングは、公認心理師などの専門資格と豊富な経験、培った知見やキャリア、そして的確なアセスメントがあってこそ成り立ちます。安易に始められるものではなく実際に行っている支援機関もほとんどありません。仮に実施している場合は、その専門性が十分かどうかは慎重に見極める必要があります。
「子どもが偉そうな態度を取るのは父性の欠如!家庭内対応の見直し方」まとめ

近年、偉そうな態度を取る子どもが増えています。しかし、その理由は家庭内対応だけではないと思っています。
昔は地域で子育てしていましたから、両親が多少甘やかしても、近所のカミナリじいさんのような人が適度に叱ってくれたりして、地域で父性が発揮されていました。
不登校もここまで多くなかったので、「学校に行くのが当たり前」という感覚の中、子どもは学校に怖い先生がいてもなんとか折り合いを付けたり我慢して通っていました。
しかし現代では、地域で子育てをしなくなり、学校の先生もあまり怒らなくなったので、子どもが父性に触れる経験が不足しています。そして地域も学校も父性を発揮しなくなって、父性を担えるのが家庭だけになった結果、親御さんが父性対応をしっかり学ばなければいけなくなっているのだと思います。
なので、昔と比べて子育ての難易度がとても上がっていると思います。さらに共働きで、時間的に余裕のないご家庭も増えているでしょう。
なので家庭内で父性が不足しているのは、決してお父さんお母さんの育て方が悪かったわけではなく、地域社会の縮小や学校の教育方針の転換などが絡み合って、そのしわ寄せが家庭に来ているからと考えています。
大切なのは、「毅然とした態度(父性)」を取り戻すことです。親子だけではなかなか大変なので、専門家を頼ることも一つの手です。
そして専門家に相談するときは、ただただ傾聴するだけで具体的な解決策がない、ずっと「心のエネルギーが溜まるまで見守りましょう」という専門家はおすすめしません。なぜなら、子ども上位の場合の対応では見守り・様子見は逆効果になると個人的に考えているからです。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

もしご家庭で「父性が不足しているか?」「これからどうすべきか?」などを悩まれている方は、無料オリエンテーションでもご相談を承っておりますので、ご活用ください。
 不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
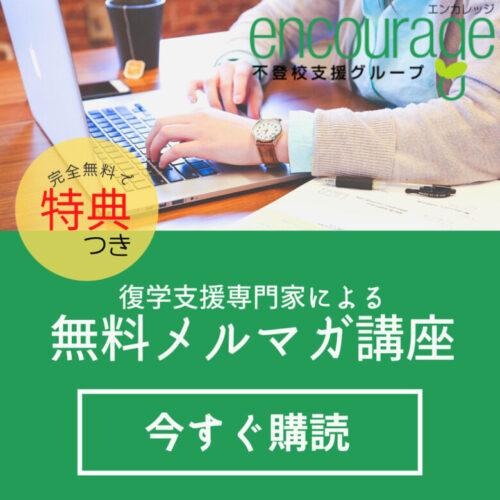 不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!
不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!