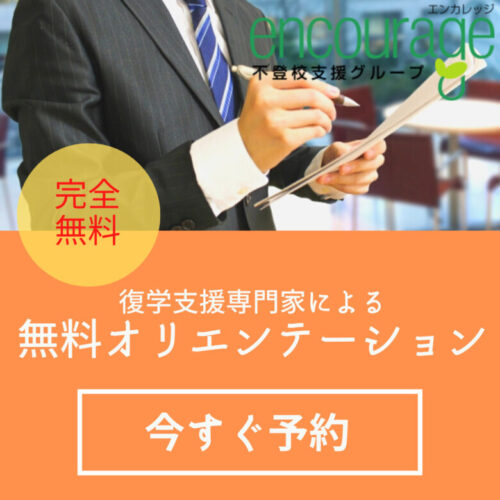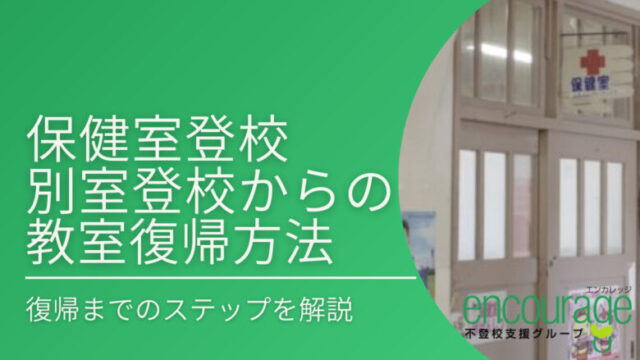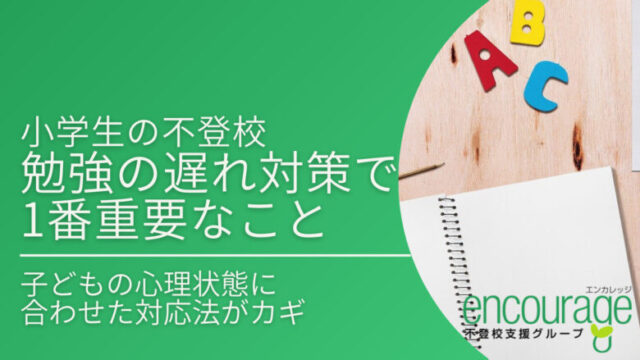不登校理由が「めんどくさい」は要注意!行けない心理とレジリエンスの育て方
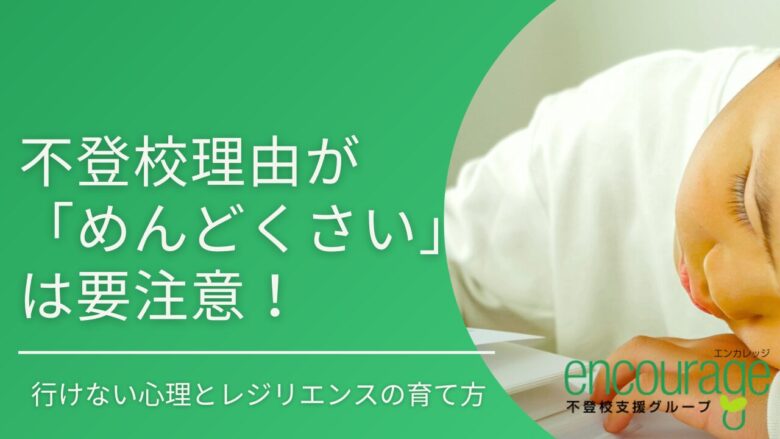
最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)
- 過剰適応起因の不登校の特徴10選|頑張りすぎる子に多いサイン - 2026年1月19日
- 2025年の2学期は6名の子ども達が学校復帰しました! - 2026年1月7日
- 岸和田市 学び舎ゼミでの講演のご報告 - 2025年12月15日
こんにちは!
公認心理師で、これまで1500人以上の不登校の子どもとその親御さんを支援してきた上野剛です。
お子さんの口から「学校なんてめんどくさいから行かない」という言葉を聞いたとき、困惑される親御さんは多いです。「本当にそんな理由で休むの?」と感じてしまいますよね。
不登校の理由は様々ありますが、「めんどくさい」という理由のときは、他の不登校理由よりも注意しなければいけないことがあります。
今回は、「めんどくさい」という子どもの心理と、親ができる家庭内対応について解説します。
私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1500人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立22年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。
不登校理由が「めんどくさい」子の心理

一時代前までは、「めんどくさいから学校に行かない」というのは考えられないことでしたよね。そんなことを言ったら、親や先生から「甘えるんじゃない!」と喝を入れられるケースもあったのではないでしょうか。
しかし現代では、不登校の理由を尋ねると「めんどくさいから」と答える子は少なくありません。
学校がめんどくさくて行けない子は、どのような心理があるのでしょうか。以下でまとめていきますね。
「行けない」のではなく「行きたくない」

不登校の理由が「めんどくさいから」という子は、「行くべきなのはわかっているけど、それよりも行きたくない気持ちが強い」という状態です。
このタイプの子は、心の底で学校に強い恐怖や不安を抱えているわけではないため、本人が「行こう」と決意すれば登校することができます。しかし「行きたくない」と本人が思っているために行けないのです。
ここが対応の難しいところです。「行きたいけど行けない」ではなく、「行きたくないから行かない」なのです。
つまり、行きたくない気持ちを乗り越えるための力、レジリエンスを育てることが大事になってきます。
「不安が強い子」との大きな違い

一方で、不安や心配が強い子は、実は学校に行きたい気持ちを持っています。「友達に会いたいし授業も受けたい、でも怖くて行けない…」という状態です。
この場合は、本人の不安を和らげ、学校が安心できる環境に整うと、比較的スムーズに登校を継続できます。
例えば「先生が怖くて学校に行けない」子であれば、先生が怖いと感じるトリガーを減らしたり、先生は怖くないことを学べばスムーズに登校を続けられるのです。
ところが、「めんどくさい」と感じる子の場合は、不安が取り除かれても、「行きたい」という気持ちがもともと弱いため、登校を継続するのは難しいのです。
実際に支援の現場でも、「不安型」の子は比較的早期に復帰する傾向がありますが、「めんどくさい型」の子は登校してもときどき自主的に休むなど、安定しにくいケースが多いです。
社会が「めんどくさい」を認めていることを知っている
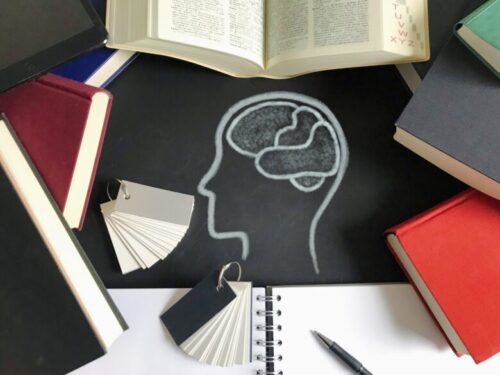
学校がめんどくさいという子は、現代社会が不登校に寛容であることに気付いています。
現代では、「不登校は個性」「学校に行かなくてもいいんだよ」「勉強ができなくても社会で活躍している元不登校」というインフルエンサーの発信が多いですよね。なので、そういった発信を見ていると、「学校に行かなくていいや」と思うのはむしろ自然かもしれません。
人間の脳は、エネルギー消費を節約するために「めんどくさい」と思うようにできています。そうやって習慣化された行動を好み、未知のことに対して抵抗を示すことで消費カロリーを節約することが、太古の時代からの生き延びる知恵でもあったのです。
ただ、現代社会でめんどくさいからと学校をお休みするのは、後々色々なリスクがあるのは以前の記事でも説明した通りです。
子どもが学校をめんどくさいと言うのは、その子だけのせいではなく、現代社会という環境が一因とも言えるでしょう。
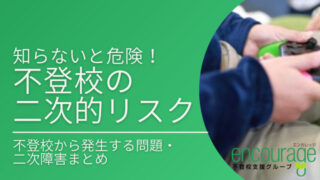
学校がめんどくさい子に親ができるレジリエンスの育て方
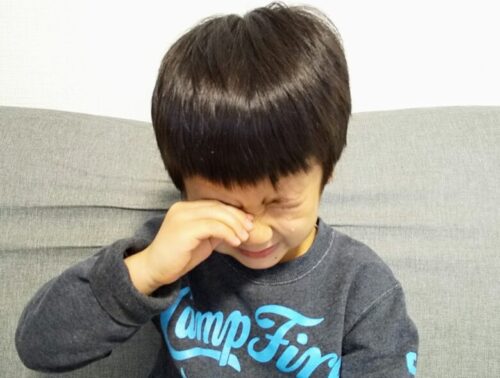
「めんどくさい」という気持ちは、誰にでもあるものです。
大人でも仕事が面倒に感じる日があるように、子どもも学校が億劫になるのは自然な感情です。
しかし、学校に行くべき理由や、自分で選んだ道を続ける力(レジリエンス)が弱いと、「行けるのに行かない」という選択をしやすくなります。
このような子どもは、親が無理に叱って登校させると、反発が強まったり、ますますやる気を失うことがあります。そのため、少しずつレジリエンスを育てられるような家庭内対応が大事だと考えます。
以下で具体的に方法をお伝えしますね。
否定しないで気持ちを受け止める(共感)

子どもが「学校がめんどくさい」というと、「まためんどくさいって言って…」とつい叱りたくなる気持ちもよくわかります。
しかし、そこで否定したり叱ったりすると、子どもは心を開いてくれなくなり、会話ができなくなって悪循環になることがあります。そのため、まずは「学校が面倒に感じるんだね」と共感してあげてください。
安心感があると、子どもは本音を話しやすくなるからです。
ただ、注意すべきは「共感と同調・同意はちがう」ということです。これを混同されている方が結構多いのでみなさんも注意してください。
「共感」「傾聴」というと、何でも相手の言う通りに聞いてあげる、相手の言うことを受け入れると思っている方もおられますが、こちらが同意できなければ相手の言うことを正面から受けなくてもいいんです。
例えば「学校に行けないのはお母さんのせいだ!もう僕の人生おしまいだ、申し訳ないと思うならお金出してよ!」と子どもが言ったとします。こう言われたら、あなたならどうしますか?
同意・同調するなら「ごめん、お母さんが悪かったね、お金はあげるから」となります。しかしこれでは、子どもは誤学習して、毎回お金を要求するようになるでしょう。「自分はお母さんより上の立場だ」と勘違いするかもしれません。
一方で、共感するなら「学校に行けないから人生終わりだと思っているんだね、本当は行きたかったのかな。」などと、聞き返したり確かめの言葉をかけるなどして相手の言葉を引き出します。
共感は、必ずしも相手の言葉に同意しなくていいんです。お金の要求など、無理なことなら尚更です。しかし、共感と同調を混同する親御さんが多く、共感しているようで実は同調になっていて子どもが自分が立場が上かのように勘違いしてしまい、レジリエンスが育たないことがあります。
このように、共感や傾聴は実は絶妙に難しかったりするので、慣れていない方は思考の練習が必要です。
小さな成功体験を積み重ねる

小さな成功体験や達成感を積み重ねることもレジリエンスを育てる上で重要と言われています。
「今日は1時間だけ行ってみようか」のように、小さな挑戦と成功を積み重ねることで「やればできる」という感覚が芽生えることがあります。
人間は本来「成長したい」という欲を持っているものです。赤ちゃんや幼児を見ていると、好奇心と挑戦したい気持ちが旺盛ですよね。それが成長するにつれて、人間関係に疲れたり、プライドから挑戦が怖くなったりして、めんどくさい気持ちが大きくなることがあるのです。
そのため、レジリエンスを育てるためにも、お子さんが何かに集中・熱中する時間を持ったり、達成感を感じられることを積極的にしてきましょう。
「うちの子は何なら熱中できるか?」をしっかり観察していきましょう。そこにレジリエンスを伸ばすヒントがあるはずです。
「継続登校しにくい」という覚悟をしておく

不登校理由が「めんどくさい」の子は、一度行けるようになっても、たまに「自主休業」をすることはよくあります。
休む度に「せっかく登校再開したのに、また休んだ…」と親御さんは落ち込むかもしれませんが、このタイプの子は継続登校しにくいのは仕方がないです。そのため、親御さんが落ち込まないように、継続登校はしにくいとあらかじめ覚悟しておきましょう。
あらかじめ覚悟していれば、いざお休みするとなったとき「あぁ、またきたか~」と親御さんが受け流せるようになって、気持ちがラクになると思います。特に長期休み明けなど環境の変化が大きいときはなおさらです。今の子は環境の変化に適応するのに時間がかかるので、親が焦らず気持ちに余裕があるというのは非常に大事です。ですので、あらかじめ覚悟することで慌てない仕組み作りをしていきましょう。
「不登校理由が「めんどくさい」は要注意!行けない心理とレジリエンスの育て方」まとめ
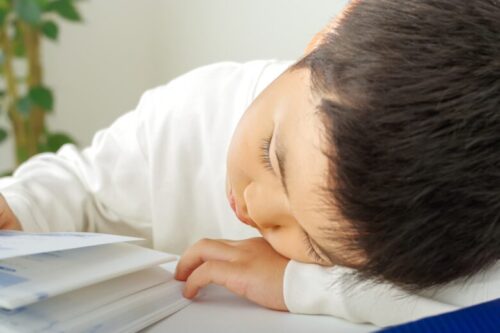
「めんどくさい」という言葉は、行きたくない気持ちが勝っている状態の表れです。
不安が強い子のように「行きたいけど行けない」のではなく、「行けるけど行きたくない」状態なので、継続登校には時間がかかることが多いです。
長年不登校支援をしていると「子どもが行きたくない学校に無理に行かせるのか?!」という批判の電話を頂くこともあるのですが、確かに「行きたくなければ行かなくていい」という選択肢もあると思います。多様性の時代ですので、そのような考えの方は、お子さんを学校に行かせなくて良いと思います。
また、いじめられていて辛い。孤独を感じて眠れない、食事もとれないなどの状況であれば行かせてはいけません。
しかし、「めんどくさい」という理由で学校を休んでいると、就職してからも「めんどくさい」という理由で仕事に行きたくなくなってその子自身が困るのではと考える親御さんも少なくないです。
危機をもってカウンセリングに行くと「焦らず、待ちましょう」「1年、2年のスパンで見守っていきましょう」とおっしゃるカウンセラーさんも少なくないので危機感も薄れて安心できます。しかし、見守り続けて動けなかったときに支えるのは親であるということもしっかりと見据えて考えないといけません。
エンカレッジでも、子どもを無理に登校させることはしていません。なので、「学校がめんどくさい」と言う子にはレジリエンスの大切さを伝えています。
学校がめんどくさい子に必要なのは、レジリエンスを育てることです。一朝一夕にできるものではありません。特に親子間ではどうしても甘える気持ちが出たりするので、できれば第三者に入ってもらって思考のクセをコーチングしてもらうのが早道ではあります。
もしイマイチ家庭内対応がうまくいかない、改善していないように思える等がありましたら、エンカレッジでもご相談を承っていますので活用ください。
 不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
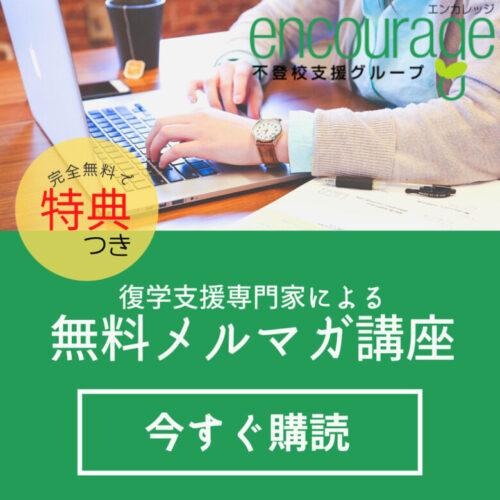 不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!
不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!