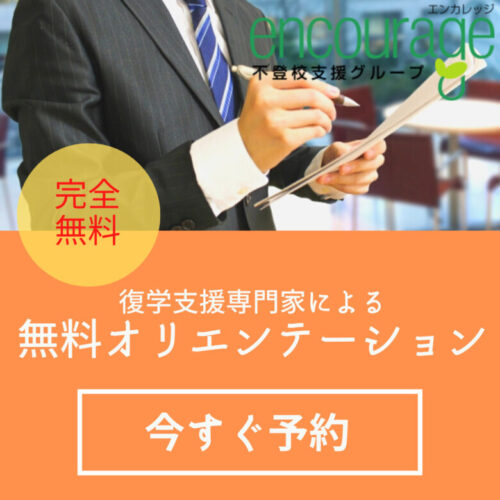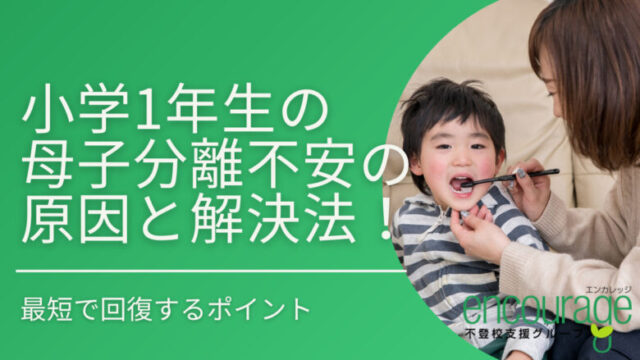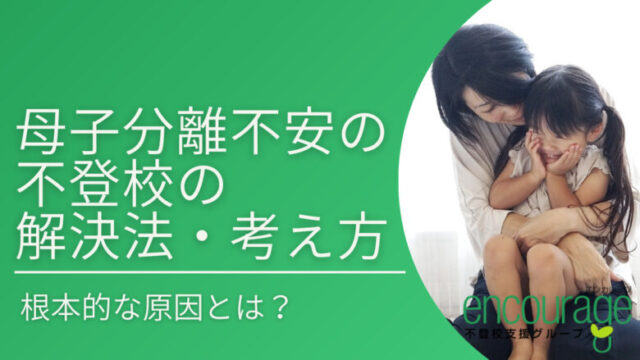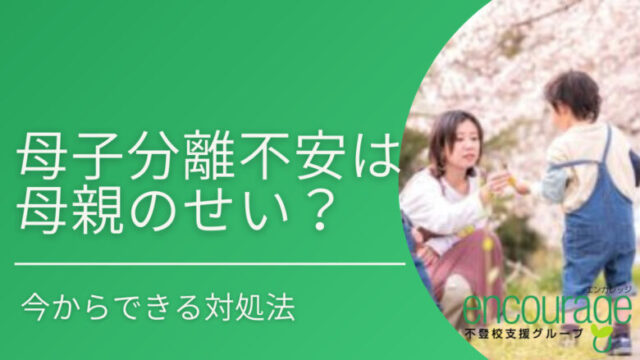不登校の子が赤ちゃん返り?2つのタイプ別に見る心理と対応法

最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)
- 過剰適応起因の不登校の特徴10選|頑張りすぎる子に多いサイン - 2026年1月19日
- 2025年の2学期は6名の子ども達が学校復帰しました! - 2026年1月7日
- 岸和田市 学び舎ゼミでの講演のご報告 - 2025年12月15日
不登校になると、「小さい子のように甘える」「癇癪を起こす」「身の回りのことをしなくなる」など、いわゆる赤ちゃん返りのような行動が見られることがあります。
そこでネット検索をすると「不登校の子が赤ちゃん返りしたら、甘えさせてあげましょう」「心のエネルギーがたまるまで待ちましょう」という情報があるので、どうすべきか戸惑ってしまう親御さんが多いのではないでしょうか。
そこで今回は、1500人以上の不登校支援を行ってきた公認心理師である私が、赤ちゃん返りの心理と対応法を整理してお伝えします。
私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1500人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立22年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。
不登校の子の赤ちゃん返りの2つのタイプと対処法

子どもが赤ちゃん返りすると、程度にもよりますが、親御さんは「うちの子、大丈夫かな…」と心配になりますよね。
しかし、赤ちゃん返りは珍しいことではありません。むしろ、不登校支援の現場にいると非常によく見る光景です。
そしてこの赤ちゃん返りは、大きく分けて2つのタイプがあると思っています。このタイプごとの対応が、状況改善のカギになります。
【赤ちゃん返りのタイプ①】癇癪型

このタイプは、感情のコントロールが難しくなり、怒りや反抗が増えるのが特徴です。
「嫌だ」「行きたくない」「やめて!」と強く主張するので、親が子どもに合わせて行動することが増え、子どもが「親は自分に合わせてくれる」と誤学習してしまうのです。
このように、親が何でもかんでも子どもに合わせて行動することが当たり前化してしまうと、家庭内のパワーバランスが崩れ、子ども上位になってしまいます。
そして、子どもが一層親の提案や指示を受け入れにくくなっていき、癇癪を起こすことも増えていきます。なぜなら、子どもは「わがままを言っても受け入れられる」と誤学習しているからです。
結果、赤ちゃんのようになることで自分の要求を通そうとするようになります。これが癇癪型の赤ちゃん返りです。
このケースは、まず家庭内の子ども上位を改善することを試みます。
【赤ちゃん返りのタイプ②】母子依存型

こちらは過度に親に甘え、何も自分でしなくなるのが特徴です。
学校に行けない不安が強いため、母親への依存が加速し、「一人では何もできない」「常に一緒にいてほしい」と訴えるようになります。
親側も「可哀想だから甘えさせてあげよう」と思うことで、さらに依存関係が深まりやすくなります。
このタイプでは、少しずつ「自分でできることを増やしていく」ことを意識しましょう。お母さんが外で仕事をしたり、1人時間を確保するのも子どもの自立を促すのでおすすめです。
ただ、急激に自立を促すと「突き放された」と感じて逆効果になることもありますので、その点はスモールステップでやっていきましょう。
赤ちゃん返りのときに甘えさせるのは良いこと?

「不登校の子が赤ちゃん返りをしたときは、甘えさせてあげましょう」という意見もネット等でよく見ますが、ただただ甘えさせるのは注意が必要だと思っています。子どもの自立を阻む可能性があるからです。
特に「おもちゃ買って」のような甘え方は、子ども上位に繋がりやすいので応えるのは避けましょう。
しかし、お風呂や一緒に寝ることに関しては、子どもが望むうちはいいと思っています。「不安だから一緒に入って欲しい」「不安だから一緒に寝て欲しい」ということは、現時点で自立面が不足しているものの、そのうち自立すれば自然と自分から離れていくからです。
なるべく自分で考えて行動できるように促してくことは大切ですが、強制的に離すことは逆に分離不安にある可能性があるので、無理にする必要はないです。
きょうだいが赤ちゃん返りするケース

不登校の子どもがいると、親のエネルギーはどうしてもその子に集中します。
その結果、兄弟姉妹が「自分を見てほしい」という気持ちを抱き、赤ちゃん返りのような行動を見せることがあります。
これは意識的に起こす子もいれば、無意識で出る子もいます。
このような場合の対処ポイントは、特別な1対1の時間を作ること。
例えば、「今日はママと2人でカフェに行こう」「内緒で映画を観に行こう」といったこっそり特別時間を持つと、「自分も大切にされている」と安心でき、赤ちゃん返りをする理由が無くなります。
子どもにとって、大好きな親と一緒に過ごす時間は嬉しいものです。家にいると家事や雑務で集中できないことも多いので、やはりおすすめは親子2人で外出し、スマホも極力見ないで《今の子どもとの時間》だけを楽しむこと。
すると子どもも「ママはしっかり僕を見てくれている」と安心し、赤ちゃん返りのような言動がなくなっていくことが多いです。
「不登校の子が赤ちゃん返り?2つのタイプ別に見る心理と対応法」まとめ

「赤ちゃん返りをするのは愛情不足のせい」のようなネットの書き込みをみて不安に感じる親御さんも多いですが、赤ちゃん返りは愛情不足が原因ではありません。
「赤ちゃん返りしたら甘えさせてあげるのがいいのか?」と悩む方も多いのですが、いい甘え方と良くない甘え方があるので、こども上位になるような良くない甘え方は対応しないようにして、「一緒に寝たい」等のような不安感を軽減するような甘えは対応してあげると良いでしょう。
ちなみにエンカレッジでは、不登校の子が赤ちゃん返りをしたときは以下を注意深く観察します。
- 子どもは年齢相応の自立ができているか
- 家庭内でこども上位がどのくらいあるか
もし自立不足であれば、無理な自立促しはかえって不安を煽り母子依存に繋がる可能性もあるため、少しずつ自立できるようにサポートしていきます。
もしこども上位があれば、「癇癪を起こせば言うことを聞いてもらえる」という誤学習を正し、家庭内のパワーバランスを整えるところから始めます。
やはり大事なのは、子ども1人1人をしっかりアセスメント(分析)するところだと思います。赤ちゃん返りをする原因をしっかり分析することができれば、親の取るべき対応の方向性が見えてくるので、その正しい方向性の中での甘えは認めてあげると良いと思います。
そして、そのうち子どもは自然と甘えてこなくなるので、それが自立のサインです。
もし、思うように自立のサインが出てこないと感じたとき、どこまで甘えを認めるべきかで悩んだときは、エンカレッジの無料オリエンテーションでもご相談を承っておりますので、ご利用くださいね。
 不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
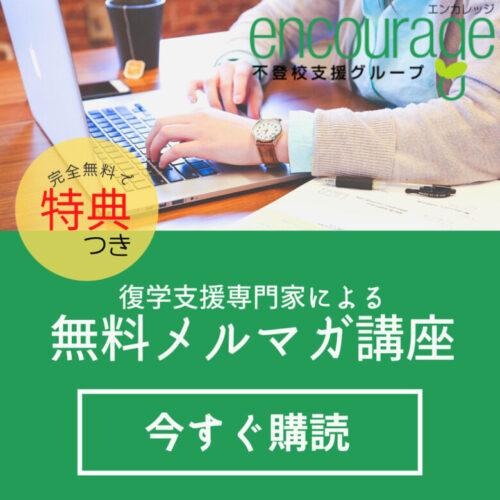 不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!
不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!