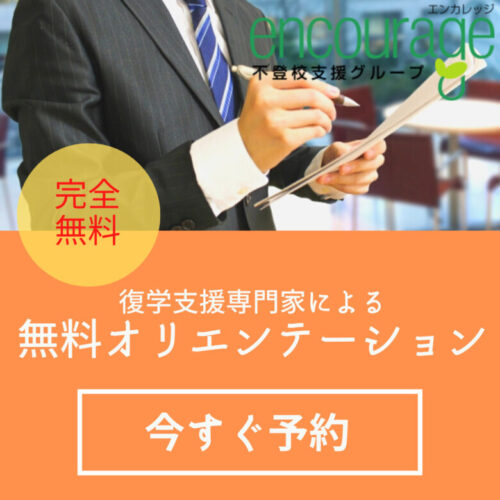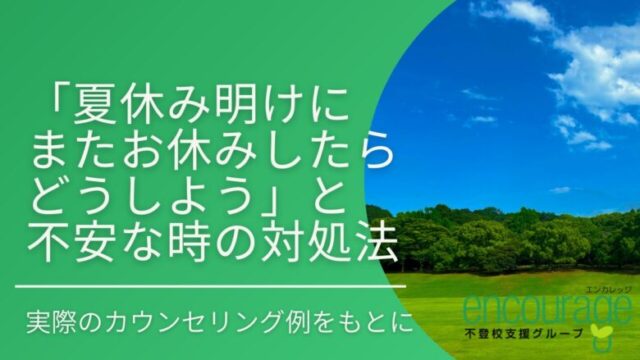母子分離不安が「母親のせい」と言われつらい方へ。専門家のアドバイス

最新記事 by 監修者:上野 剛 (全て見る)
- 過剰適応起因の不登校の特徴10選|頑張りすぎる子に多いサイン - 2026年1月19日
- 2025年の2学期は6名の子ども達が学校復帰しました! - 2026年1月7日
- 岸和田市 学び舎ゼミでの講演のご報告 - 2025年12月15日
保育園に預けるとき、「ママ~!」と泣かれる…胸が締め付けられるような思いで、子どもを預けて仕事に行くお母さんは多いですよね。
親と離れる不安は、子どもならば誰でもあるものです。むしろ、しっかりと親子の愛着が育っている証拠でもあります。
しかし、小学校に上がってもまだ母親と離れることに強い抵抗がある場合、母子分離不安症という診断名がつき、原因は親の過保護・過干渉が多いので家庭内対応を気をつけようという方向性になるかと思います。
実際エンカレッジでも、母子分離不安のクライアントには、自立心を養うような家庭内対応の仕方をお伝えしています。
しかし本質的に見るべきは、なぜ母親が過保護・過干渉になってしまうのかという社会的背景です。
多くのお母さんは、「この子をちゃんと守りたい」「一人前に育てたい」「失敗して傷つかせたくない」という善意と責任感から動いており、「過保護になりたい」「干渉したい」と思っていないにも関わらず、つい過保護・過干渉になっていますーーーしかも、自分に多大な犠牲を強いて。
今回は、現代のお母さんたちを過保護・過干渉に向かわせる現代日本の社会的構造について、私の意見をお伝えしていきたいと思います。
私たち不登校支援グループエンカレッジでは、今まで1500人以上の子どもたちの復学をサポートし、設立22年の現在も復学率は100%を維持しています。不登校に悩む方向けに無料のLINEやメルマガの発信もしておりますのでご活用ください。
母子分離不安の根底にある「母親の不安感」

なぜ現代のお母さんたちは過保護・過干渉になりやすいのでしょうか?それは、社会全体が母親を不安にさせやすい構造を持っているからです。
母親の不安を掻き立てる5つの要因を見ていきましょう。
【母親の不安の原因①】ネット・SNS

ネットやSNSは、上手く使えば情報収集等で便利に使えますが、気づけば心を侵食していることも多いですよね。
特にSNSには「理想の子育て」や「成功体験」が溢れています。
そうした投稿を見るたびに、周囲と比較して「私も頑張らなきゃ」と自分を追い込んだり、「こんなかわいいお弁当を作ってあげられなくてごめんね」と自分を責めたりしていませんか。
小さな子どもが大人顔負けのピアノ演奏をしているのを見て「うちの子はまだ…」と落ち込んだりしていませんか。
このような投稿を見続けると無意識に自己肯定感が下がっていきます。
SNS投稿の多くはハイライトであり現実のすべてではないこと、人と自分を比べるのは良くないことだとわかっていても、潜在意識に「自分はダメだ」「自分の子はダメだ」と刷り込まれていくことに注意しましょう。
【母親の不安の原因②】共働き等による忙しさ

現代の母親の多くは、家事・育児に加えて仕事も担っています。物理的な時間のなさに加え、常にマルチタスクで動く疲労感もあるでしょう。
そんな中で、つい時間短縮のために本来子ども自身でやるべきことも親が片づけてしまうことがあるかと思います。子ども自身がパンにバターを塗ると失敗したときに片付けが大変になるからと、お母さんがバターを塗ってあげるなどです。
このような「先読み」の親の行動により、子どもが自分で経験することが少なくなり、その結果として自立心が不足することになります。しかしこのとき、本来子どもがやるべきことも親がやることで、親自身がタスクが増えて疲弊しているケースもとても多いのです。
つまり、子どもにとっても親にとっても良くない循環が起きているのです。しかし、この循環をやめることができないですよね。
それは、「出勤時間に遅れないように」「風邪を引いて休みにならないように」というプレッシャーが、親を掻き立てているのではと感じます。
【母親の不安の原因③】幼児教育・中学受験の過熱
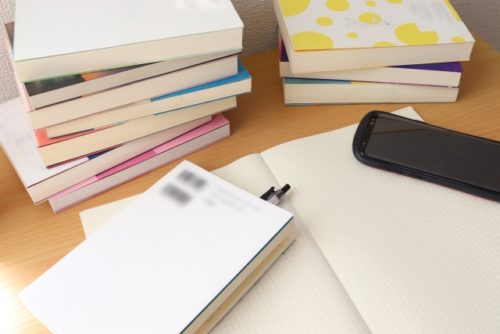
「小1から塾」「英語もプログラミングも早めに」——。
こうした早期教育ブームも、親の不安を大きくする一因に思います。2025年入試の中学受験者数は前年より減少したものの、それまでは10年近く右肩上がりに受験者数は増えていました。
2024年入試で過去最高の受験率に達した首都圏(1都3県)の中学入試。直近の25年入試の受験者数は、日能研の推計で6万2200人と昨年から3000人以上の減少となり、15年から右肩上がりを続けていた受験率は21.5%と、10年ぶりの減少に転じた。
引用:ダイヤモンドオンライン「【首都圏の中学受験最前線!2026年入試版】25年入試は御三家が総崩れ!11年ぶり「サンデーショック」の26年入試を占う」(2025年5月1日)
これほど多いと「うちも乗り遅れないように」と焦ったり、金銭的にも時間的にも無理をしてでも受験させたいと考える人が増えたりして、余裕のない人が多くなっている気がします。
【母親の不安の原因④】女性の生き方の多様さ

社会の変化により、女性の生き方は本当に多様になりました。
仕事を続ける、家庭に専念する、半々にする——どの選択も尊重されるはずなのに、現実は「どの選択をしても批判される」ことが多いと感じている方もおられるのではないでしょうか。
- 「働いてるから子どもが寂しがるのかも」
- 「家にいても、結局何もできていない」
- 「3歳までは母親が育てるべきって、義母に言われた」
そんな「何を選んでも報われない感覚」が、母親が幸福を感じられにくい環境を作っているのではと感じます。
【母親の不安の原因⑤】孤独

そして何より深刻なのが、孤独です。
昔は地域や親戚とのつながりの中で、自然に育児の知恵や共感を得られました。みなさんが子どもの頃も、近所に「カミナリじいさん」や「おせっかいなおばあさん」がいなかったでしょうか。
今は核家族化とオンライン化で、「悩みを話せる相手がいない」「本音を出せない」お母さんが急増しています。同じ保育園や小学校に子どもが通っているのに、お互いに名前も顔も知らない人が多いですよね。
実際、心理学研究でも「社会的サポートの少なさ」は不安や抑うつのリスクを高めることが分かっています。
孤独を抱えるほど、母親は自分の内側で問題を抱え込む傾向が強まるのです。
母子分離不安のときの母親のメンタルの整え方

では、そんな時代に生きる母親は、どう心を守ればいいのでしょうか。
ここからは、専門家としてお伝えしたい4つの視点です。
母子分離不安が増える社会的構造を知っておく

まずは「母子分離不安=母親の問題」ではなく、社会の構造が母親の不安を煽っていることに気がつくことが大事です。
お母さん自身が、実は心の中に不安を抱えていて、その不安感が過保護・過干渉のような子どもへの接し方に繋がっているという仕組みを知るのです。
「自分は不安に立ち向かおうと、過干渉になっているんだ」と気づくだけで、対処法も色々と見えてきますし、心の重荷も少し軽くなります。
自分の時間を持つ
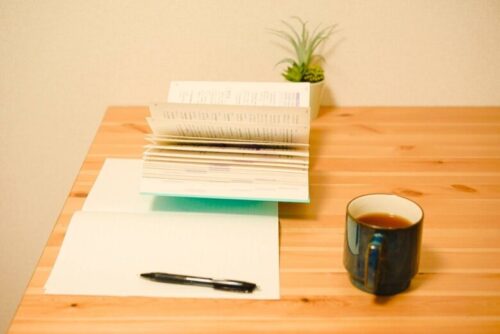
罪悪感を感じるかもしれませんが、自分だけの時間は必要不可欠です。
疲労や睡眠不足が蓄積すると、脳は「危険信号(アラーム)」を誤作動させやすくなります。つまり、あなたの不安は脳の疲れでもあるのです。
1日15分でもいいので、子ども抜きで散歩したり、コーヒーを飲んだり、大好きなスイーツを食べたりする時間を持ちましょう。
ちょっと気持ちに余裕ができると、それだけで頭がスッキリして、前向きになれることも多いです。
自分の価値観の軸を持つ

情報が多い時代ほど、「何を信じるか」の軸が必要です。
「うちの子に合うのはこれ」「私はこうしたい」と明確に言えると、他人の意見に振り回されなくなります。
軸を持つとは、頑固になることではなく、柔軟に選択する自信を持つこと。その自信が、子どもに安心を与える最大の力になります。
仕事を続ける

「仕事をしてるから子どもが不安なのでは」と悩む方も多いですが、私は多くのケースで、仕事を続けたほうが母親も子どもも安定すると感じています。
仕事を通して社会とつながることは、「母親」という役割以外の自分を保つことになり、気分転換になるという方も多いです。現実的な話、経済的な余裕は精神的な余裕に繋がることも多いので、仕事を続けたい方は続けた方が良いと思います。
さらに子ども側も、お母さんが仕事をしていると何でもかんでもお母さんに世話してもらえなくなるので、結果的に自立が促されることが多いからです。
もしお子さんがいじめなどの心の傷を負って、そのケアをしなければいけないなどの事情があれば仕事をやめて家事育児に専念するのも良いと思いますが、単なる母子分離不安の場合は仕事を続けることをおすすめします。
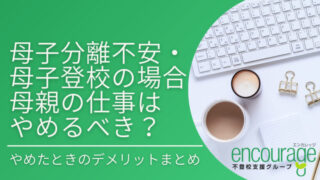
「母子分離不安が『母親のせい』と言われ辛い方へ。専門家のアドバイス」まとめ

母子分離不安は、母親のせいとは言えません。
確かに過保護・過干渉は母子分離不安を招くことがありますが、そもそもなぜ母親が自ら望んでいないのに過保護・過干渉になってしまうのかという社会的構造に目を向ける必要があります。
現代社会は母親が不安を抱えやすい構造をしています。
だからこそ、自分を責めるのではなく十分頑張っていることを労って、不安な気持ちに気づきましょう。そして、その不安感に向き合うのです。
お母さんの不安感が減ってくると、子どもに対しても大らかな気持ちになれます。子どもの持ち物を全部を確認していたお母さんが「宿題を忘れても、まぁ、いっか」と構えられるようになると、自然と子どもが自分で持ち物確認をするようになっていくものです。
もし不安感が消えない、完璧主義をやめられないようなときは、お母さん自身が過去のトラウマを抱えているのかもしれません。エンカレッジでは不登校の子の親御さんのカウンセリングも承っておりますので、ご希望の方はご相談ください。
 不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
不登校情報が無料配信されるエンカレッジのLINE。 「子育て診断テスト」が無料で受けられます!
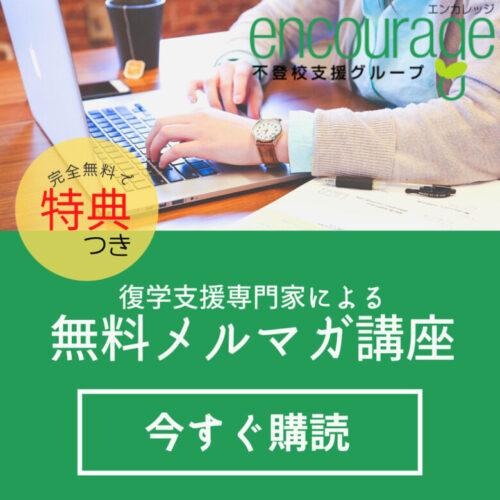 不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!
不登校を解決する親の考え方が学べる無料のメール講座。 今ならご登録で「家庭環境改善マニュアル」をプレゼント!